夏の暑さがじりじりと照りつけ、竹垣に囲まれた茅葺きの家も、まるで蒸し風呂のようになっていた。
指月は扇子をせっせとあおぎながらも、額の汗は一向に止まらなかった。
外からは蝉の声が響き、まるで暑さに比例して大合唱が激しくなっていくかのようだった。
山裾の村人たちも、家の中にじっとしていられず、大きな木陰に涼を求めて集まっていた。
そんな様子を見て、指月は祖父に尋ねた。
「祖父は扇子も使わないで、暑くないのですか?」
祖父はにっこり笑い、静かに一首の詩を口ずさんだ。
皆は暑さを避けて右往左往、
ただ禅師のみ房を出ず。
禅房が暑さを免れたわけではなく、
心が静かであれば、身もまた清らかに涼し。
指月は、それを聞いてすぐに気づいた。
祖父が、夏に扇を使わず、冬に炉を頼らないのは、心の内に静けさがあるからだ。
暑さというのは、外気よりも、むしろ内なる“いら立ち”によって増すのだ——と。
突然、入り口の扉を叩く音がした。
指月が戸を開けると、息を切らせた、ひとりの農夫が立っていた。
顔色が悪く、すぐにでも診る必要がありそうだった。
「中へどうぞ」
農夫は咳き込みながら中に入り、そのまま診察机の椅子に腰を下ろした。
指月が尋ねた。
「どうされたんですか?」
農夫は答えた。
「暑い中で畑仕事をしてたら、汗がどっと出て、そのあと急に頭が重くなって、力が抜けて……。木陰で少し休もうと横になっていたら、今度は寒気がしてきたんです。身体はだるく、鼻も詰まって、もう何もする気になれんのです」
指月は頷きながら言った。
「それは……たぶん“冷え”ですね」
農夫は目を丸くして聞き返した。
「こんなに暑いのに、“冷え”ですって?」
冷えと言ってみたものの、いざ説明するとなると指月は困ってしまった。
見かねた祖父は咳払いをして話を引き取った。
「夏は暑さを避けて涼しい場所に逃げ込みがちだが、風に当たりながら眠ったり、冷たい地面に長く横たわったりするのは、かえって体を冷やしてしまうんだ。君のように、めまいや寒気がして、身体がだるいというのは、“陰暑”という症状だよ」
そして祖父は、指月に問うた。
「さて、この場合はどうする?」
小指月はきっぱりと答えた。
「その邪が表にあるならば、“汗で追い出す”のが基本です」
祖父は続けて問う。
「その通りだ。だが、どれを使う? “発汗して邪を払う薬”はたくさん種類がある。なぜだと思う?」
指月は少し考えてから答えた。
「病には軽重があり、薬には“季節”があるからです。秋冬は寒いので腠理が強く閉じています。なので、麻黄のような強い薬でなければ汗を出せません。一方、春夏は毛穴が開いているので、香薷のようにやさしく汗を促す薬で十分に体表から邪を祓えます」
祖父は満足そうにうなずきながら言った。
「ならば、香薷を一両ずつ、二包用意して、この農夫に渡しておあげ」
指月はあらかじめ準備していた香薷の包みを二つ取り出し、農夫に手渡した。
実は、祖父はすでにこの夏の時期に“陰暑”の患者が多くなることを見越して、香薷を多めに用意していたのだった。
「この香薷の煎じ薬は、あまり長く煮すぎないよう気をつけてください」
指月はさらに念を押した。
「長く煮ると香気が飛んでしまって、効き目が落ちてしまいます。飲むときは少し冷ましてから飲んでください。熱いままだと、かえって吐き気が出やすくなります。この薬は独特な香りを持っていて、冷やして飲むことで“暗度陳倉(ひそかに働いて)”くれるんです」
農夫は「暗度陳倉(ひそかに働く)」という表現の意味はわからなかったが、「煎じすぎず、冷やして飲み、風には当たらないようにする」とだけは、しっかり覚えて帰っていった。
「暗度陳倉」は、表面上は別の行動をとって、相手の注意をそらし、裏では別の目的を達成する戦略や行動を指す中国の故事成語です。現代では、表面上は別の行動をとって、相手を欺き、裏では別の目的を達成する戦略や行動を指す際に使われます。
一服飲んだだけで、胸のつかえが取れ、頭のふらつきも消えた。
うっすらと汗をかくと、体のだるさも消えていった。
二服目を飲み終えるころには、鼻づまりも咳もすっかり治まり、元気を取り戻した農夫は、また田畑へと出かけて行った。
「人間って不思議だなぁ」
指月はつぶやいた。
「ちょっと体調を崩すだけで、一歩も歩けなくなるのに、治れば、まるで龍や虎みたいに元気になる。やっぱり、体と心が健康って本当に大切なんだな」
「知っているかい? 李時珍はこう言った。“香薷は夏の時期に用いる発汗解表薬であり、それは冬に用いる麻黄の如し。” だから、夏に冷えを感じて発症する感冒(陰暑)には、香薷こそが特効薬なんだよ。そのため香薷は“夏の麻黄”という美称を持ち、夏季の感冒治療における専用薬とされているんだ」
「でもね」と、祖父はさらに続けた。
「医者が香薷を使って“陰暑”を治せるても、それではまだ半人前だ。もっと大切なのは、なぜ陰暑になるのかを理解することだよ。薬で治ったからといって、それを忘れてまた木陰で寝たり、風に当たったり、氷で冷やしたスイカを食べたりしていれば、またすぐに同じ病気にかかってしまうからね」
指月はそこで尋ねた。
「祖父? 病を“根本から治す薬”ってあるのでしょうか?」
祖父はいつものように笑って答えた。
「ないよ。感冒だって、一生のうちに何度もかかる。薬で“根治”することなんてできないんだよ。本当に大切なのは、日々の暮らし方そのものさ。風寒に気をつけ、食を慎み、心身を大切にし、怒りに囚われないこと——これが本当の“根治の薬”なんだよ」
指月は大きく肯くと、すぐにペンを取り、ノートにこう書き記した。
養生の四か条:
一、風寒を慎むこと
二、飲食を節すこと
三、精神を惜しむこと
四、怒りを慎むこと
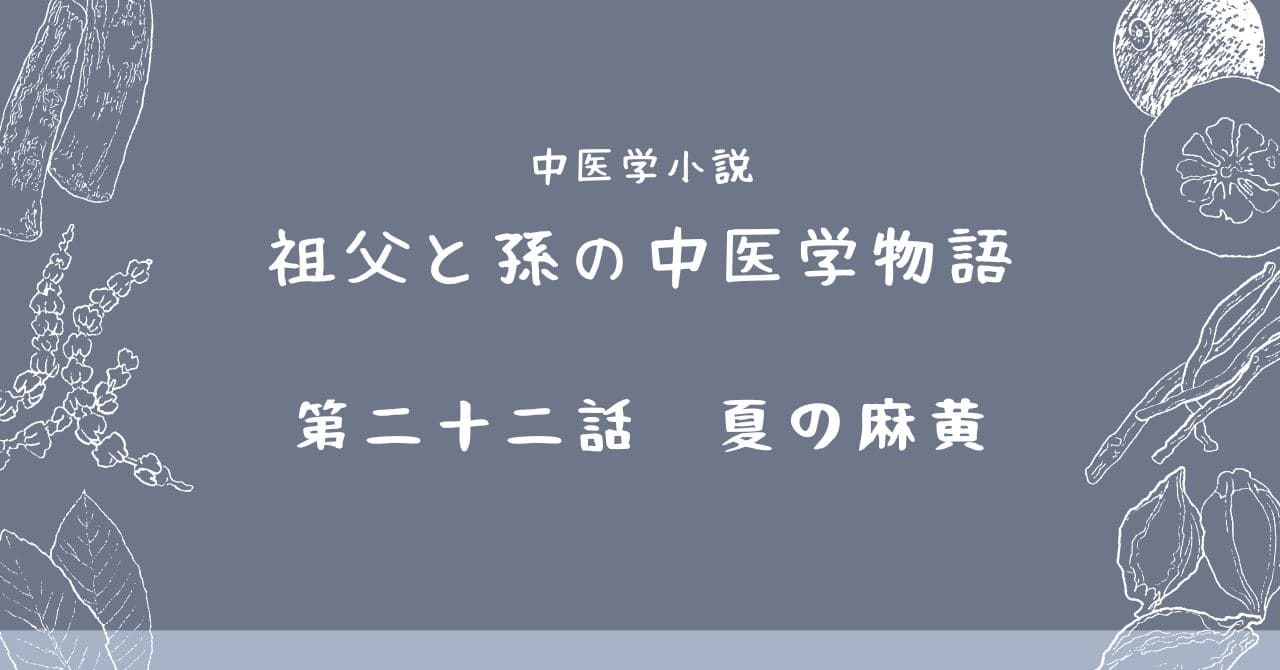

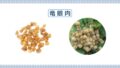
コメント