南方では水腫や脚気に悩む人が多い。
なぜなのか?
それは、湿気は下に集まりやすい性質があるからだ。
南方は雨が多く土地も低いため、湿邪にやられやすい。
だからこそ、南方で病を治すには、まず湿を除く術を知らなければならないと、祖父はいつも指月に言っていた。
「手に三本の傘(散)を持てば、一日中歩き回れる」という俗諺がある。
その三本の傘とは、銀翹散・藿香正気散・五苓散のことを指す。
十日以上も雨が降り続き、天地はまるで水の中に沈んだような景色になった。
太陽の姿を何日も見ておらず、指月は口をとがらせながら「僕までカビが生えそうだ」とぼやいた。
窓辺にかかったタオルを見やると、しっとりと濡れて重たそうに垂れている。
急に祖父が質問をしてきた。
「指月よ、このタオルは上半分が重いか、それとも下半分が重いか?」
指月は頭をかきながら、「また何を試されているんだろう」と考えたが、すぐには答えが出てこなかった。
祖父はさらに尋ねた。
「じゃあ、上半分と下半分、どっちが乾いてる?」
指月がタオルに触れてみると、上半分はほとんど乾いているのに、下半分はまだずっしりと湿っていた。
祖父はさらに問う。
「さて、そこから何がわかる?」
指月はぱっとひらめいた。
「わかりました! 湿気は下に集まります! 人間の体も同じで、湿気は下半身にたまりやすいのですね!」
祖父が脈をとる時、両脈が沈濡であれば、「脚が重たくてまるで泥を引きずるようで、歩くのがしんどいんじゃないのか?」と聞く。
多くの患者が驚くのも無理はない。
自分から話してもいないことを、祖父は脈に触れただけで見抜くからだ。
中医学を学ぶには、物をよく観察し、そこから象を取り出して理を体得する力が求められる。
医理とは、神秘的なことを語るためにあるのではなく、自身で実践してこそ真価を発揮するのだ。
ある日、両脚が腫れ上がった婦人がやって来た。
祖父は彼女に足を椅子の上に乗せるよう指示すると、指月に触れてみるよう促した。
押すと、足にくっきりとした凹みができ、その凹みはしばらく戻ってこなかった。
脈を診ると、やや浮き気味で緊張していた。
(脚がむくんでいて、脈が浮いている。湿を取り、利尿を図るのが基本だが、この脈象ではうまくいかない。脈が沈んでいれば、その流れに乗って利尿させる方法もある。でも、今回は浮脈に加え、悪寒、無汗、頭痛、身体の重だるさといった感冒の症状まである。利尿で湿を出すのが正解とは言えない。さて、どうすべきか?)
悩む指月をみていた祖父は、さっとヒントを出した。
「前に麻黄でやかんのフタを開ける話をしただろう?」
指月は「ああ、思い出しました!」と、額を叩いた。
祖父は香薷に白朮を合わせるように指示した。
これは『外台秘要』に載っている「薷朮丸」だ。
「夏の暑い季節、発汗して解表し、なおかつ利水消腫もしたいなら、香薷が最適だよ。香薷は上にも下にも働き、水を治す働きが非常に速い。『本草正義』にはこう記されている」
上は腠理を開泄し、肺気を宣し、皮毛に達して表の寒を解く。
下は三焦を通じ、膀胱を疏し、小便を通じて中の水を導く。
白朮は脾を補う聖薬であり、土の力で水を制する働きを強める。
この二味を合わせたところ、脚の腫れは数日でみるみる引いていった。
婦人は「冷え症だったけど、この薬を飲むと汗が出て、毎日たくさん尿が出て、脚の腫れも日に日に軽くなりました。三服で完全に治りました」と喜んでいた。
指月は不思議に思った。
祖父は香薷を使うとき、5グラムから8グラム程度のときもあれば、30グラムから50グラムと大量に使うときもある。
その理由を尋ねると、祖父は答えた。
「上焦を治すには羽のように軽くなければ持ち上がらない。だから香薷で発汗させるときは、量は少なく、煎じ時間も短めがいい。“軽舟速行”の意を取るんだ。逆に下焦を治すには、錘のように重くなければ沈まない。水腫や脚気、小便不利を治すには量を多く、しっかり煎じて、重い一撃で患部までしっかり届ける必要があるんだよ」
指月は納得した。
薬の分量を変えることで、薬の量を変えるだけで、効き方も変わる。
中薬の柔軟さに感動し、ノートに記した。
上焦を治するは羽のごとし、軽からざれば挙がらず。
香薷を用いて発表するは軽剤を宜しとす。
下焦を治するは錘のごとし、重からざれば沈まず。
香薷を用いて利尿するは重剤を要す。
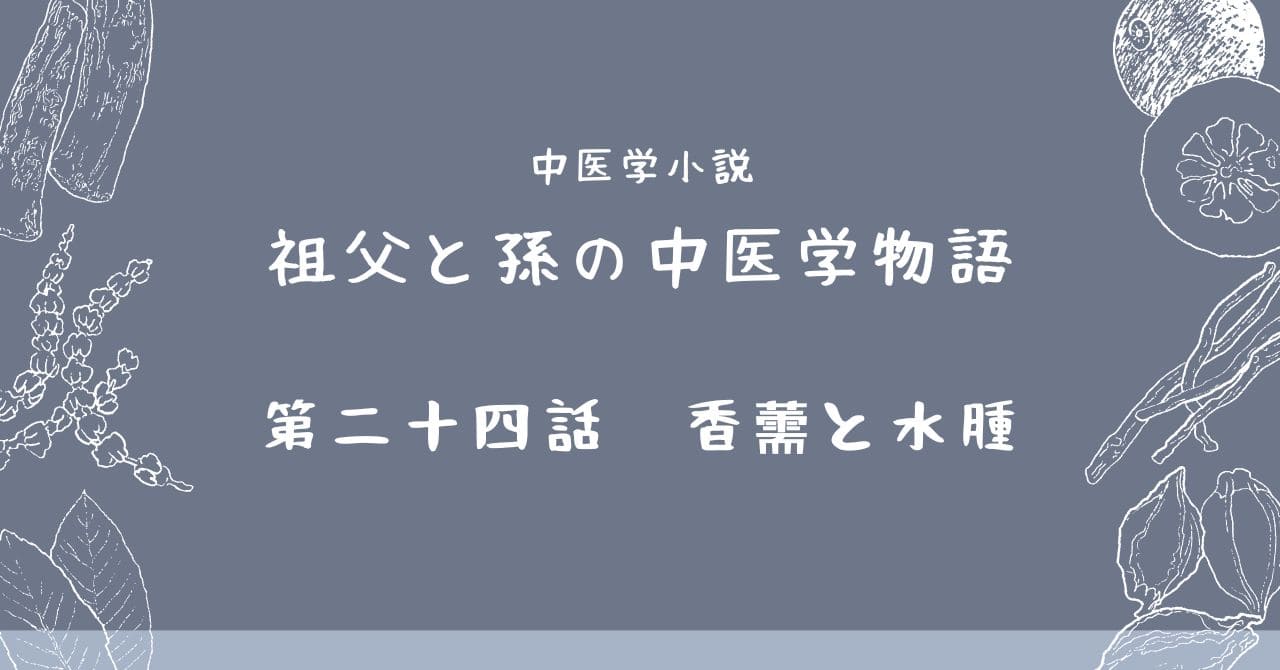


コメント