昔々、順州府南河県に、何病児(かびょうじ)という名の若者がいました。
彼は薬草を採っては丁寧に加工し、町の薬屋へと売って暮らしていました。
多くの人々の命を救ってきたものの、生活は貧しく、やせ細った体には骨が浮き出し、顔は土のように黄色く、まだ二十歳を少し過ぎたばかりだというのに、白髪が混じっていました。
ある春の日、何病児は背負った薬草を市場で売り歩いていました。
そのとき、竹の葉でいれたお茶を売る女の子が彼に声をかけました。
「何さん、この十日あまり見かけませんでしたよ。お元気でしたか?」
「春は薬草の採り時で、山にこもっていたんです」と答えると、ふたりは自然と打ち解け、互いに笑い合う仲になっていきました。
ところがある日、県の太守の息子がその茶売りの娘をからかい始めました。
怒った何病児は、棍棒でその息子を打ち据えました。
事はすぐに知れ渡り、追っ手が差し向けられたため、何病児は山へと逃れ、やがて人里離れた洞窟に身を潜めるようになりました。
ある夜のこと。月明かりが一層澄んでいた晩、山の斜面に日差しのよく当たる場所で、何病児は二本の青い蔓草を見つけました。
葉は緑濃く、左右が向かい合っていて、まるで心臓の形をした葉が抱き合っているようでした。
彼は「夜交藤(やこうとう)」という薬草を思い出し、この草がそれではないかと感じました。
鍬で掘ってみると、根には小人のような丸い塊がいくつも付いていました。
試しにかじってみると、初めは苦く、噛むほどに甘みが滲み出てきました。
その根を食べると、不思議と喉の渇きも飢えも感じず、体が軽くなったように思えました。
以後、彼はこの草を掘っては食べながら山中で暮らすようになりました。
やがて秋が過ぎ、冬になっても、何病児の身体は元気そのものでした。
ある日、山で薬草を探す道士に出会い、この草には肝を養い腎を補う力がある「仙薬」だと教えられました。
何病児は道士に頼み込み、弟子として薬草の知識を学び始めました。
一年が経つと、白く黄ばんでいた髪はつややかな黒に戻り、しわの寄っていた顔も赤みを帯び、若々しさを取り戻しました。
その薬草を粉にして、貧しく弱った人々に配ると、皆が元気を取り戻していきました。
ある日、何病児は道士とともに薬草を採りながら、海辺の漁村へとやって来ました。
そこで網を編んでいたひとりの女性に出会いました。
――それは、かつて市場で出会った茶売りの娘でした。
娘は祖母を頼ってこの村へ来たこと、家を出たあと行くあてがなかったことを話しました。
それを聞いた道士は穏やかに笑い、こう言いました。
「今日、ふたりが再び出会ったのは天の導き。私が媒酌人となりましょう」
その晩、ふたりは漁村の祖母の家で結婚しました。
その後、何病児はふたりで薬草を採り続け、根を粉末にして人々に配りました。
不思議なことに、それを飲んだ人々の白髪は黒くなり、病は癒え、みるみる元気になっていきました。
人々はこの薬草を、何病児によって見つけられ、食べると「烏(からす)」のように髪が黒くなることから、「何首烏(かしゅう)」と呼ぶようになりました。
そして、やがて人々は、何病児のことも親しみを込めて、こう呼ぶようになったのです。
「何首烏先生」と――。
おしまい

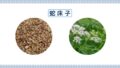

コメント