蕁麻疹――それは、肌の表層を風のように這いまわる奇妙な痒みである。
どこを掻いても、すぐに赤い発疹がぷつぷつと盛り上がる。
ひどくなれば、全身がむず痒くて夜も眠れず、身も心もくたくたになってしまう。
茅葺の家を訪ねてきたのは、そんな症状に苦しむ若者だった。
「もう三年も、この痒みに悩まされてるんです……最初は海鮮を食べたあとでした。そこからずっと……」
彼はそう言いながら、上着を脱いだ。
指月は目を見張った。
胸から腕、背中にかけて――いや、脚の方まで、まるで血の雲が浮かんでいるかのような紅い発疹が一面に広がっていたのだ。
「これは……!」
小指月の言葉が詰まる。
見ているだけで、こちらまで痒みを感じてしまいそうな光景だった。
若者は言った。
「顔にはなるべく触れないようにしてるんです。でも……」と、彼は頬を指した。
そこには、ふた筋の赤いひっかき傷が走っていた。
「もう、これ以上、顔まで腫れたら、人前に出られなくなってしまう……」
その目は、痒みのせいではなく、絶望感で潤んでいた。
若者は眉間に皺を寄せて言った。
「先生、どうしても我慢できないんです。考えたところが痒くなる。痒くなると、もう掻かずにはいられない。掻けば掻くほど、肌は真っ赤に腫れて、血の線が浮き上がってくるんです……」
その訴えに、祖父はゆっくりと頷き、小指月の方を向いた。
「さて、指月。これはいったい、どんな邪気が働いているのか、わかるか?」
問われた指月は、即座に答えた。
「風邪です! “風はよく走り、たびたび変ず”――風の性質は移ろいやすく、どこにでも入り込む。まるで隙間風のように、皮膚の内外を自由自在に動き回るんです!」
祖父はにっこりと笑った。
「では、こういった急性と慢性が入り混じったような風団(蕁麻疹)で、なぜ皮膚がそんなに痒くなるのか、説明できるか?」
そこで指月は、口を開きかけて、言葉に詰まった。
祖父がその続きを受け取るように語り出す。
「“痒み”というのは、風を追い出すための反応なんだ。かゆいところを掻くと、気血が通い始めて、楽になるだろう? ということはつまり、それだけ体内の気血の流れが滞っている証拠なんだよ」
そう言ってから、祖父は改めて問いかけた。
「さあ、指月。どうすれば、この局所に溜まった風邪を疏泄し、肌表の血気を通じさせ、痒みを鎮めることができるだろう?」
指月はじっと若者の傷痕を見つめ、考え込んでいた。
指月は何度も頭をひねった。
――やっぱりこれは、煎じ薬を飲んでもらって、様子を見ないと……
だがそのとき、祖父がぽつりと言った。
「指月、あの壺の上に置いてある、数日前に挽いておいた“荆芥穗”の粉末を持ってきなさい」
言われるまま指月が粉末の壺を差し出すと、祖父は匙でひとすくいし、その粉を若者の腕のかゆみがひどい箇所にまぶした。
そして、手のひらで、それを洗濯物をこするように、ぎゅっぎゅっと擦り込んでいく。
最初はただ熱くなるばかりだったが、やがて若者の表情が少し和らいだ。
「……あれ……なんだか……気持ちいい……」
さっきまであんなに苦しんでいた彼の目に、初めて安堵の色が浮かんだ。
祖父はにっこりと頷き、今度は若者自身に粉を渡した。
「さあ、今度は自分の手でやってごらん。さっきと同じように、反対側の腕にも擦り込むんだ。熱くなるまで、根気よくね」
言われた通り、若者はもう一方の腕にも荆芥穗の粉を擦り込んでいった。
すると、どちらの腕もぽかぽかと温まり、次第に皮膚表面がさらりと乾き、清々しさすら感じるようになった。
「背中は自分じゃ届かないから、手伝ってやりなさい」
指月は頷き、背中や腰、足の裏側など、若者が手の届かない部位にも丁寧に粉を擦り込んでいった。
こうして全身のかゆみの強い箇所をすべてしっかりと擦り終えたとき――
あれほど猿のように体を掻きむしっていた若者が、まるで別人のように静まり返った。
「……あれ……不思議だ……もう、まったく痒くない……」
その姿を見て、指月は驚きのあまり言葉を失った。
確かについさっきまで、彼は痒みで身をよじらせ、耳の後ろまで爪を立てて掻いていたというのに――今は静かに椅子に座り、手も動かさず、穏やかな顔をしている。
「痒いときは、ただ座っていることすらできない。でも痒みが去ると、気持ちは落ち着き、心も澄んでくるものなんだよ」
祖父は、まるで自分に言い聞かせるように、そっと呟いたのだった。
「どうだい? 少しは楽になったかな?」
若者は目を輝かせ、満面の笑みを浮かべて答えた。
「先生、これはまるで神さまの薬ですよ! あれほど痒くて寝ることすらできなかったのに、今は嘘みたいに痒みがない……本当に不思議です!」
その様子に指月も大笑いした。
「まさかそんな手があるとは思いませんでした。今日はまたひとつ、素晴らしい技を覚えました!」
「今回使ったのは、荊芥の花穂だけを乾かして作る「荊芥穗」の粉だよ。風邪を祓い、邪を散らし、急性・慢性を問わず風疹や蕁麻疹によるかゆみに効果があるんだ」
指月はこれまで、荊芥穗は煎じて飲むものとばかり思っていたが――まさか粉末にして肌に直接擦りこむだけで、こんな即効性があるとは夢にも思わなかった。
「ただし、これは“標”を治しただけで、“本”はまだ手つかずだよ」
と、祖父は穏やかに言った。
若者が少し不安げに尋ねた。
「えっ、じゃあ……また家に帰ったら、ぶり返しますか?」
祖父はにこやかに首を振った。
「今後は海鮮や脂っこいものを控え、味の濃い食事はなるべく避けなさい。お菓子や加工食品もほどほどに。病というのは、たいてい口から入ってくるものだよ」
若者は素直に肯いた。
そこで祖父は、仕上げにと、指月に薬方を指示した。
「生地黄一両(約30グラム)、荊芥五銭(約15グラム)――これを水で煎じて飲ませなさい。これは急慢性の蕁麻疹や、かゆみと赤みを伴う肌の炎症に用いる特効方だ。数日飲めば、病根もきれいに抜けていく」
こうして若者は、笑顔とともに茅葺の家をあとにした。
肌に残るかゆみは、もうなかったが、それ以上に、心に残る何かを持ち帰ったようだった。
指月は、今日もまた大いに学びを得た。
ひとつは、荊芥穂の粉末を肌にすり込む「外搓法(がいさほう)」――すなわち、かゆみのある患部に薬を直接塗ってこすり、風邪を肌から追い払う方法。
もうひとつは、荊芥と生地黄を合わせて煎じ、体内の血と気を調える「内服法」。
このふたつを組み合わせれば、内と外の両面から治療できる。
いわば、「標」と「本」を同時に癒す術だ。
病はたちまち癒えていく。
「ところで祖父?」と、指月は尋ねた。
「なんで、生地黄を一両も使うのでしょうか?」
祖父はにっこりと笑い、問いかけた。
「風を治すには、まず何を治すのだったか――覚えておるか?」
それを聞いた指月は、得意げに口を開いた。
「“風を治すにはまず血を治す、血が巡れば風もまた滅ぶ”――ですね!」
「そう、それでよい」と祖父はうなずいた。
「生地黄は陰を養い、血を冷ますのに最も優れた薬だ。荊芥穂は気血の巡らせ、風邪を追い払う力がある。つまり――生地黄が足りない陰血を滋養し、荊芥穂が余分な風邪をさばいてくれる。過不足がそれぞれ調えられれば、病は早く癒えていくというわけだ」
指月はうれしそうに、この「内外同治」、「標本同治」の妙法を、自分のノートに書き留めた。
蕁麻疹のような病に出会ったとき、頼れる“金剛石のような切り札”がひとつ増えたことが嬉しかった。
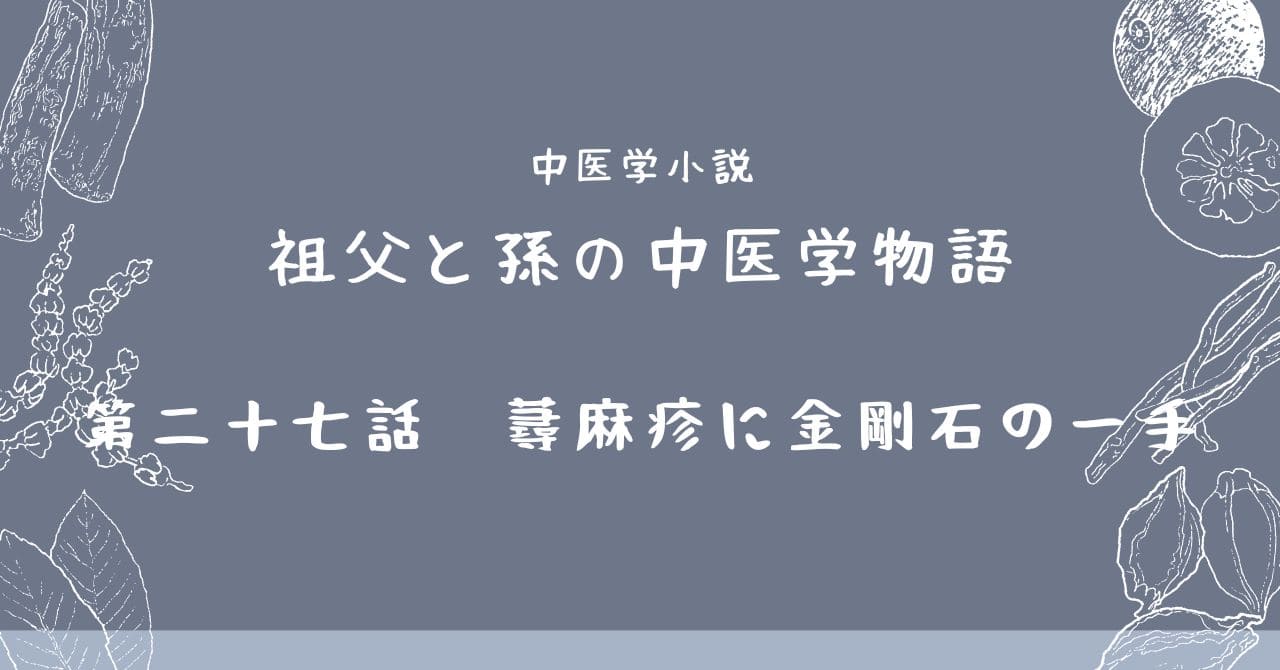


コメント