近ごろは冷蔵庫や防腐剤の普及により、一年を通してさまざまな生野菜や果物を口にできるようになった。
人々はそれを「暮らしの豊かさ」だと喜んでいるが、中医の眼から見れば、それは健康を蝕む大きな落とし穴でもある。
なぜそう言えるのか?
ある秋冬のこと、富豪の息子が数日間、冷やしたスイカを食べ続けた末に、腹を下し始めた。
頭痛まで起こり、どんな治療をしても良くならず、半月以上も下痢が続いていた。
子どもの顔色はどんよりと青白く、生気は失われ、まるで水気を失った若苗のようにしおれてしまっていた。
そう、下痢で失われるのはただの水分ではない。
それは「津液」――身体を潤し、命を養う大切な水である。
津液を大量に失えば、たちまち人は枯れてしまうのだ。
富豪は名のある医師たちを何人も呼び、止痛薬や止瀉薬を次々と与えたが、どうしても止まらなかった。
病が重いのか、薬が効かぬのか、それすらも分からないまま手詰まりとなり、ついに茅葺の家を訪れることになった。
指月がひと目見ると、その子の顔は青白く、舌苔は白くねっとりとしていた。
とても富豪の子とは思えず、まるで食うに困る家の子のようにやせ細り、骨ばっていた。
(なるほど。物が豊富にあるからといって、それが身体を養えるとは限らない)
――それがすぐに分かった。
祖父は「何を食べて、こうなったのかな?」と尋ねた。
「何日続けて、冷たいスイカを食べました」
祖父は、やれやれ、と首を振った。
「最近の人は健康の理を知らない。季節外れの果物をありがたがって食べるが、それは身を損ねるもとになるんだ。スイカは夏のもので、秋冬に食せば体に冷えを呼び込む。しかも、今の冷蔵スイカは数ヶ月も保存され、防腐剤まみれ。君たちはスイカを食べているのではない、氷と薬品を食べているんだ。中医の言葉に『時ならぬ気は、すなわち邪なり』とある。季節にそぐわぬ気を取り入れることは、病を呼ぶことになるんだよ」
『黄帝陰符経』には、「時にかなったものを食せば、百骸(ひゃくがい)理(おさ)まる」とある。
つまり、季節に合ったものを口にしてこそ、身体は調和を保てるということだ。
高価なものが必ずしも身体に良いとは限らない。
真に健康を養う食とは、値段とは関係がないのだ。
「たとえば、いまの季節には白菜、大根、サツマイモが出回っているだろう? それらこそ身体にやさしく、元気を取り戻す食物なのに、なぜそれを選ばず、わざわざ高価で体を冷やす西瓜などを選ぶのか――それで病になっては、本末転倒だよ」
富豪は深くうなずいた。
ようやく気がついた。
自分の家には「健康的な食の考え方」がまったく根づいていなかったことに。
世間の評判や市場の流行にばかり目を向け、値段の高いものが良いものだと子どもに食べさせていた。
(どうりで、栄養には事欠かないはずの子どもが、かえって虚弱に育っていたわけだ――)
富豪の子供の姿は、慎ましくも健康な貧しい家庭の子どもに遠く及ばなかった。
祖父は、こうした健康の根本をしっかりと伝えてから、ようやく「用薬」について語り始めた。
これが祖父の流儀である。
病に対する薬の処方を論じる前に、まず「養生」を語るのだ。
「養生は、病を治す源であり、薬を使うことは、病を追い出す手段にすぎない」
いくらうまく薬で症状を取り去ったとしても、病の源を絶たなければ、いずれまた病は戻ってくる――
それが祖父の信念だった。
祖父は、指月に尋ねた。
「さて、陽気を生じさせ、泄瀉を止めることができ、かつ巓頂(てんちょう=頭のてっぺん)の痛みを取れる薬といえば、何があるかな?」
指月はにこりと笑って答えた。
「それなら藁本ですね。藁本は巅頂に昇り、胃腸に下達する。陽気を引き上げて下痢を止め、風邪を祛い、表を解く。頭頂の痛みは、これがなければ治りません」
祖父はうなずいた。
「では藁本湯でいこう」
その後、一服で効果を示し、二服で癒えた。
子供の病気が治ったことを知った指月は、すぐにノートに書き記した。
『本草彙言』いわく――
藁本は上に巓頂へと通じ、下は胃腸に達する。
『神農本草経』いわく――
藁本は腹中の痛みを主り、頭風の痛みを除く。
『邵氏見聞録』いわく――
夏英公、泄瀉を患い、太医が虚証と見て治せず。
霍翁いわく、「風、胃に客す」として藁本湯を与え、たちどころに癒ゆ。
これは藁本が風湿を祛うがゆえである。
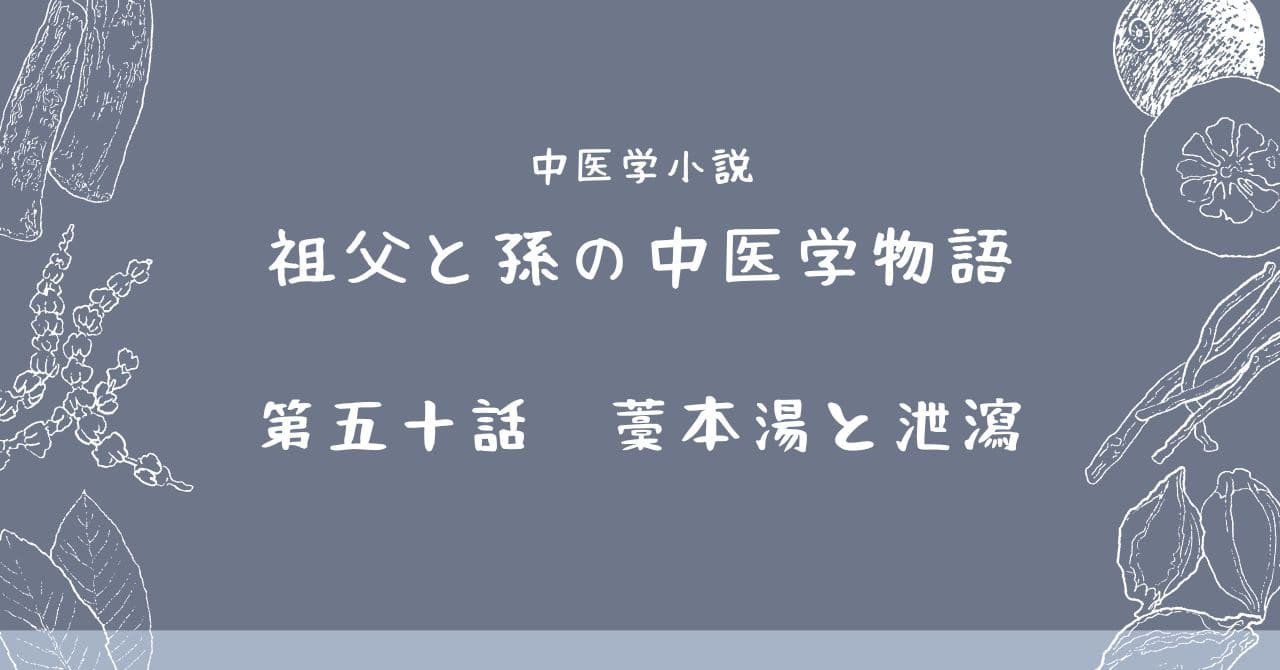
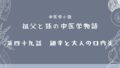

コメント