ある日、小さな子どもが全身に疥癬(かいせん)を患い、ひどいかゆみに苦しんでいた。夜もまともに眠れず、泣きじゃくってばかりいる。
家族はありとあらゆる皮膚の薬を塗り、時には黄連や黄柏といった清熱解毒の薬で体を洗ったりもした。でも、一時的に良くなったかと思えば、またすぐにぶり返してしまった。
さらには、市販の抗菌剤や殺虫・消炎の薬まで買ってきて試したが、それでもこのしつこい虫やかゆみはまったく治らなかった。かきむしった皮膚は傷だらけ、血と膿がにじみ、人目にも痛ましい有様だった。
ちょうどその頃、祖父は指月を連れて薬草採りに出かけていた。
家族はふたりを見つけるや否や、すがるような思いで家に招き入れ、診てもらうことにした。
家に入ると、指月は何か妙な違和感を覚えた。何とも言えない重苦しい空気が漂っている。子どもの寝床に近づいてみると、顔色はくすみ、皮膚のただれはひどく、膿までにじんでいた。
家族はこれまでの治療経過を詳しく語った。
祖父はしばらく黙って考え、やがて指月にたずねた。
「この皮膚病、なぜこんなに手こずると思う?」
指月は少し考えてから答えた。
「清熱解毒の薬も使ったし、外洗薬も使ったし、殺虫剤や消炎薬も相当試したみたいです。それなのに…こんなにしぶとい虫や湿疹って、本当に薬が効かないんでしょうか?」
祖父は微笑んで言った。
「だから言ったろう、病の三分は薬で治すが、七分は養生次第だと。この子はその“養生”ができていないんだよ」
家族は驚いた顔で言った。
「養生が足りないって…そんなことを言うお医者さんは、これまで誰もいませんでした」
祖父はゆっくりと話し始めた。
「どれだけ強い殺虫薬を使ったところで、すでに発生した虫は駆除できても、これから出てくる虫までは止められない」
家族はなおも首をかしげていた。
そこで祖父は、庭の水場のそばに置かれていた朽ちた木片を指差して言った。
「ほら、あの木を見てごらん。なぜ、あれにはいつもカビや虫がついているのだと思う?」
家族は答えた。
「そりゃ、水のそばに置いてるからでしょう。湿っていると虫も生えるし、カビも生えます。」
その通り、と祖父は笑って肯いた。
「では、その木に虫やカビが生えないようにするには、どうすればいい?」
「それなら簡単です。高いところに置いて、日光に当てて、風に当てて乾燥させれば、湿気もなくなって、虫もカビも出ませんよ」
このとき、家族はまだ祖父が何を言いたいのか分かっていなかった。
指月は突然手を叩いて叫んだ。
「分かった、分かりました!」
祖父が尋ねた。
「何が分かったんだい?」
「病気がどうして起きたのか分かりました。そして、どうすれば治せるかも分かりました!」
祖父はわざと試すように言った。
「指月、あの家の人は名医を何人も呼んで、あらゆる薬も使ってきた。それでも治せなかったんだよ。そんな難しい病を、お前のような子どもが“治せる”なんて、よくもそんな大言壮語を……」
指月はにこにこ笑いながら答えた。
「これは大言壮語ではなく、自信です。医理を理解すれば、自ずと心の中に治せる確信が湧いてくるものです」
祖父はそれを聞くと「では、お前の考えをその家の人に話してごらん」と促した。
指月は言った。
「この家はあまりに暗くて湿っています。窓はいつも閉め切られ、家のすぐそばには大きな木が何本も茂っていて、日光が家に差し込めません。そのせいで、洗濯物も乾ききらず、僕が家に入ったときにはすぐにカビ臭さが鼻につきました。皆さんは長くこの家に住んでいるから気づかないのかもしれませんが、かなりの湿気です」
家の人たちはうなずいて言った。
「まさにその通りです。洗濯物が乾かず、家の中も常に湿っぽいです。でも、その湿気と痒みの病気がどう関係あるんですか?」
指月ははっきりと答えた。
「湿は虫を生みます。湿気がなければ虫は生まれません。木が湿って腐ればカビが生え、人の住む環境が湿っていれば、ウイルスや細菌が繁殖しやすくなります」
家の人は目を見開いて言った。
「なるほど! その通りだ!」
指月は続けた。
「こうしましょう——
一つ目、家のすぐ近くの木を切って、太陽の光がきちんと家に入るようにしましょう。
二つ目、子どものベッドを少し高くしましょう。高ければ風通しがよく、湿気もたまりにくくなります。低いと湿気がたまりやすいです。
三つ目、服はきちんと洗って、しっかり日干ししたものだけを着せてください。
四つ目、布団も数日に一度は外に出して天日に干しましょう。
五つ目、ドアや窓をこまめに開けて、空気を循環させてください。そうすれば自然と湿気はなくなります。
六つ目、藁本を煎じた薬湯で子どもを入浴させましょう。
七つ目、子どもが着る服やシーツも、同じ藁本の湯で洗ってください」
病を治すときは、ただ単に病邪を取り除く手段を考えるだけではなく、病の根本的な原因を絶つという視点が大切だ。
藁本という風薬を用いて湿邪を祛するのも、まさにその理にかなっている。
なぜなら、風は湿に勝る――湿が除かれれば、虫が生きるための環境自体がなくなるからだ。
その後、半月も経たないうちに、あの家の人がまた茅葺の家にやって来た。
手にカゴいっぱいの卵を持って、「このたびは本当にありがとうございました」と礼を述べた。
あの子どもは、すっかり元気になり、軟膏も、炎症を鎮める薬も、痒み止めも、虫を殺す薬も使っていないという。
たった一味の藁本だけを用い、それを煎じて入浴に使い、またその湯で衣類を洗い、そして指月の言った生活習慣の改善をきちんと守っただけで、日に日に症状は軽くなり、皮膚の疥癬はすっかり消えて、元のきれいな肌に戻ったのだ。
指月はそれを聞いて心の中で大いに喜んだが、それは当然のことだと思っていた。
なぜなら、理が通れば、治療の効果は自ずと現れるし、筋道が正しければ、薬もまた見事に効くものであるからだ。
そして指月はノートにこう書き記した。
《小児衛生総微論方》:疥癬を治すには、藁本を煎じて湯とし、これで入浴させ、また衣服を洗うこと。
虫を治すのではなく、湿を治す。
湿が除かれれば、虫は生まれようがない。
病を見て、病の根を知ること。
ただ目の前の痒みや疥癬だけを見ていては駄目で、人の体質に潜む湿、
さらには家そのもの、住環境に潜む湿気までを見なければならない。
環境を変えることで、病原菌が再び生き延びる余地をなくす。
これこそが中医学の本当の全体観であり、
――病原菌を治すのではなく、「環境」を治すのである。
なぜ藁本を使うのか?
藁本は風薬であり、ただ風こそが湿を祛うことができるからである。
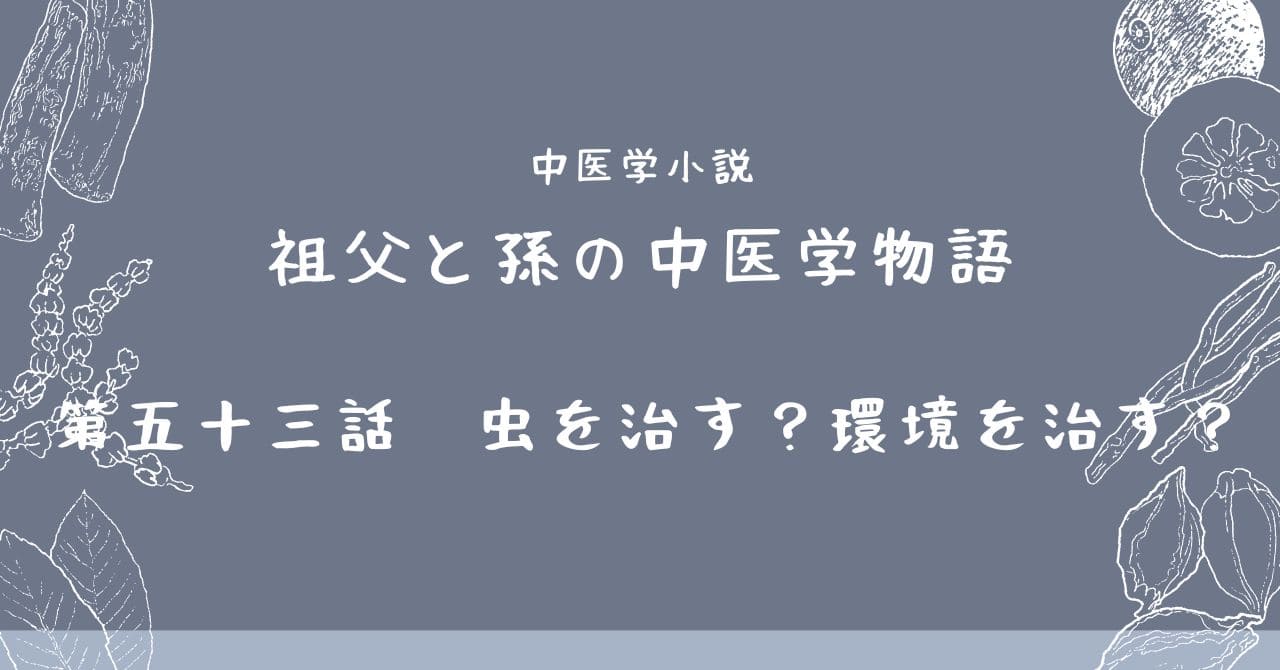


コメント