(桂枝は邪悪な鬼を退治できる)
この数日、小指月はこの問題について考えていました。
「邪悪な鬼なんて本当にいるのか? 桂枝でどうやって退治するのか? しかし、確かにあの病人は桂枝を服用した後、もう邪悪な鬼の夢を見なくなったのだ。もしかして、祖父は護符を描いて鬼を祓うことができるのか? でも、そんなこと一度も教えてくれなかったぞ……」
その患者は、半年以上の間、夜ごとに亡くなった親族や、鬼のようなものが夢に現れるという状態に悩まされていました。
夢の中では、まるで氷の洞窟に迷い込んだように、寒さに震え、恐怖に支配されるのです。
何度も夢の中で驚き、恐怖で目を覚ましました。
目覚めた後も、心臓はドキドキと高鳴り、冷や汗が滝のように流れ、手を胸に当てて息を整えようと必死でした。
この症状を聞いた祖父は、たった二味の薬——桂枝と甘草を処方しました。
患者は五服(五日分)の薬を飲み終えたころには、半年以上苦しんでいた悪夢はピタリと無くなり、動悸もなくなったので、ぐっすり眠れるようになったのです。
指月はますます不思議に思いました。
(なぜ桂枝と甘草だけで、悪夢が止まったのか? 桂枝は本当に鬼を祓う力があるのか?それとも、鬼ではなく……別の何かだったのか?)
指月は、桂枝甘草湯が「心下悸欲得按」(心臓の動悸が激しく、手で押さえたくなる症状)を治せることは、すでに理解していました。
しかし――
「なぜ、たったこの二味の薬で、夢の中の鬼を追い払うことができたのか?」
それが、どうしてもわからないのです。
(しかも、悪夢だけじゃない。あの患者は薬を飲む前、手足が冷たく、顔にはまったく笑顔がなかったのに、薬を飲み終えると手足が温まり、晴れやかな笑顔を浮かべてやって来た。この変化は一体何なのか? どうして、これほどまでに変わるのか?)
指月は、いてもたってもいられず、祖父の周りを何度も何度も回りながら問い詰めました。
しかし、祖父はただ笑うばかりで、決して答えようとはしません。
ついに、指月は真正面から祖父に詰め寄りました。
「祖父! なぜ桂枝甘草湯で『邪鬼』がいなくなるのですか!?」
祖父は、静かに目を閉じ、深く息を吸った後、ゆっくりと口を開きました。
「それは⋯⋯言えん、言えん」
「えぇっ!? どうして!?」
「言えない」と言われると、ますます知りたくなるのが人間の性です。
指月は、ますます好奇心を掻き立てられました。
「なんで言えないのですか!? 意地悪しないで教えてください!」
祖父はただ微笑んで、またもや沈黙しました。
(くそっ⋯⋯このままじゃ絶対に諦められない!)
指月は、ついに奥の手を使いました。
祖父の着物の裾をギュッと掴み、まるで幼子のように言いました。
「祖父が教えてくれないなら、私も祖父を放しませんからね! 絶対に離しませんよ! お願いです、教えてください !教えてくれなきゃ、ずーっとこうしてますからね!」
祖父は、わざと怒ったふりをしながら、手に持っていた煙管で小指月の頭を「コツン、コツン、コツン」と三回叩きました。
「今夜、家に帰って、しっかり寝るんだ!」
指月は、一瞬ぽかんとしました。
(えっ⋯⋯今夜? 祖父はどうしちゃったんだ? なんで急にこんなことを言うの?)
指月は祖父をじっと見つめました。
祖父は、普段めったに指月の頭を叩くことはありませんでした。
それなのに、今日はわざわざ三回も叩いたのです。
(もしかして⋯⋯祖父、ボケてきたのかな?)
いや、それはない!
(だって、まだ昼間だよ!? 今夜寝ろって、そんなの当たり前じゃないか! そんなこと言われなくても、夜になったら寝るよ!)
指月は、頭を抱えて考え込みました。
(いったい、どういう意味なんだ?)
祖父は、ただニヤリと笑っただけで、それ以上何も言いませんでした。
指月は、何か言おうと口を開きかけましたが、祖父はすでに飄然と寝室へ戻ってしまっていました。
指月は額をそっと撫でながら、ふと何かを悟ったような気がしました。
目をくるりと動かし、にやりと笑うと、そのまま自分の仕事に戻りました。
その夜――
屋内は漆黒の闇に包まれ、屋外には丸い満月が浮かんでいました。
しかし、次第に厚い雲が月を覆い隠し、あたりはますます暗くなっていきました。
そこへ、一陣の風が吹き抜けると、雲がゆっくりと移動し、再び澄み渡った月の光が、茅葺の家のまわりを白銀の輝きで照らしました。
まるで――
鳥は池邊の樹に宿り、僧は月夜に友を訪ねて門を敲いている
という詩の情景のように、静謐で幻想的な世界が広がっていました。
四方から蟋蟀(こおろぎ)の声が響いた、ちょうど三更(真夜中の0時)――
指月は、普段なら決して起きることのないこの時間に、目を覚ましました。
寝床からそっと起き上がり、左右を見回しました。
「おかしい。どこにも、祖父の姿はないな。やっぱり私の考え違いだったのか⋯⋯)
疑問を抱えながら、彼は静かに祖父の寝室の前へ忍び寄りました。
部屋の中には何の気配もありませんでした。
指月は祖父がもう寝てしまっているのかと思いました。
(そんなはずないよな。だって、祖父は『今夜、しっかり寝ろ』って言ったんだから。祖父なら、私がそんな事を言われたらむしろ寝ないことくらいわかっていたはず。そして、ここへ来ることもわかっていたはずなのに、何の準備もしていないのか?)
ますます不思議に思った小指月は、ついに好奇心を抑えきれず、
「コン、コン、コン」
と、扉を三回叩きました。
すると、すぐに、扉の向こうで灯りがともった。
「!!!」
指月の胸は、一気に高鳴りました。
(やっぱり、おじいちゃんは寝てなんかいなかった! 絶対に何か大事なことを伝えようとしているに違いない!)
指月の頭の中には、様々な想像が駆け巡りました。
(もしかして、これは本当に「降魔除鬼」の秘伝なのでは!? 「法不伝六耳(法は六耳には伝わらず。つまり、師匠と弟子の一対一でしか伝わらないということ)」というように、古来より、大法・大道は決して簡単には伝えられないものだ! きっと祖父が今から教えてくれるのは、秘中の秘――神秘の技に違いない!!)
興奮と期待に胸を膨らませていると――
「ギィィィ……」
扉がゆっくりと開きました。
すると、最初に目に入ったのは、祖父の顔ではなく、手に掲げられた灯油ランプでした。
ゆらゆらと揺れる小さな炎が、暗闇の中で静かに燃えていました。
(これは何かの儀式の始まりなのか!?)
興奮を抑えきれず、彼は思わず祖父を呼ぼうとしました。
「祖――」
しかし、その瞬間――
ふっ――
祖父は、静かに口をすぼめると、一息で灯の火を吹き消しました。
真っ暗になりました。
なにが起こっているのか全くわかりませんでした。
「え? え? え?」
指月は、完全に混乱していました。
つい先ほどまで明るく照らされていた祖父の寝室が、一瞬にして真っ暗な闇へと変わったのです。
「バタン」
祖父は、何の躊躇もなく扉を閉めました。
指月は、そこにただ立ち尽くしていました。
なぜ、祖父がこんなことをしたのかという疑問が頭の中を駆け巡っていました。
ほんの一瞬、明と暗が交錯する、その刹那の変化の中で、指月の脳内に広がっていた霧が、一気に晴れたのです。
「!!!」
小指月は、ふっと微笑みました。
まるで、ずっと探し続けていた目的地にようやくたどり着いた旅人のように、満足げな表情を浮かべながら、静かに自分の寝室へと戻っていきましま。
歩きながら、指月は小声でつぶやいていました。
「そういうことか。 なるほどね」
心は、火を主る(心主火)。
心火が明るければ、暗闇は消え去る。
心が晴れやかであれば、世界は光に満ち、ポジティブになる。
心火が弱まれば、四方は陰に覆われ、闇が支配する。
何もないのに不安になり、考え過ぎ、悪夢に悩まされる。
心火が旺盛であれば、全身が温かく、四肢も暖まり、冷えを感じることはない。
心火が衰えれば、体は冷たくなり、全身が寒気に包まれ、凍え、病に伏せることになる。
「邪悪な鬼の夢」は、心陽の不足から生まれたもだったのです。
桂枝甘草湯の「辛甘化陽(辛味と甘味で陽を生じる)」作用が、心陽を活性化させ、心の機能を高めたのです。
心陽の光が周囲を照らせば、その光が届く範囲に「冷え」や「病」は存在しえないのです。
一息の陽気が、一息の命となり、一息の寒気が、一息の病を生む
(一息阳气一息命,一息寒气一息病)
指月は、単に「心陽虚」による悪夢・心悸・手足の冷え・心痛といった症状の治療法を理解しただけではありませんでした。
指月はさらに深く悟ったのです。
陰が形成するすべての疾患は、「陽を生じさせて気を巡らせることで治療できる」のだと。
祖父が指月に授けたのは、「邪悪な鬼を祓う符」でも「悪夢を退ける秘薬」でもなかった。
祖父が授けたのは――
数千年にわたり、医学の道として受け継がれてきた「陰陽の真理」。
「唯陽光可以消陰翳!」(ただ陽の光のみが、陰の翳(かげり)を消し去ることができるのだ!)
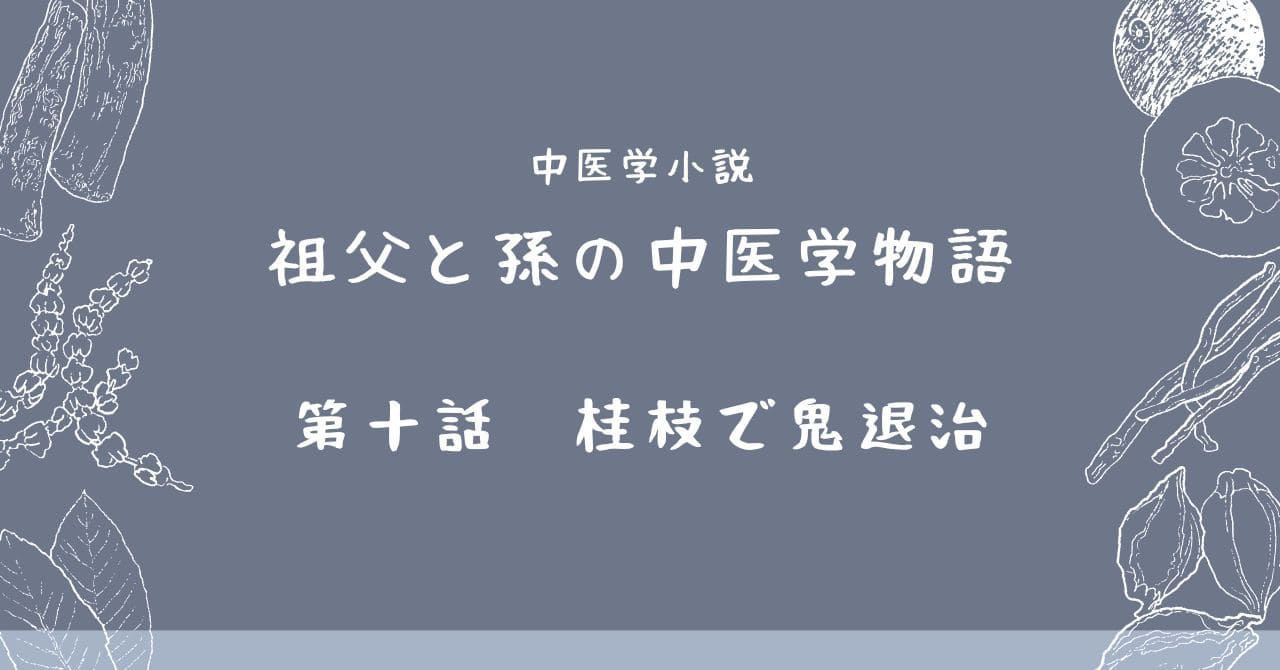

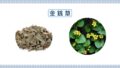
コメント