紫蘇と麻黄はいずれも表寒を散じ、風寒感冒を治療する作用を持っています。
(じゃあ、この二つの薬には、どのような違いがあるのだろうか? いつ紫蘇を使い、いつ麻黄を使うべきなのか?)
指月は少し混乱していました。
薬の効能が似ている場合、指月はどちらを選ぶべきか、いつも迷ってしまうのでした。
でも、そんなときは、祖父が説明してくれるのです。
「麻黄と紫蘇はどちらも辛温で発散させる効能を持つが、麻黄の発汗解表は強力で、紫蘇の発汗解表は穏やかなんだ。つまり、軽症なら紫蘇を、重症なら麻黄を使うべきだよ」
指月はさらに尋ねました。
「もし間違えて使ったらどうなりますか?」
祖父は厳しい表情で答えました。
「すぐに問題が起こる。軽症に麻黄を使った場合、もし体が虚弱な人だったら、汗が止まらなくなる。逆に重症に紫蘇を使えば、風寒が表に閉じ込められたままになる。重症に対して紫蘇は力不足で、病を治すことができない。まるで靴の上から痒いところを掻いているようなものだ」
指月はこの説明をすぐに理解しました。
ちょうどそのとき、一人の母親が娘を連れてやってきました。
「この子は風邪を引いてから、もう一か月以上も咳が続いていて、鼻水も止まりません。いろいろな風邪薬を試しましたが、一時的によくなってもまたぶり返してしまいます。何をしても治らないのです」
指月は尋ねました。
「寒がりますか? 汗は出ますか?」
娘は厚手の服を着て、帽子をかぶっていました。
それを見た祖父は、もうすでに診断を終えていました。
「風に当たるのも怖がって、汗もほとんどかきません。頭痛もして、食欲もなく、元気がありません。学校にも行けずに困っています」
祖父は脈を診た後、指月に尋ねました。
「この症状、どう思う?」
指月は考えて答えました。
「脈は浮いているけれど、少し弱い……。つまり、風寒の外邪がありながらも、中気が不足している……。これはどうすればいいのでしょう? 補気すれば、邪気を体内に留めてしまうし、発汗させるにはこの子の体力では耐えられません……」
祖父は笑って答えました。
「もし発汗させて治るなら、これまで飲んできた風邪薬で治っていたはずだ。子供の生理的特徴は何だったかな?」
指月はすぐに思い出しました。
「脾は常に不足し、内傷や実滞を起こしやすく、外感風寒にもかかりやすい」
祖父はさらに問いかけました。
「では、体が虚弱で脈が弱く、外に邪気があり脈が浮いている場合、どうすればいい?」
指月は笑って答えました。
「補気解表ですね」
「では、どんな処方を使う?」
小指月は迷わず答えました。
「参蘇飲です」
祖父は微笑み肯きました。
指月はすぐに参蘇飲の処方を紙に書きました。
参蘇飲は、人参と紫蘇葉を主とする補気解表の処方で、気虚による反復性の外感を治療するものでした。
数日後、娘は元気に学校へ行けるようになりました。
帽子も脱ぎ、寒さを怖がることもなくなり、食欲も戻りました。
彼女を一ヶ月以上も苦しめた風邪が、参蘇飲で完治したのでした。
「他の医者が麻黄湯を使った結果、彼女の風邪がますますひどくなったのは、なぜか分かるか?」
「以前、祖父が言っていました。戦場で、守りの兵力が不足しているときに城門を開けば、敵を招き入れるだけだ、と。つまり、体が虚弱で力がないときに、大量の発汗を行ったせいで、邪気は去るどころか、さらに彼女の体を弱らせてしまったのですね」
祖父は「そうだ」と肯きました。
「毛竅が開けば正気を消耗する。正気が足りない人は、毛穴が開いた途端、邪風が入り込んでしまうんだ。だから、麻黄湯を誤って使えば、風邪が悪化することもあるんだよ」
指月は納得するも、まだ一つ疑問がありました。
「なぜ参蘇飲では、人参をほんの少ししか入れないのですか?」
祖父はそう質問されることをすでに知っていたかのように、喩昌の『寓意草』を取り出し、ある一節を読みました。
「傷寒病で人参を用いる場合、その区別を明確にしなければならない。人は外邪に侵されると、まず発汗して邪を追い払おうとする。
しかし、発汗が成功するのは、元気が旺盛な場合のみである。もし元気が弱ければ、薬が外に作用しても、気がさらに衰えてしまう。軽い場合は邪が体外へ出きらずに留まり、重い場合は元気が萎縮し、熱が引かずに苦しむことになる。だから虚弱な体質の人には、人参を少量用いる。これにより、元気をわずかに補い、邪気を一気に押し出すことができる。しかし、これは滋養のためではなく、邪気を排除するためである」
この一節を聞いた指月は、祖父の説明を待つまでもなくすぐに理解しました。
「虚弱体質の感冒には、人参を少量使い、気を整える紫蘇葉を組み合わせることで、肌表を軽く開き、邪気を追い出すことができます。そして、気を補うことで、体が自然に回復します。こうすれば、長引く感冒を断ち切ることができるんですね」
指月は驚きを隠せませんでした。
(これほど矛盾するように見える病態が、一つの方法で解決できるとは! )
これまで指月は、「体が虚弱なら補気すべき」と単純に考えていました。
しかし、ただ補気するだけでは邪気が体内にとどまり、病が長引いてしまいます。
また、「邪気があるなら発汗して追い出すべき」と考えていましたが、大量の発汗を行うと体がさらに虚弱になり、邪気が去るどころか戻ってきてしまうこともあります。
そんな中、祖父はわずかな量の補気法と、穏やかに発散する紫蘇葉を組み合わせることで、補気と祛邪のバランスを見事に取ったのです。
その結果、指月が驚くほどの速さで、小さな少女の一ヶ月以上に及ぶ感冒を治すことができたのです。
「感冒に対する薬の使い方を誤れば、病は長引く。しかし、正しく使えば、たった一剤で治るんだ」
指月はまた一つ、中薬の道理を学びました。
ところが、その後すぐに新たな疑問が湧いてきました。
(では、気滞と外寒が同時にある場合はどうすればよいのだろうか? 単純な風寒感冒なら発汗で解決できる。単純な内傷食滞なら、気を巡らせて消化を助ければいい。でも、同時に起こったら? もし風寒感冒に加えて、胸がつかえ、食欲がない場合はどうすればいいんだ? このような症状は特に子供に多い)
そんなことを考えていた時、一人の母親が五歳の子供を連れて、茅葺きの家の戸を叩きました。
「この子はもう一週間も食欲がなく、寒がってくしゃみをしています。風邪だと思って治療しましたが、何度も繰り返してしまうのです」
祖父は指月に尋ねました。
「今回の場合、なぜ発汗解表の方法では風寒感冒が治らないのか、分かるか?」
指月は微笑んで答えました。
「食べたものは脾胃が運化しなければなりません。それと同じように、薬も脾胃が運化しなければなりません。もし脾胃の働きが悪ければ、たとえ風寒を追い出しても、肌表の気血が不十分な状態なので、すぐにまた風邪を引いてしまうのです」
祖父は満足そうに肯きながら言った。
「『難経』にはこう書かれている。『脾を損なえば、飲食で肌膚を養えない』と。つまり、脾胃に食滞があると、摂取した栄養がうまく消化されない。脾胃は全身の気血生化の源だ。水穀をうまく運化できなければ、五臓六腑や四肢百骸に十分な気血を供給できない。結果として、肌表の毛竅の開閉が正常に機能しなくなる」
小指月は深くう肯きました。
「だから、通常の発汗解表の薬では治らないのですね」
「そうだ。これでは麻黄の出番はない。では、どんな薬を使うべきだろう?」
「外寒を散じ、気を巡らせて脾胃を整える薬……それなら、紫蘇に勝るものはありません!」
「では、どの処方を使う?」
小指月は自信満々に答えました。
「香蘇散です!」
香蘇散内草陳皮,外感風寒気滞宜。
悪寒発熱胸満悶,解表又能暢気機。
(香蘇散は甘草と陳皮を含み、外感風寒と気滞に適す。悪寒や発熱、胸が痞えて悶々に対し、解表しつつ気機を整える)
指月はリズムよく方歌を唱えました。
香蘇散は、紫蘇に香附・甘草・陳皮を加えた四味薬で構成されます。
紫蘇葉は肌表の風寒を発散させ、悪寒・頭痛・無汗の症状を解消します。
さらに、紫蘇葉に香附・陳皮を組み合わせることで、気を巡らせ、脾胃を整え、胸脘の痞えを解消し、食欲不振を改善させるのです。
この処方を服用した子供は、二日後には食欲が戻り、寒がることもなくなりました。
食欲が回復すると、子供は元気いっぱいに走り回り、笑顔を取り戻しました。
指月はその姿を見て、とても嬉しくなりました。
「祖父の処方は本当にすごいですね」
祖父は指月の頭をポンポンと叩きました。
「薬を誤れば、病は長引く。だが、適切に用いれば、たった一剤で治すことができるのだよ」
指月は「どんな時でも適切な診断・処方ができる医師になる」と強く決心しました。
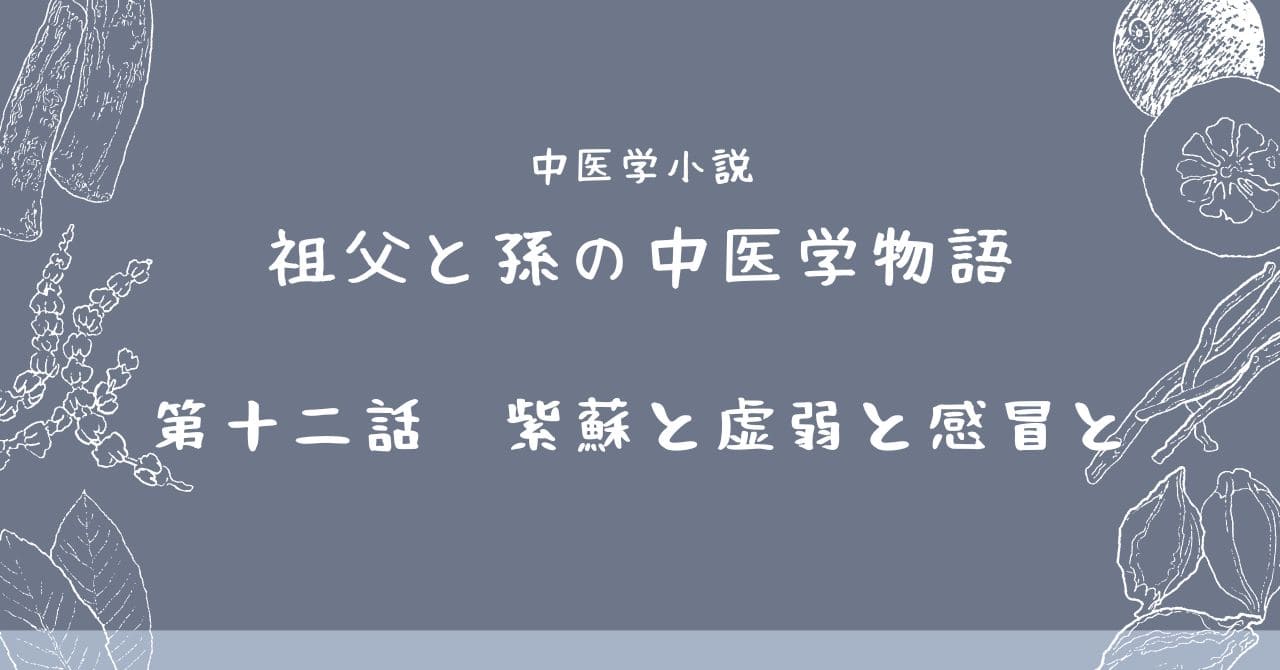


コメント