茅葺きの家では、慢性病に対しては多くの場合、湯方(煎じ薬)の処方だけを出し、患者に町まで薬を取りに行かせるのが通例でした。
もし、急ぎで薬草を必要とする場合は、祖父は自分の薬棚に備えてあるものを出すか、あるいは自ら山に分け入って薬草を採りに行っていました。
この日は、早朝から祖父と指月は、薬草を採りに出かけました。
しかし、今日はいつもと違いました。
いつもなら、指月は元気いっぱいに祖父の前を走っているのに、どうしたことか今日はまるで元気がなく、祖父に後れを取っていたのです。
祖父は心配して尋ねまし。
「いつものように元気に跳ね回るお前はどこへ行った?」
「祖父、なんだか今日は山道を歩いてると頭がふらふらして、くしゃみも出そうになるんです」
祖父は足を止めました。
「朝出るときに、生姜を一片噛んでおきなさいと言ったろう? ちゃんと噛んだのか?」
指月は首を振った。
「だって、辛いじゃないですか……。何度か試したのですが、どうしても嫌で……」
祖父は笑いながら言いました。
「それじゃあ不調になるのも当然だ。早朝の山道は、水気や寒気、山嵐瘴気(さんらんしょうき:霧が立ち込めた山中で生じる疫病)がある。生姜は悪気を祓い、神明を通す力がある。それを口に含まずにどうやって気を奮い立たせ、寒気を追い払うというんだ?」※神明を通すとは、心の状態が安定させ、思考能力が保たれること)
そう言いながら、祖父はまるでマジシャンのように袋の中から生姜を二片取り出し、指月に渡した。
「さあ、早く噛みなさい。さもないと、病気の猫のようになってしまうよ」
指月はしぶしぶ生姜を口に放り込んだ。
(辛味はあまり好きじゃないけど、仕方ない……。早朝の山には霧や露、湿気が多く、瘴気も強い。太陽も昇りきっていないから、最も風寒の邪に侵されやすい時間帯だ)
指月の考えていることを見透かすように、祖父は話し始めました。
「だからこそ、山中を早くに歩く採薬人は皆、生姜を身につけて身を守るのだ。『本草綱目』にはこう記されている。『朝早く山中に行くなら、生姜一片を口に含むとよい。霧や露、清湿の気に侵されず、山嵐瘴気も防げる』この一文こそ、一生にわたる知恵の結晶である。本草綱目を記した李時珍は本草の巨匠だよ。山と向き合って生きる者は、常に山中の寒湿や霧気、そして瘴気と向き合わねばならない。もし身を守る術を知らなければ、ただ一度山を歩いただけでも、風邪をひいたり、下痢をしたり、身体がだるくなったりするんだ。多くの山中の住人が、理由もわからず風湿痹症(リウマチや関節痛のような症状)にかかるのもそのためだ。長年にわたって風寒にさらされ、それを温通・発散する方法を知らないから起こるんだよ」
口の中に広がる生姜の辛味が体内を駆け巡ると、それまで気力をなくしていた指月は、まるで空気を入れたボールのように元気を取り戻し、またピョンピョンと祖父の前に跳ねて出ました。
そして指月の声が、青い山と緑の水にこだましました——
《採薬歌》
草木の茎が中空であれば、風邪を治すのに優れている(草木中空善于治風)。
葉や根に毛があれば、血に関連する病気を治す(根有毛治血之宗)。
茎にトゲがあれば、瘀血を取り除き、腫れを消す(葉杆生刺祛瘀消腫)。
葉の中にが含まれていれば、膿を引き出すことができる(叶里藏浆可以抜膿)。
茎が多く、白い花が咲くものは寒性があり(多梗白花寒性相同)、
赤い花で、丸い茎を持つものは温性で通じを良くする(紅花圓梗性属温通)。
香りが芳しいものは、気の巡りを良くし、痛みを和らげる(気味芳香行気止痛)。
辛味があるものは、蛇や虫による害を治す(気味辛辣治寄蛇虫)。
枝や葉をすりつぶして、打撲に使い(対枝対葉跌打之用)、
山に登って薬草を採るときに役立つ(上山採薬有所适用)。
さらに歌は続きました——
どうぞお受け取りください、淮山の草木の香りを(笑納淮山草木香)。
神曲が寺院で響き渡るのを耳にしながら(聆聴神曲寺中揚)。
朱砂が春の道を鮮やかに彩り(朱砂点破陽春路)、
琥珀が半夏の里へと戻っていく(琥珀回穿半夏鄉)。
目を上げれば、赤い花が険しい崖に燃え立ち(举目紅花焼峭壁)、
目を伏せれば、白い菊が垣根のそばで静かに咲いている(低眉白菊卧籬墙)。
使君子と遠志が漢の国を目指し(使君遠志当帰漢)、
玉竹は依然として熟地に隠れている(玉竹依然熟地蔵)。
こうして、祖父と指月の一日は、歌と薬草の香りに包まれて過ぎていきました。
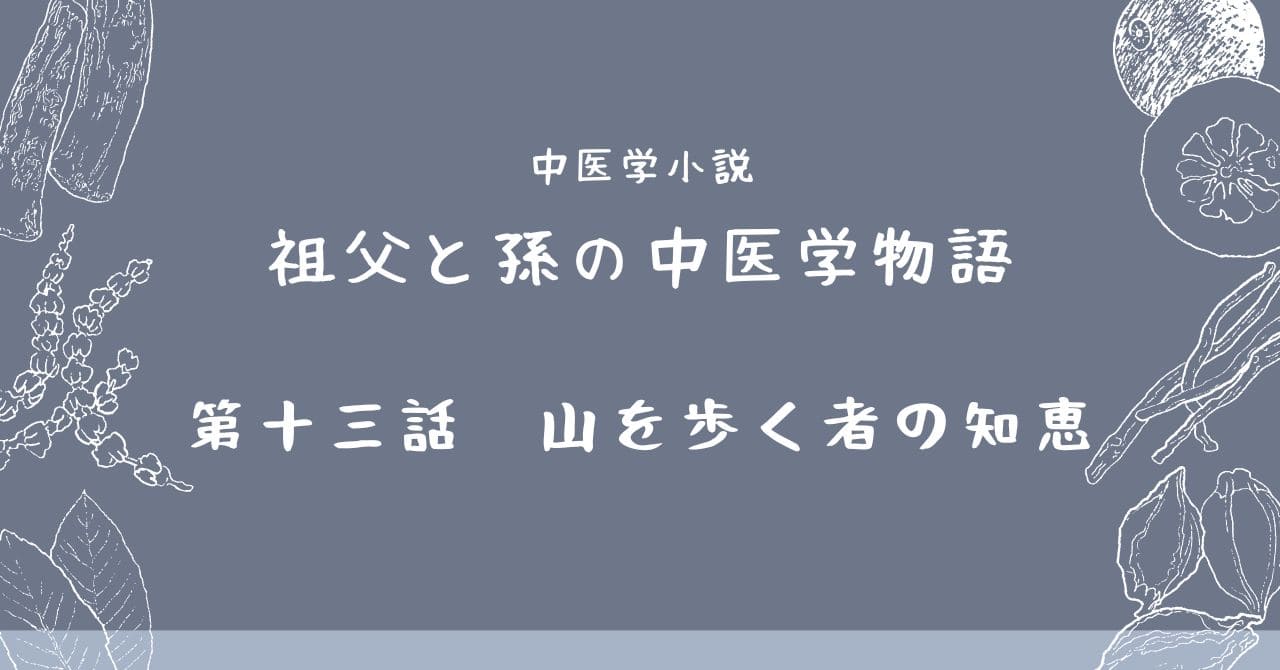


コメント