山のふもとに、羊を飼って暮らす夫婦がいた。
二人にはひとり息子がいた。
彼は真面目に働こうとせず、遊び惚けては飲み歩き、あげくには賭博にも手を出すようになっていた。
もともと多くない家財は、みるみるうちに失われ、ほとんど一家離散寸前まで追い込まれていた。
周囲の村人や、町の年配者たちが何度も忠告し、「今ならまだ引き返せる」と諭したが、彼は一向に耳を貸さず、ますます深みにハマっていった……。
ある日、彼はいつもの仲間たちと町で飲み過ぎ、さらに冷たい果物をむさぼった。
その帰り道、彼は突如として嘔吐を繰り返し、家に着いたころには激しい下痢まで始まった。
体はすっかり干からびた若芽のように萎れてしまっていた。
数日間経っても、彼は何も口にできず、少し湯を飲んでもすぐに嘔吐した。
その姿に、両親はただただ胸を痛めるしかなかった。
藁にもすがる思いで、両親は山の中腹にある茅葺きの家を訪れ、助けを求めた。
両親に案内され、祖父と指月がふもとの家を訪れると、祖父は患者の様子を一目見るなり、原因をすぐに見抜いた。
「指月よ。冷たい果物と酒による胃腸の傷み、それにより吐き気が止まらない……さて、どう治す?」
祖父の問いに、指月は元気に答えた。
「もちろん、嘔吐を止める聖薬を使います!」
祖父は満足げにうなずいた。
「そうだ、生姜の汁は止嘔の効果が抜群だ」
祖父は夫婦に命じて、生姜を一塊すり潰し、汁を搾ってもらった。
さらに、薬籠から「藿香正気散(かっこうしょうきさん)」を取り出し、生姜汁と混ぜて、息子に飲ませた。
すると、飲み終えて間もなく、あれほど苦しんでいた吐き気がぴたりと止まった。
彼はお腹の中に、じんわりと温かい気が巡り出すのを感じはじめた。
そして、空腹を覚えるようになった。
「……何か食べ物を。そうだ、粥が欲しい……」
その言葉を予想していたかのように、祖父は両親に、すでに山芋粥を作らせていた。
粥を口にすると、息子はなんと吐かずに飲み込むことができた。
実に三日ぶりの、まともな食事だった。
「吐かずに食べられるようになれば、体力の回復は早い」
夫婦は涙を浮かべて何度も頭を下げ、若者もまた、死の淵から救い出してくれたことに、深く感謝した。
「それではこれで失礼」
帰ろうとした祖父をみて、息子が気づいた。
「先生、靴ひもが解けていますよ!」
祖父はニッコリと微笑み、こう言った。
「やれやれ、歳を取ったものだ。手は震え、目は霞んで、細かい文字も見えにくい。最近は本を読むにも拡大鏡が手放せない。こうして靴ひもが緩んでいても、自分で腰を曲げて結ぶのもひと苦労だ……すまないが、結んでくれないか?」
息子は喜んで膝を折り、祖父の靴ひもを結んだ。
すると祖父は、しみじみと語りかけた。
「ありがとう。若いというのは、本当に素晴らしい。目も手もよく働く。でも見てごらん、年を取ると、人はどんどん衰えていくんだ。君も、いまのうちにやるべきことをしっかりやりなさい。この老いぼれのように、目も手も利かなくなってからでは、何もできなくなるぞ」
その言葉は、雷のように息子の胸に響いた。
息子がまだ反応しきれないうちに、祖父と指月は静かに背を向けて、山へと戻っていった。
それからというもの――
息子は一切、酒や博打に手を出すことはなくなった。
両親のもとで真面目に羊を飼い、畑を耕した。
やがて借金を完済し、結婚して家庭を築いた。
帰り道、指月は不思議そうに祖父に尋ねた。
「祖父? 祖父は手なんて震えてないですよね。目だって全然見えてるし、毎日私よりも本を読んでいます。拡大鏡なんて一度も使っていません。靴ひもだって、毎朝自分でさっと結んでいるではありませんか。それなのに、なんであの息子に“見えない、できない”って言ったのですか? なんでウソをついたのですか? 祖父はいつも私に、“人は嘘をついてはいけない”って言ってたじゃありませんか」
祖父は、指月の頭を煙管でコツンと軽く叩いて言った。
「“嘘が真になれば真もまた嘘、真が嘘になれば嘘もまた真”――この世の真偽なんて、はっきり割り切れるもんじゃないのだよ。大事なのは、言葉の表面じゃなくて、その奥にある“心”を見ることだ。お前も大きくなれば、きっとわかる日が来るよ」
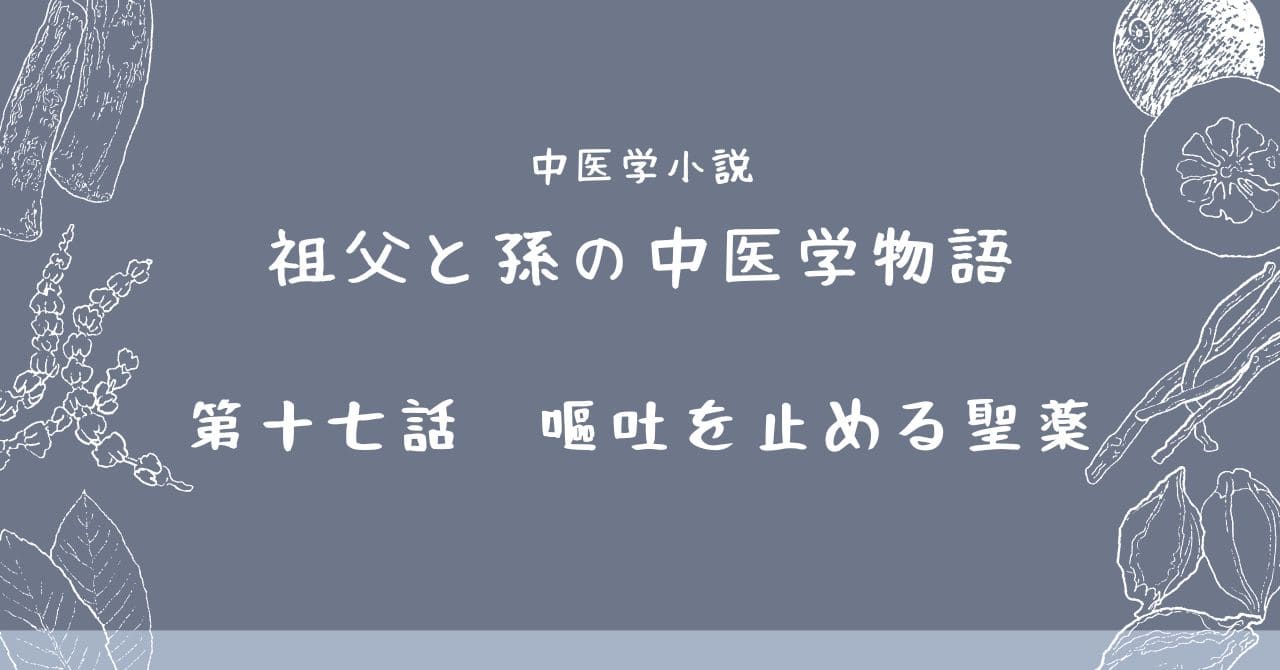


コメント