「男にとって、生姜がないのは百の備えを欠くようなものだ」
『論語』には「姜は撤せず、多くは食せず」と記されている。
※撤せず:てっせず(撤するは「取り除く」という意味)
毎回の食卓には必ず生姜を添えるべきだが、食べすぎてはならないものだ。
生姜はただの食材ではない。
正しく用いれば、健康を保つ延年の妙薬となる。
とりわけ山中や、年中冷えや湿気に晒されるような環境では、生姜はまさに“命を延ばす良薬”となる。
ある日、指月は祖父とともに山道を歩いていた。
その途中、一つの古びた禅寺にさしかかった。
寺は青竹に囲まれ、世間から隔絶されたような静寂な地に佇んでいた。
周囲には山々が連なり、澄んだ水が流れ、空気には木々の香りが満ちていた。
「神秘的ですね。ここはまるで、この世ではないようです……」
そのとき、蝉の声と鳥のさえずりが響いた。
(ああ、これは夢ではないのだ)
指月は、いつの日だったか、祖父が詠った詩を思い出した。
「蝉の声が林をより静かにし、鳥の声が山の幽けさを際立たせる」
石段には苔がびっしりと生え、遠くからは読経の声と木魚の音がかすかに聞こえた。
道の脇では、山羊がのんびりと歩きながら、見慣れぬ来訪者をじっと見つめていた。
「不思議ですね。他の場所で山羊を見るとすぐ逃げちゃうのに、ここの山羊は近寄っても平気なんですね」
祖父は笑って言った。
「ここは仏門の清修の地だ。周囲十里、狩人ひとり足を踏み入れない。だから、この地の鳥も獣も、人間を恐れないんだよ。仏の静けさは動物の心にも通じるのさ」
初めて“清修の地”というものを知った指月は、目の前の山羊を撫でてみたい気持ちをぐっとこらえた。
ちょうどそのとき、寺の山門から一人の老禅師が現れた。
まだ近づかぬうちに、禅師の響き渡る声が耳に届いた。
「遠路よりお越しいただいたのに、出迎え遅れ、まことに失礼!」
祖父は手を合わせ、深く頭を下げて言った。
「お手を煩わせてしまい、恐れ入ります。清修の場に押しかけて申し訳ありません」
その横で指月が遠慮なく口を挟んだ。
「あの、どうして私たちが来るのがわかったのですか?」
「こら、指月、無礼だぞ!」
祖父がたしなめると、禅師は笑ってこう言った。
「人はまだ来ぬが、先生が纏う薬の香気が先に届いておったのだ。かつて先生に風湿の痺症を治していただいたのだ。先生の香気は忘れられんよ」
指月はその言葉で、祖父がかつてこの禅師を治療していたことを知った。
「……いったい、どんな薬を使ったのだろう?」
祖父は淡々と答えた。
「出家の身は四大皆空。たかが風湿、騒ぐほどのことではありません」
四大みな空(くう)なり;世界のすべてのものは空虚であるという意味。仏教では地・水・火・風の宇宙を構成する4元素を“四大”という。
禅師は声を上げて笑った。
「仏もこう申しております。“人ひとりを救うは、七層の塔を建てるに勝る”と。先生は多くの命を救っている。まさに真の出家者の行いでありますぞ」
祖父は笑みを浮かべてうなずきながら言った。
「身体の病には薬を、心の病には仏法を。今日はその教えを、あらためて学ばせていただきたく……」
禅師は手を振りながら笑って応じた。
「老衲など浅学菲才。せいぜい口禅を少々唱えるばかりです」
老衲(ろうのう);年をとった僧侶。老僧。また、年をとった僧が自称としても用いる。
浅学非才(せんがくひさい);学問や知識が浅く未熟で、才能が欠けていること。自分の識見をへり下っていう語として用いられることが多い。
小指月はふと疑問に思った。
「先ほどから“老衲”って言ってますけど……あんまり年をとっているようには見えません。四、五十歳くらいですよね?」
確かに、その禅師は目元も口元も柔らかく、どこか童子のような顔立ちをしていた。
禅師は静かに答えた。
「生姜を服して、かれこれ四十余年。それゆえ老いが現れぬのじゃ」
驚いたことに、禅師はすでに八十歳を超えていた。
聞くところによると、禅師は若き日、山に籠もり修行するうちに、心ばかりに重きを置き、身体を顧みなかった。
その結果、三十代で重度の風湿病に悩まされ、脚もまともに動かず、顔色もやつれてしまったそうだ。
そんな禅師を救ったのが、指月の祖父が授けた「生姜養生法」だった。
毎日少量ずつ生姜を取り入れることで、胃を温め陽気を助け、長年の素食で体に溜まった寒湿を取り除いた。
脾胃が健やかになれば、四肢に力が通う。
脚の冷えも消え、体は次第に強くなり、禅師の顔色には血の気が戻った。
体が整えば、座禅の修行も一層深まっていった。
「この身体は、あの時の恩のおかげです」
禅師は穏やかに語ってくれた。
禅師は祖父と指月を寺に招き、案内した。
そのあと、茶室で共にお茶を飲み語らった。
祖父がふと問いた。
「“心、太虚を包み、量、沙界に周る”とは――どういうことでしょう?」
禅師は静かに一つの動作を見せた。
口笛をひとつ吹くと、窓の外から一羽の鳥が飛び入り、彼の掌にふわりと舞い降りた。
禅師はその鳥を軽く包み込み、また放すと、鳥は指先に頬をすり寄せ、再び空へと舞い上がった。
禅師は微笑み、ひとこと言った。
「……お分かりかな?」
祖父もまた、にこやかにうなずいた。
指月には、彼らの言葉も行動も意味が理解できなかった。
だがその光景に心を打たれた。
その後は言葉もなく、ただ静かに寺の中を散策した。
やがて夕暮れ、指月は祖父とともに、再び山を下っていった。
帰り道、指月はたまらず祖父に尋ねた。
「あの鳥……どうして警戒することもなく、禅師の手にすっと乗ったのでしょう?」
祖父はほほ笑みながら答えた。
「天地の心を抱く者には、鳥もまたその掌に帰るものだよ」
この日、指月は「生姜」という薬草に、またひとつ新たな価値を見出しただけでなく、心のあり方と自然との調和にも、深い感銘を受けたのだった。
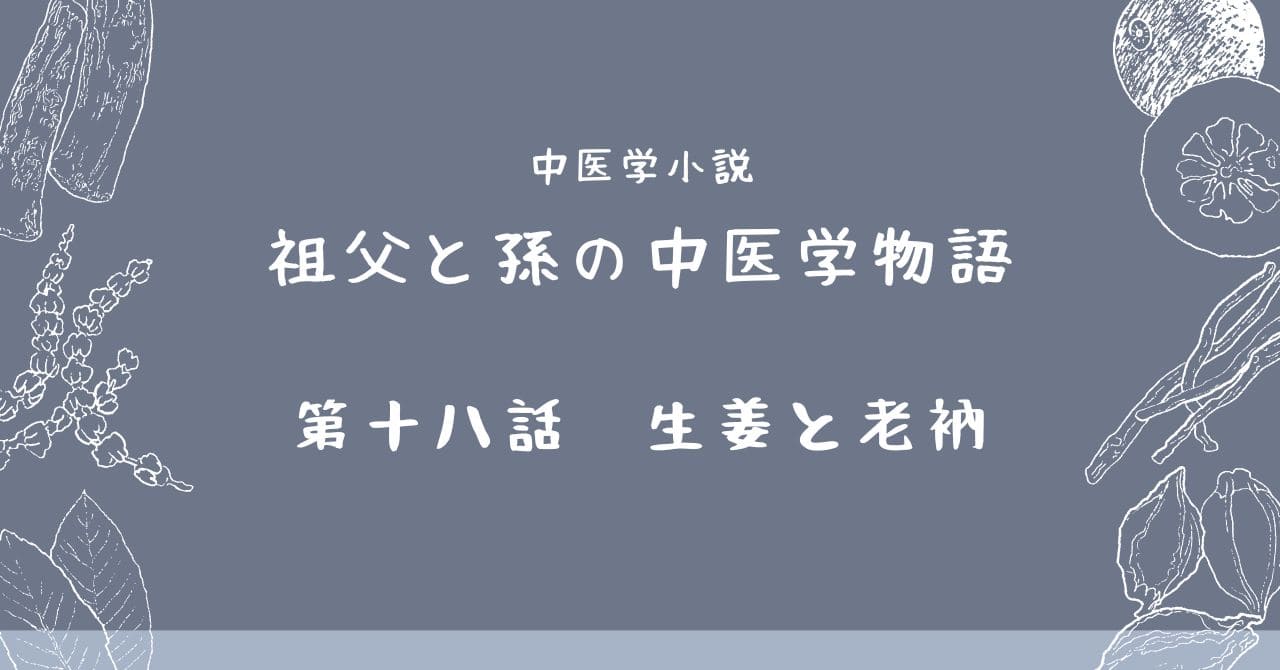


コメント