秋の風が吹き始め、空気が少しずつ冷たくなってきたある日、山の林を見守っている年配の農夫が、急に倒れこんでしまった。
ここ数日、風と雨が続いていた。
それなのに、もともと丈夫でなかった体で草を刈りに出たとき、うっかり上着を忘れたのだ。
それがたたり、腹が冷えて激しく痛み、下痢が止まらなくなった。
あまりの回数に、ついには手足に力も入らず、立ち上がることさえできなくなっていた。
家族は最初、何か悪いものでも食べたのだろうと考え、「お腹に熱毒があるに違いない」と、涼性のあるお茶で毒を取ろうとした。
だが、それは虚弱な老人にとっては、まさに“雪に氷を重ねるようなもの”だった。
下痢はさらにひどくなり、床から起き上がれなくなってしまった。
強者でさえ“三度の下痢には敵わない”というのに、一日に七、八回も下していては、命にかかわってくる。
こうして祖父と指月は、農夫のもとに呼ばれることになった。
指月が農夫を見て、まず驚いたのはその顔だった。
顔のしわはまるで乾いた樹皮のようで、血色はなく、ここ数日まともに栄養も取れていないため、息を吸うのも苦しそうだった。
小指月は思案に暮れた。
薬百種類の薬草があれば自信も出だが、ここは辺鄙な山の中。
薬は乏しく、たとえ金があっても、町の薬屋まで買いに行くのは困難だった。
(こんなとき、一体どうすればいいんだ……)
指月は長いこと考え込んでいたが、よい手立てが浮かばなかった。
そんなときだった。
祖父はまるで最初から策を練っていたかのように落ち着き払って、農夫に語りかけた。
「あなたの体はすでに年老いて陽気が弱く、体力も乏しい。だから一般的な“下痢の治療法”に従って薬を与えるのは、かえって害になる。確かに、“痢(下痢)に止む法なし”とは言うが、それは「全ての下痢に“通じさせる薬”を使うべき」という意味ではない。体内に熱毒や汚濁が滞っていて、どうしても出し切る必要があるときには、寒性の通下薬を使って邪を追い出す。だが、あなたの場合は体の陽気がすでに弱い上に、肛門の筋力もゆるく、しばしば脱肛ぎみなのだから、これ以上“通じさせる”薬を使うのは危険だ。むしろ、中焦(脾胃)の機能を温めて立て直し、身体の外側に入ってきた風寒を追い払うために“温中散寒”の薬を使うべきなのだ」
農夫やその家族は、長年山の中で暮らしているだけに、ある程度の医学の知識は持っていた。
だが、所詮は素人の域を出ないものだった。
病名に引きずられて本質を見誤り、“雲の向こうに晴れがある”ことに気づけず、見た目の症状の奥にある病の理(ことわり)にまでは到達できていなかった。
そんな様子を見ていた指月は、(でも肝心の薬がない……どうしよう……)と心の中で焦っていた。
その焦りを見透かしたように、祖父はほほえみながら、昔から村々に伝わる諺(ことわざ)を、ポツリと口ずさんだ。
「一杯の茶に、一片の生姜——寒を払い、胃を健やかにする良薬なり」
そう言うと、生姜を細かく刻み、茶葉と一緒に急須に入れて、「生姜茶」を作った。
指月は、祖父が生姜の皮を剥いているのを見て、不思議に思った。
「祖父、なぜ皮を剥くのですか?」
祖父はにこやかに答えた。
「『集験方』にはこうある。“生姜茶は下痢の簡便な処方である。生姜を細かく刻み、茶と一緒に飲むとよい。だが、熱による下痢なら皮付きで、寒による下痢なら皮を剥く。”——そこが“妙”なんだよ」
農夫に、一杯の熱々の生姜茶をすすめると、彼は「ほぉ……なんと気持ちいい……」と、しみじみ言った。
祖父はやさしく言葉を添えた。
「ゆっくり飲みなさい。年寄りの腹は弱っている。茶も、千口をもって一杯とし、じっくりと味わうのがよい。焚き火と同じさ。最初から太い薪をくべれば、火は消えてしまう。だから、まずは小枝を少しずつくべて、じわじわと火を育てるんだよ。病床にある老人も同じで、飲むも話すも、“静かに、ゆっくりと”が大切だ」
農夫はうなずきながら、「本当にそうですね」と感心していた。
翌日、農夫はすっかり回復し、自分の足で起き上がり、ふたたび仕事に出かけていった。
生姜茶を飲んでからというもの、下痢はぴたりと止まり、再発することもなかった。
祖父は指月に今回の症例について説明した。
「どうやら今回の下痢の原因は、体内に熱毒がこもっていたのではなく、加齢によって体が弱り、陽気が不足していたところに、季節の変わり目で冷え込み、風寒が体表に侵入したことだったようだ。その寒気は、脾胃が司る四肢をめぐって腹部へと入り込み、陽気の乏しい腹部では、飲食物の運化(代謝・吸収)をうまく行えず、その結果、下痢が起こっていたのだった。そこへ、生姜茶が体内に入り、脾胃の中土をしっかり温めたことで、運化が回復し、結果として下痢が止まり、腹痛もすっかり治まったんだ」
指月は、ずっと気になっていたことを尋ねた。
「生姜の皮を剥いたことについて、もっと教えてください」
祖父は、きっとそう聞いてくるだろうと思っていたかのように、にっこり笑って答えた。
「生姜の皮には、体の表面を巡らせる働きがある。性質は辛涼だ。それに対して、生姜の中の“身”の部分は、内臓にとどまりやすく、性質は辛温だ。だから、身体の内側――特に“中焦”を温める力があるんだよ。年を取って陽気の衰えた人や、冷えが原因の下痢をしている人には、たとえわずかでも“涼”の性質があるものを与えると、病を悪化させかねない。だから、皮を取り去って中身だけを使い、その“温中散寒”の働きで下痢を治すんだ」
指月は驚きとともに、思わずつぶやいた。
「同じひとかけの生姜で、皮と中身とでこんなにも性質が違うなんて! 皮は“辛凉”、身は“辛温”……まさに陰と陽がひとつの中に共存してるんですね!」
そう言うと、指月はノートにこう書き記した。
生姜茶、一椀の処方。
冷えと痛みには、皮を剥いて試すべし。
肉は辛温、皮は辛涼。
寒熱を見極め、病に応じて活かすべし。
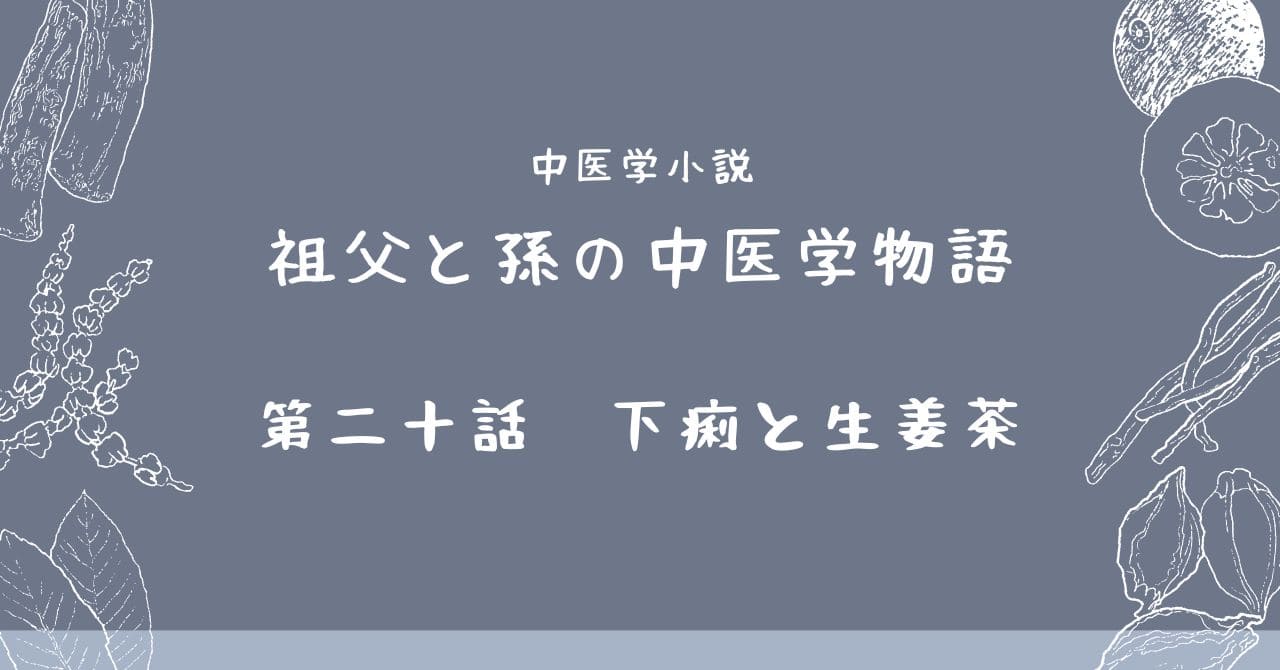

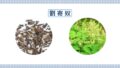
コメント