風邪を引いたときに使う薬は、その季節や状況によって異なる。
冬には麻黄、夏には香薷がよい。
だが、風邪を引いたのが産後の女性であれば、話は別になる。
出産直後の身体は、血が消耗し、脈は空虚になっている。
もしこの状態で風に当たり、頭がふらつき熱が出たとしたら──。
そのときは、普通の風薬では太刀打ちできない。
血脈に入り、血中の風邪を抜き出すことができる、特別な薬が必要になる。
それが、血中風薬の第一薬、「荊芥」である。
ある日、生後まだ十日ほどの赤子を抱える産婦が、部屋の中ばかりで過ごすのが退屈だと、朝の散歩に出かけた。
家族は、「風に当たらないよう帽子をかぶれ」、「冷気は避けるんだよ」と何度も諭したが、彼女は聞き入れなかった。
「今はそんな古臭い、迷信的なことを気にする時代じゃないわよ。最近の病院なんて、産後すぐに退院して、みんな仕事に戻ってるじゃない」
そんな言葉を残して、涼しい朝の空気の中へ、ふらりと出ていった。
最初はご機嫌で草花を眺めていたが、しばらく歩くうちに顔色が変わり始めた。
風に当たりすぎたせいか、頭がぼんやりしはじめ、身体に熱がこもるような感覚が襲ってきた。
慌てて家に戻ったが、すでに手遅れだった。
彼女は知らなかった。
出産後の女性の体は「血の海」が不足し、すべての脈が虚ろな状態になっていることを──そして、まさにその時期こそ、風邪を受けやすく、冷えに傷つきやすいということを。
たとえ家の中の窓を開けるにしても、その開け方は慎重にしなければならない。
とくに体が虚弱な者にとっては、「産後の養生」の作法をきちんと守り、心を静かにして体を休めることこそが、なにより大切だったのだ。
まるで蚕の繭のようなものだった。
なぜ、あの柔らかな生き物が、外界から自らを守るために、あの殻を必要とするのか。
それは、時が来るまで静かに、じっくりとその中で力を蓄えねばならないからだ。
もしも早まって繭を切り開き、休むべき時間を与えなかったなら──やがて羽化し、産卵へと向かうその一歩は、大きく狂ってしまう。
風を浴び、冷気に触れ、まだ固まっていない生命の芽を傷つければ、成長は深く妨げられてしまうのだ。
では、どうするか。
外に出て医者を訪ねることもできないとなれば、医者を家に呼ぶほかなかった。
祖父と指月が訪ねたとき、産婦はすでに布団に横たわり、顔には熱の気配がにじみ、めまいに苦しんでいた。
指月が手を取り脈を診ると、脈は浮いていた。
しかし深く押さえると、そこには明らかな虚──
「さて、どうする?」
祖父の問いに、指月は困った。
(発散薬で風邪を追い払おうとすれば、腎の気まで散じてしまい、ただでさえ虚している身体を、ますます損ねてしまう。かといって、補薬を使おうとしても、体内にはすでに風邪が入り込んで、外感発熱となっている。こんな状態では、いくら補薬を使っても、その効き目は届かない‥‥‥)
そんなとき、祖父が静かに口を開いた。
「婦人科の古方に、血中の気に働きかける風薬がある。これを使えば、血分に入り込み、そこに潜んだ風邪を体の外へと導くことができる。とりわけ、血中の風邪による瘀滞に対しては、この薬が最もよく効くとされている。傅青主は『傅青主女科』の中で、これを用いて多くの女性の病を癒している。さて、何という薬だったかな?」
すかさず指月が答えた。
「もしかして……荊芥?」
祖父は静かに肯いた。
「そうだ、荊芥だよ。荊芥には二つ形がある。ひとつは全てを含む『荊芥』、もうひとつは花穂の部分の『荊芥穂』だ。中でも、荊芥穂のほうがより強い発汗作用をもち、しかも下焦にまで達する力を持っている。だからこそ、出産後に血を損じた婦人が風を受けたとき、その深く入り込んだ風邪を、根こそぎ引き抜くことができるんだよ」
指月は眉をひそめた。
「でも……風薬は、動血させてしまうのではないでしょうか?」
指月は少し不安そうに尋ねた。
すると祖父は、穏やかに微笑んでこう答えた。
「証があるなら、その薬を使う。産後の女性は血が虚している。だが、煎じ湯に少し紅糖を加えてやれば、風を祓いつつ、血も養える。風邪を発散しながらも気を損なわず、血分まで届きながら陰も傷つけない――これこそ、産後の血晕と発熱を治す妙法なんだよ」
彼女が、薬を口にしてほどなく、あれほどふらついて熱っぽかった産婦の頭がスッと冴え渡った。
身体にはうっすらと汗がにじんだが、衣が濡れるほどではない。
その感覚がなんとも心地よく、ふだんであれば二服目を要するところ、一服で起き上がれるまでに回復していた。
立ち上がる彼女を見て、祖父は静かに言った。
「産後の養生は何よりも風を避けること。それが一番大事だよ」
彼女は、恥ずかしそうに目を伏せた。
我が身の偏った思いが、こうして自らを苦しめていたことを、ようやく悟ったのだった。
その日から、彼女は素直に家族の言葉に耳を傾けるようになった。
産後は仕事を控え、風に当たらぬように努めた。
静かに身体を休め、テレビや携帯の使用も最小限にした。
かつての「古臭い」と一笑に付していた教えが、いまは確かな命の支えとなって、彼女の心にしみわたっていた。
茅葺の家に戻ると、祖父は書棚から一冊の古書を取り出した。
それは《本草思辨録》――草薬の効能を深く考察した名著だった。
ページをめくりながら、祖父は指である一行を示した。
その言葉を目にした瞬間、指月は「はっ」と声をもらし、目を見開いた。
「そうか……だから荆芥だったのか……」
祖父が選ぶ薬には、いつも裏づけがある。
思いつきや経験則だけではない。
そこには古の医家たちの知恵が積み重ねられていた。
(やっぱり……もっと古書を読まなきゃだめだ……)
そう自分に言い聞かせながら、指月はノートに記した。
「荆芥、血中の風を散じ、産後血晕の第一要薬とする」
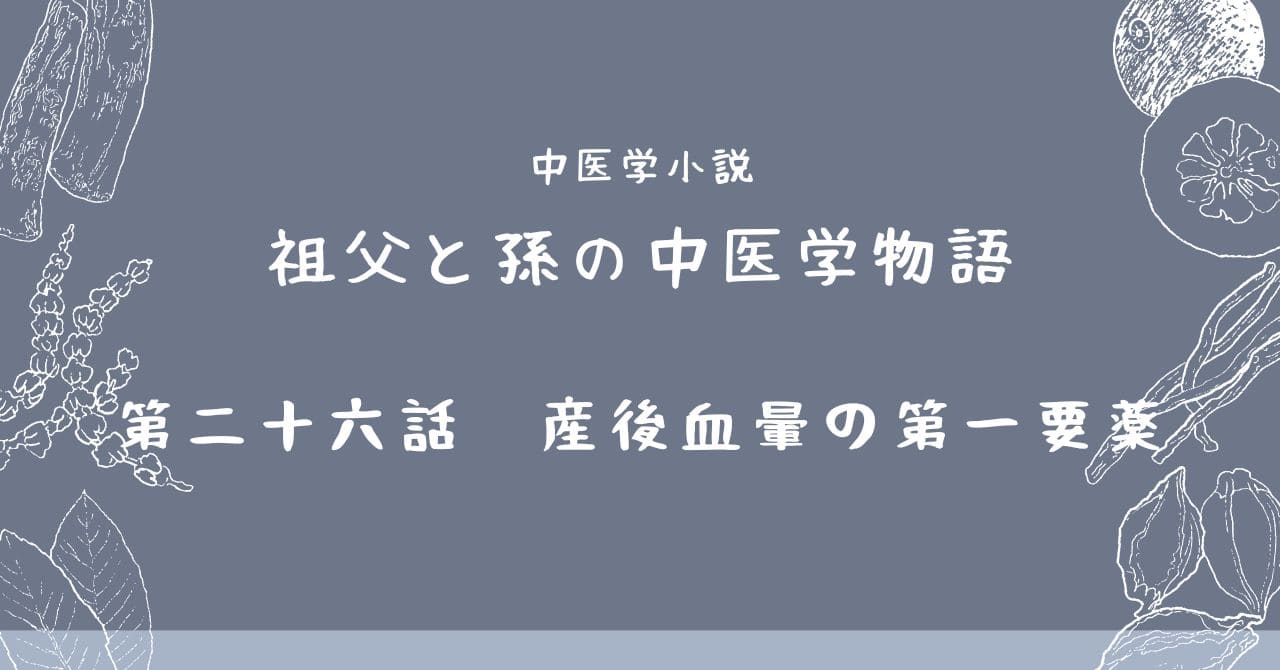

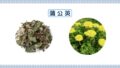
コメント