「名医は咳を治さず。咳を治そうとすれば顔に泥を塗ることになる」とは、医界で語り草となっている言葉である。
指月はこの風刺めいた一句をふと思い出し、疑問を抱いて祖父に尋ねた。
「祖父、なぜ名医でも咳には手を焼くのでしょうか? 咳は、そんなに難しい病なのですか?」
祖父は穏やかな笑みを浮かべながら、反問した。
「《黄帝内経》にはどう書いてあったかな? 咳を起こす臓腑は、どこだと言っていた?」
指月はすぐに答えた。
「五臓六腑、皆肺を咳せしむ。ただ肺のみならず、ですね」
祖父は満足そうにうなずいた。
「咳が難しいのは、薬の選び方じゃない。難しいのは“証”を見極めること、つまり病の根を探ることにあるんだよ」
その言葉に、指月の脳裏にふと浮かんだ一節。
「“必伏其所主,而先其所因”――なるほど。病を治すには、その現れている症状(結果)だけを見るのではなく、まずはその原因を探し出し、そこに手を打たねばならぬ、ということですね!」
祖父はますますうれしそうにうなずいた。
「肺は“金”に属す。金は鐘と同じ、打てば鳴る。つまり、内から情志や飲食の邪で打たれれば鳴り、風寒湿熱の邪が外から打てば、それでも鳴る。中も外も叩けば鳴るのじゃ。だからこそ、咳は虚実入り乱れ、寒熱複雑に絡み、病因がはっきりしない。だから薬も選びにくいんだよ」
「なるほど……咳って、ささいな症状に見えるけど、実は複雑なんですね」
指月は、咳という病の奥深さに引き込まれていった。
そんな時、茅葺の家に、咳が止まらず困り果てた男がやってきた。
「もう一ヶ月も咳が続いていて、どんな薬を試しても全く効かないんです……」
祖父が脈を取ると、すぐに顔を上げて言った。
「浮脈だね。さて、これまでどんな薬を使んだい?」
男は苦笑いを浮かべながら答えた。
「川貝の咳止め膏も、雪梨膏も、鎮咳水も……とにかく咳に効くと言われたものは全部試しました。でも全然止まらなくて。しかも今では、ちょっと風が当たっただけで咳き込むし、ときどき血まで混じるようになったんです」
それを聞いた指月が、改めて脈を触れた。
やはり浮いている。
「風を怕れ、風に触れると咳が出る。やっぱり“表証”ですね」
祖父はすぐさま問いかける。
「それならば、そんな状態で収斂薬ばかり使えば、どうなる?」
指月はにやりと笑って答えた。
「“閉門留寇(へいもんりゅうこう)”。邪を閉じ込めてしまえば、咳なんて治るはずがありません!」
「なら、どうする?」
「表にある邪なら、汗を出して発散します。つまり“開門逐寇(かいもんちくこう)”――門を開けて、賊を追い出しましょう!」
祖父は満足そうにうなずいた。
「では、荆芥を含む“止嗽散”を使おう」
指月はすぐさま薬歌を口ずさんだ。
止嗽散には桔梗・甘草・白前を用い、
紫苑・荆芥・陳皮・百部を細かくすり混ぜる。
肺の気を宣通し、風を祓い、咳と痰を鎮める妙方なり。
煎じる必要はなく、生姜湯で服せよ。
そして棚から、あらかじめ粉にしておいた止嗽散を取り出し、紙に包んで数袋、男に手渡した。
病人は、手渡された薬包を見て、眉をひそめた。
「……こんな少しで効くのですか? 私の咳は、もう一ヶ月以上続いてるのに」
そう言い終わるか否か、言葉の勢いでまた激しく咳き込んだ。
指月はくすっと笑った。
「薬を食事と同じだと思っちゃいけません。これは“上焦”に働きかける薬だから、羽のように軽やかでいいのです。少量の散薬こそ、“散”としての力を発揮します。そして、表面に留まった風邪を、素早く追い払うことができるのです」
「でも、喉がムズムズしてたまらないんですけど……」
そう訴える患者に、指月はにこりと笑って答えた。
「心配は無用です。この止嗽散には荆芥が入っています。喉のかゆみを鎮めて、咳を止めるのにぴったりです。しかも、たまに血も混じって咳き込んでますよね? それも、この薬で大丈夫なんです。《本草備要》という書物には、『荆芥の主たる効能は風を治することにあるが、あわせて血を治する力も備えている。それは荆芥が風木の臓に入るからであり、風木の臓とはすなわち“血を蔵するところ”、すなわち肝である』とあります。また、皮膚や膜のすぐ外側にいる風には、防風のように骨や筋肉の奥深くに入ることはない荆芥のほうが効果的だって李士材も言っているのです」
止嗽散に荆芥が含まれているのも納得である。
というのも、荆芥はその性味が穏やかで、寒熱どちらにも偏らず、解表作用を持ちながらも、気の流れを自然に整えるという特性を備えているからだ。
そして、特筆すべきは、「血中の風邪」を祛うという珍しい効能だ。
ただの発散薬ではない。
荆芥は、風邪が血に入り込んだときにこそ、本領を発揮する。
それゆえ、咳嗽に風邪が絡み、血にまで及んだとき――まさに、この薬草の出番なのだった。
「血中の風邪」と言われても、病人には正直よく分からない。
だが、目の前の小さな少年が、まるで古の名医のように堂々と話す姿を見ていると、言葉の意味は分からずとも、心にすとんと落ちてくるものがあった。
彼は黙ってうなずくと、紙包みにされた散薬を持って帰っていった。
指月は止嗽散を六包用意したが、患者はたった三包飲んだだけで咳がすっかり治まってしまった。
残りの三包を持って茅葺の家まで戻り、「これほど効く薬なら、ほかに困っている人に譲ってほしい」と深く頭を下げて礼を述べた。
一ヶ月以上も苦しんだ咳が、たった三包の粉薬で治った。
しかも、その薬は特別なものではなく、ごく普通の安価な薬である。
それなのに、なぜこれほどの効果があったのか?
それについて、祖父は語った。
「薬に高い安いの区別はない。肝心なのは、そのときその人の病に“適している”ことだ。今回の患者は、外から風邪を受けて起こる咳だったのに、飲んでいたのはすべて“肺を潤して咳を止める”薬ばかり。これでは咳の原因である“表の邪気”を外に追い出すことができぬまま、かえってこじれてしまうんだ。だから風にあたるとすぐ咳がぶり返すし、脈も浮いている。こんなときは、少しだけ肺の気を通してやり、温和な解表薬で風邪を外に導いてやることが肝心なんだよ。そこでこの止嗽散だ。たった七味の軽い薬から成っているが、肺気をよく宣通させ、温めても乾かしすぎず、潤しても重くならない。寒を散らしても熱を助けず、邪を祓っても正気を損なわぬ。実に絶妙な処方なんだよ」
祖父は棚から一冊の古書を取り出した。
程鐘齡の『医学心悟』第三巻。
そこに書かれていたのは「治諸般咳嗽」の章だった。
薬は険峻である必要はない。ただ病に当たっているかどうかが肝要なのだ。この方(止嗽散)は、わたしが長年の経験と観察から得たものである。
肺は金に属し、火を嫌う。熱すぎれば咳となり、また金は剛で乾く性質ゆえ、冷えすぎても咳が出る。肺はまた“嬌臓”とも呼ばれ、激しい薬には耐えられず、さらに皮毛を主るために外邪を受けやすい。もし発散せずに閉じ込めれば、邪は中にとどまり、咳が続いて治らぬ。
経に曰く、「微寒あれば微咳あり」。これは寒気を感受した結果であり、まるで小さな賊のようなもの。門を開いて追い出せば、すぐに立ち去る。
ところが、医者がよく見極めず、軽率に清涼・酸収・渋滞の薬を用いてしまえば、まさに“門を閉じて賊を留める”ことになる。出ようとする賊には門がなく、ついには壁を突き破って逃れようとし、咳が激しくなり、血まで混じるようになるのだ。
肺には二つの穴がある。一つは鼻、もう一つは喉。鼻の孔は開いていてこそ健やかで、閉じてはならず、喉の孔はむしろ閉じていてこそよく、開いてはならない。
今、鼻の孔が塞がっていれば、喉の孔が開こうとするのは避けられない。これを憂慮せずにいられようか?
この処方(止嗽散)は温潤で調和が取れ、寒からず熱からず、強すぎる攻撃性もなく、まさに“門を開いて賊を逐う”の勢いあり。
ゆえに客邪は容易に散じ、肺気も安らかとなる。この処方が効果を発揮するのも、道理であろうか。
指月はその一文を読み終えると、目を見開いて祖父の顔を見た。
「だから、祖父は止嗽散をよく使うのですね……咳を止めるのではなくて、肺の働きを整えて、邪を出してやることが本質なんですね」
祖父はにっこりと笑った。
「よし、ではここで一問。肺の咳は、“咳を止める”ことが先か、それとも“肺を理(おさ)める”ことが先か?」
指月は迷わず答えた。
「もちろん、肺を理めることが先です!」
その答えに、祖父は深くうなずいた。
「そうだ。咳という“音”に惑わされるな。その奥にある肺の“気の乱れ”こそ正さねばならぬ。邪が去れば、咳など自然と治まるものだよ」
その言葉は、まるで鐘の音のように、指月の胸に深く響いた。
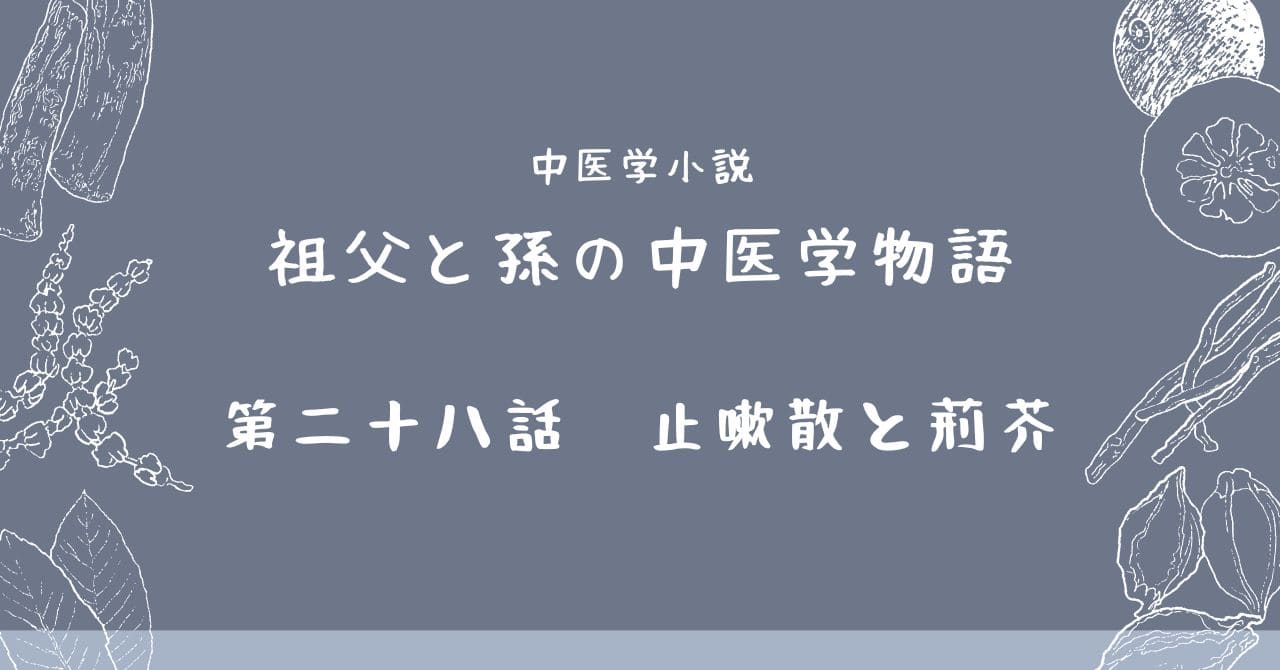


コメント