暇を見つけては、祖父と指月は薬草の話や謎かけを楽しんでいた。
ある日のこと。
「指月よ、ひとつ謎を出してあげよう」
祖父がにやりと笑って言った。
指月はすっと背筋を伸ばし、目を輝かせて答えた。
「いつでもきてください!」
祖父はゆっくりと謎を口にする。
「五月の終わり、六月の初め。家の者が紙を買って、窓に張りつける。夫は旅に出て三年が過ぎた。便りは届けど、一文字もなし――さて、いくつ薬が隠れているかな?」
指月はすぐに答えた。
「五月末から六月初めなら、それは“半夏”。窓に紙を貼るのは“破故紙”。夫が三年も外にいれば“当帰”。手紙に文字がないなら“白芷”!」
自信たっぷりにそう言った指月を見て、祖父はにっこり笑って首を振る。
「惜しい、ひとつだけ違う」
(えっ……全部ぴったり合っていたのに、なぜ?)
指月は首を傾げる。
「紙を貼るのは、何のためかね?」と祖父。
「もちろん、風を防ぐため……あっ!」
その瞬間、指月の顔に悔しさと喜びが交互に現れた。
「そうか、“防風”ですね!」
祖父はうれしそうにうなずいた。
「そう、防風だよ。文字通り、“風を防ぐ”。肌表に入りこもうとする風邪を追い払う薬だ」
そのとき、入口から、誰かが戸を叩く音が響いてきた。
祖父が話を続けようとした矢先のことだった。
指月は、もう慣れっこだった。
話がいちばん面白くなってきたところで、いつも患者がやってくる。
けれどそれも悪くない、と思っている。
病人のいない時間は書を読み、知識を積む。
病人が来れば、目の前の病に向き合い、技を磨く。
祖父はいつもこう言っていた――「半日読書、半日臨床。これぞ医の楽しみだよ」
訪れたのは、三十歳そこそこの男だった。
頭に手拭いを巻き、どこかだるそうな足取りだった。
「もう何日も頭が痛くて……風が当たるとズキズキするし、鼻水も止まらないんです」
指月は問診をした。
「鼻水は黄色くて粘ついてますか? それとも、さらさらで透明ですか?」
「水みたいに、すごくサラサラしてて……とめどない感じです」
指月の脳裏には、すぐさま『黄帝内経』の一節が浮かんだ。
――「諸病水液、澄澈清冷、皆属寒(あらゆる病において、排出される水液が澄んでサラサラしている場合は、すべて寒に属する)」
頭痛に加えて鼻水が透明で、身体の節々も痛み、風に当たると症状が悪化する……これはまさしく「風寒束表証である。
祖父は脈診を終えると言った。
「さて、どうする?」
指月は胸を張って答えた。
「麻黄湯で、汗を出して風邪を追い払いましょう!」
祖父はふふっと笑って、首を横に振った。
「今は夏の盛り。汗をかきすぎると、かえって体を傷めてします。しかもこの人の脈は、浮き気味ではあるが、力が弱い。風寒の邪はそれほど強くないということだ。ここは《荊防散》でいこう」
指月はすぐに筆をとり、「荊芥」「防風」と書いた。
(なるほど、これが軽度の風邪にぴったりの“表散の名コンビ”か)
祖父は以前こう言っていた。
「荊芥と防風を一緒に使うことは、まるで窓に紙を貼るようなものなんだ。紙というものは、薄くて弱いように見えるが、風の侵入はしっかり防いでくれる。それと同じで、荊芥と防風は、軽やかで穏やかな薬ではあるが、人の肌表に一層の“風除け”を張ってくれるんだ。いわば“身体の金鐘罩(きんしょうとう)”だね」
気の力で相手から受けるダメージの一定量を軽減する技術。
彼は薬の包みを受け取り、しげしげと中をのぞき込むと、やや不安げな顔で言った。
「先生、私の風邪はもう十日以上も長引いていて……たった2種類の、こんな少しの薬で本当に治るんでしょうか?」
祖父はにこっと笑みを浮かべて答えた。
「重い船は進みが遅いが、軽い船はひとひらの葉のごとく、山を越え谷を渡ってゆくものだよ。無形の風邪を治すには、まさに“軽舟已過万重山”の理を用いるべきなんだ。重くて力強い薬は、かえって“表(ひょう)”を塞いでしまい、風の出口を奪ってしまうんだよ」
軽舟已過万重山(けいしゅうすでにすぐ ばんちょうのやま)とは、李白の『白帝城』という漢詩にある、「軽やかな小舟は幾重にも重なった山々を通り抜けていった」とい一節。
祖父は、外を飛ぶ一羽の雀を指さした。
「ほら、あの雀を見なさい。羽が軽いからこそ、空へ飛べる。もし羽に水をかけたり、泥を塗ったりすればどうなる? 重くてすぐに落ちてしまうだろう。薬も同じことだよ。風を祓い、邪を抜くには、軽やかで繊細なものがいい。量が少ないからといって効かないわけではないのだよ」
病人は目をぱちくりとさせたのち、ぽんと手を打って言った。
「なるほど! 理に適っていますね!」
その横で指月は、無意識に笑みを浮かべていた。
(まただ。診療のたびに、祖父は不思議な比喩やたとえ話をする。そしてそれが、まるで霧を払う風のように、病人の心のわだかまりを解いていく)
納得すれば、病人は安心して薬を飲むことができる。
疑いのままに飲めば、効く薬も効かなくなる。
そのことを祖父は、誰よりもよく知っているのだった。
だからこそ、祖父はいつも指月にこう言っていた――
「中医学は民間から生まれたものだ。だからこそ、きちんと民へと還っていくべきものなんだ。もしおまえが本当にこの医の道を伝えたいのなら、学問の言葉ではなく、人々の暮らしに寄り添った言葉で話すんだ。誰にでも伝わるように。誰でも納得できるように」
そうすれば、中医学はむずかしいものではなくなり、人々は自然と心を開き、信じ、受け入れてくれる。
そして、いつか――その知恵の恩恵に、自ら気づく日が来る。
荊防散を一服飲み終えたその日――
彼は長らく手放せなかった頭巾を外し、そっと額に触れた。
じんわりと汗がにじんでいる。
鼻の通りはすっきりし、頭の痛みも消えていた。
体にまとわりついていたような風の寒気や、節々のだるさ、筋肉の痛みまで、まるで霧が晴れるように消えていった。
「証は表にあり。まずは表を解くべし」――
その言葉どおり、表証を解いた途端、まるで身体全体が羽根のように軽くなったのであった。
指月はノートを開き、今日の学びを書き留めた――
感冒において、風を怕れ、寒さを嫌い、汗がうまく出ず、全身が痛むような「外感表証」のとき、麻黄や桂枝といった辛温の重い発散薬では力が強すぎ、金銀花や連翹といった辛涼の軽薬では、かえって冷やしすぎる場合がある。そんなときにこそ、用いるべきは荊芥と防風――すなわち「荊防散」。これは辛温発散の中でも、もっとも穏やかで効果的な組み合わせである。荊芥は汗を発し、寒を散らす力が強く、防風は風邪を祓う力がある。このふたつが合わされば、汗孔がふわりと開き、風邪と寒邪はたちまち体表から追い出される。頭から足まで、すみずみまで調い、病はいつの間にか消えていく。
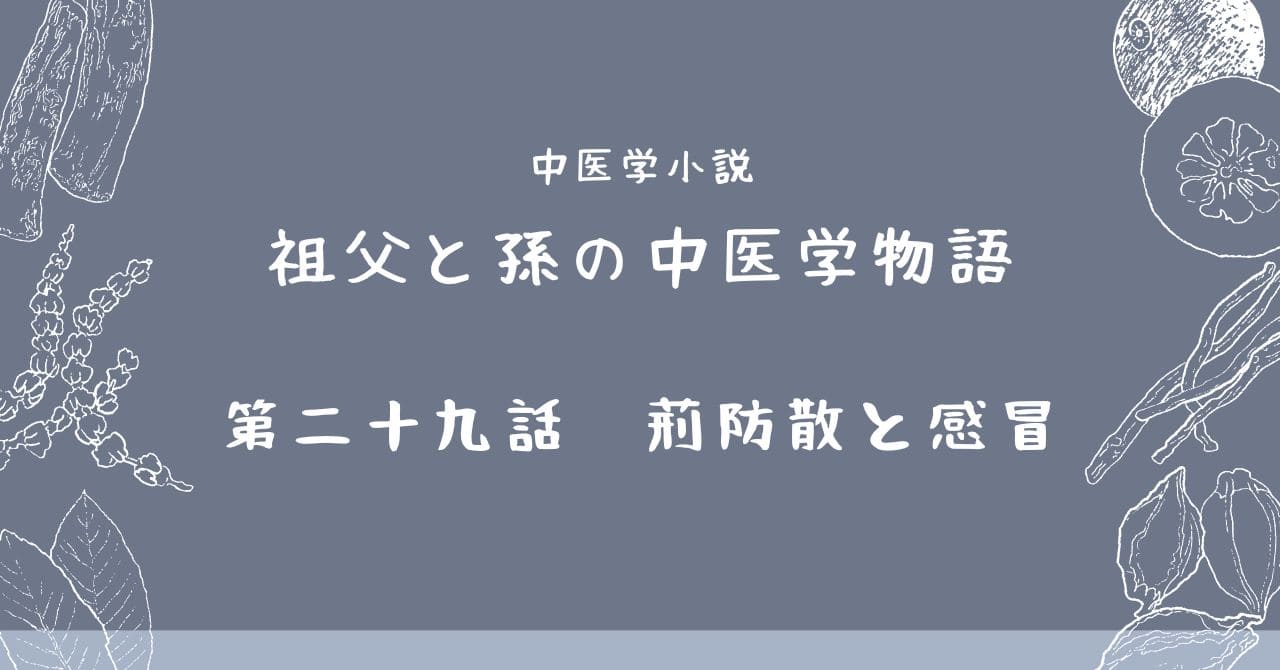


コメント