ある日、指月は釜戸に火をおこしてご飯を炊こうとしました。
ところが、火をつけたところ妙なことに気づきました。
煙が上に昇らず、外側に出てきたのです。
指月は煙を吸い込み咳き込んでしまいました。
指月は眉をひそめながら涙目で、祖父に尋ねました。
「今日の釜戸はどうしたんでしょう…ゴホッ!」
言い終わる前に、また激しく咳き込んでしまいました。
祖父は笑いながら言いました。
「梯子を持ってきなさい。煙突の上の瓦片を取り外せばいいんだよ」
「煙突の瓦礫?」
指月は祖父が何を考えているのか不思議に思いました。
(どうして煙突に瓦片をかぶせて、煙が出なくなるようにしたのか?)
(まるで地鼠(モグラ)を燻すよう、自分を煙まみれにしたのか?)
祖父がすることにはいつも何か意図がありました。
指月はそう考えると、咳のことは忘れ、興奮した様子で梯子を持ってきました。
屋根に上がり煙突の瓦片を取り去ると、再び火をつけてご飯を炊きました。
今度はきちんと煙突から煙が排出され、指月も煙にまみれることなく、ご飯は美味しく炊き上がりました。
指月は食事をしながら、さっきの出来事のことを考えていました。
(祖父は一体何をしたかったんだろう?)
すぐにでも質問したかったのに、壁に貼られた「食不語」(食事中は話さない)の三文字を見て、黙って食事を続けました。
祖父は指月が幼い頃から、「食事中は話さない」と徹底して教えてきました。
『食べる時は話さない、話す時は食べない』(吃飯不説話,説話不吃飯)
しゃべってしまったら、祖父は必ず箸で指月の頭を叩いて、その上に書かれた「食不語」の文字を見せるのです。
そのため、指月は「食不言」の習慣が身についていました。
やっと食事が終わると、祖父が口を開く前に、指月は祖父に尋ねました。
「祖父! なぜ煙突を瓦片で塞ぎ、私を咳き込ませたんですか?」
祖父は大笑いしました。
「指月よ。お前は昨日、麻黄、杏仁、甘草の三薬が、なぜ咳を止めるのか尋ねていたね。今日、私はすべて教えてあげたのだよ」
指月は昨日のことを思い出していました。
昨日、ある患者が再診にやってきました。
その患者はひどい咳をしていて、気温が下がると咳がさらに激しくなり、喘息を引き起こしていました。
その患者に、祖父は麻黄、杏仁、甘草の三薬だけを処方しました。
麻黄は蜂蜜と一緒に炙ったものでした。
指月は麻黄が宣肺平喘の特効薬であり、風寒の肺気壅遏(はいきようあつ)による喘咳の特効薬であることを知っていましたが、その仕組みはまだ理解していませんでした。*壅遏:ふさぐ、さえぎること。
指月は、表面的な薬物の効果だけでなく、その作用機序も知りたいと思っていました。
だから、祖父に質問していたのです。
なぜその患者は咳止め薬を飲むと、咳がさらにひどくなるのに、祖父の麻黄、杏仁、甘草の三薬を飲むと、すぐに咳が収まるのかが理解できませんでした。
そんな指月の心を見透かした祖父は、さらに言葉を付け加えました。
「咳止め薬は瓦片のように煙を押し下げるが、宣肺理肺の麻黄はお前が梯子を登って瓦片を取り去ったのと同じことをするんだ」
それはまさに目が覚めるような一言でした。
指月と祖父は一瞬止まったかと思うと、次の瞬間一緒に大笑いしました。
指月はようやく祖父の意図を理解しました。
風寒が毛孔を閉塞し、気機が内外で通じなくなっている状態は、瓦片が煙突の筒を塞いでしまい、煙や廃気が出てこれない状態と同じです。
部屋の中にいる人が煙にまみれて咳き込んでしまうように、気機が内外で通じなくなると肺気が失調し咳が生じるのです。
このような時は、肺を開放させます。
咳止め薬を飲むんで抑え込むのではなく、風寒を散らせば胸中の気機が一転し、咳は自然に治まるのです。
祖父は咳止め薬を使わずに、気機を通じさせることで咳を止める方法を教えてくれたのです。
「煙突は気管のようなもので、天地との気機を通じる役割を果たしているんだ。風寒や瓦片で閉塞されると、内外の通じがうまくいかなくなり、中にいる人は当然苦しくなる。咳が出るのは当然だよ」
「だから祖父は、その患者に『今後は扇風機の使用を控えなさい。風寒を避けるように』と言い聞かせたのですね」
「この患者は、夜に寝付けないからと、窓を開けたうえに扇風機をつけていた。一時の涼しさを求めたために、風寒に侵襲されたのだ。肌表が閉塞され肺気が壅遏したため、咳が止まらなかったのだ」
祖父はその患者に「座臥不当風(座っても寝ても風に当たらないこと)」という五文字を紙に書いて渡しました。
小指月はこの理屈を完全に理解しました。
祖父は無形の気である風寒が肌表を閉塞することを、有形の物質である瓦片が煙突を塞ぐという比喩で示してくれました。
祖父はこの日常の現象を通じて、医学の道という名月(真理)を指し示そうとしていたのです。
もし煙突が指であるならば、医道の真理はこの指を通じて指し示されるのです。
これこそが、祖父がこの小さな弟子に「指月」と名付けた理由なのです。
「指月」とは、指がなければ月を見ることができないということ。
つまり、「指の役割は、観る者を正しい方向へ導くことであり、最終的には本来の目標である『月(真理)』へと目を向けさせる」という深い意味を持っているのです。
つづく
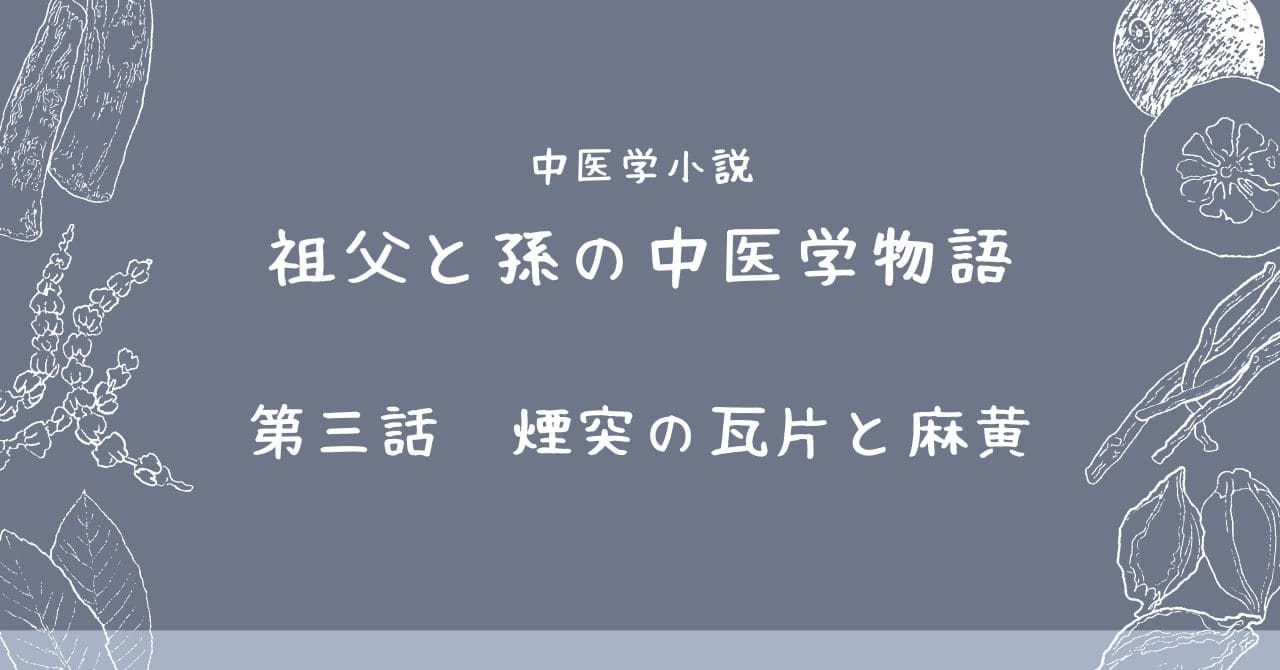


コメント