防風という薬は、外からの風邪を防ぐだけでなく、組み合わせ次第で、内からの津液の漏れ――すなわち「自汗」――を防ぐこともできるという。
一つの薬で、外から入るものを防ぎつつ、内から漏れるものも防ぐ。
まさに一石二鳥、双方向の調節である。
だが指月には、どうにも腑に落ちなかった。
(風を散じ、汗を出すはずの薬が、なぜ逆に、自汗を止められるのか?)
その日のこと、一人の幼い男の子が、母親に手を引かれて茅葺の家を訪れた。
顔色は蒼白く、体つきはややむくんでいて、どこか頼りない様子。
指月は一目見ただけで、その子の印象が脳裏に焼きついた。
祖父は脈をとる前に、男の子の母にたずねた。
「この子は夜になると、よく布団を蹴飛ばすんじゃないか?」
母親は目を見開いた。
「そうなんです! 毎晩のようにです!」
祖父はさらに重ねる。
「風邪をひきやすく、よく鼻をすすっている。そして食も細い――そうじゃないかな?」
「はい、はい、まったくその通りです……!」
母親は次々とうなずき、驚きを隠せない様子だった。
それもそのはずだ。
祖父はまだ脈も取らず、触診もせずに、まるで見透かしたように次々と言い当てたのだから。
指月も不思議そうに祖父を見る。
(なぜ、まだ診察にすら入っていないのに、さまざまなことを見抜けるのか)
祖父は、指月の疑問を見透かしたように、静かにこう語った。
「診断は脈をとる時から始まると思っているようだが、それは半分だけだよ。診察は、患者が扉を叩いたその瞬間から始まっている。歩き方、声の張り、目つき、息づかい――それらすべてに、その人の五臓六腑の虚実や、気血の通り、経絡の滞りが現れるんだよ」
「えっ、門を叩いたときから……?」
小指月は、思わず自分の胸を押さえてしまった。
自分は今まで、脈を取ってからが“医術”の始まりだと思い込んでいた。
だが、祖父はすでに、扉からノックの音がしたその瞬間から、患者を診察し始めていたのだ。
「たとえば」と、祖父は続けた。
「扉を叩く音がやたらに重いのは、気が過剰で火が盛んな証。逆に、扉をこっそり叩くような音なら、気が足りず寒がちな性質で、臆病。歩き方が重たく、足を引きずるようなら、気虚に加え湿がある。言葉に張りがなく、覇気のない者は、たいてい中気が足りていないことが多い」
指月は目を丸くした。
そんなことまでわかるのか――。
「子どもは、もともと脾が弱いもの。脾は四肢と筋肉をつかさどる。筋肉が締まりなく緩み、脂肪が下に垂れ、軽くたたくと揺れ動くような「虚胖」の子は、たいてい脾虚。だからこそ、四季の変わり目に風邪を引きやすくなるんだ」
その言葉に、指月の脳裏に『黄帝内経』の一節がよみがえった。
──「四季脾旺、不受邪(一年を通して脾胃がよく働けば、邪気に侵されない)」
祖父の診立てが、理論として頭の中にすっと繋がっていく感覚。
それが嬉しくて、指月は心の中でにんまり笑った。
これから祖父がどんな薬を使うのか――目を輝かせて見守るのだった。
母親が言った。
「この子は本当に風邪をひきやすくて……それに、日中はいつも汗がだらだら出て止まらないんです」
祖父は静かにうなずいた。
「邪の集まるところ、そこには必ず虚がある。正気が内にあれば、邪は入り込めないものだ」
そう言ってから、指月に振り返る。
「この子は脾と胃が弱く、肌の表面――腠理(そうり)がゆるんでいる。さて指月よ、どうして脾の弱い子どもは、まるで穴だらけの障子のように、外からの風邪を受けやすくなるのだろうか?」
指月は得意げに笑みを浮かべて答えた。
「この数日『難経』を読み返していて、ようやく腑に落ちました。あの書にはこうあります――『損其脾者,飲食不為肌膚』と。つまり、脾胃が傷めば、飲食からの栄養が肌や筋肉に行き渡らなくなります。そうなると、肌表の腠理に気血が満ちず、隙だらけになります。だから風が入りやすく、汗も外に漏れてしまうのです」
祖父は満足げにうなずいた。
「よろしい、ならばこの子に処す薬は?」
すると指月は迷いなく筆をとり、紙に三つの文字を書きつけた。
「防風、黄芪、白朮。この三つで“玉屏風散”ですね!」
それを聞いて、母親は眉をひそめた。
「先生、この薬は前にうちの子も飲んだことがあります」
どうやら、長患いで母親自身も薬に詳しくなっていたようで、疑いを解かないかぎり、この薬をもう一度使う気にはなれない様子だった。
祖父はにこやかに笑った。
「方剤を出すのはたやすいが、患者の疑念を解くのは難しい。だが難しいからといって、説明せずに済ませるわけにはいかない」
そう言ってから、祖父はゆっくりと尋ねた。
「以前に玉屏風散を飲んだとき、生姜水で服用したかな?」
母親は首を横に振った。
「いえ、お湯で煎じて、そのまま飲ませていました……」
「玉屏風散の力を最大限に引き出すには、生姜を薬の使い手として加えるのが妙なのだ。この方剤は、金元四大家の一人・朱丹溪が創ったもので、中に配されている黄耆は、気を補い、表を固め、衛気を強くしてくれる」
それを聞いて、指月はすぐに反応した。
「衛気は何をするものかというと――」
と、《黄帝内経》の条文をそらんじた。
「『衛気者,所以温分肉,充皮肤,肥腠理、司开阖者也』。衛気とは、筋肉を温め、皮膚を充実させ、腠理(そうり/皮膚の気孔)をふっくらと引き締め、開閉をつかさどるものである」
祖父はうなずいた。
「そのとおり。衛気は、身体を外から守る“気”であり、国でいえば万里の長城だ。それがしっかり張りめぐらされていれば、外からの風寒邪が入ってこられない。だが一度でも破れれば、身体はすぐに風邪に繰り返しやられる。黄耆という薬は、その破れかけた金の鐘のような鎧を、見事に修復してくれるのだ。しかも密で、風が通らぬほどに」
祖父は、子どもを見つめながら言った。
「この子は、長いあいだ食べ過ぎで育てられてきた。それで中焦――つまり脾胃が弱くなっている。営衛の気は、すべてこの中焦から生まれる。だから脾胃が傷めば、すぐに肌表の衛気も足りなくなって、風邪をひきやすくなる。これからは腹八分……いや、七分で育てることだ。そうすれば、薬を使わずとも、ゆっくり身体は元に戻っていくよ」
母親は、申し訳なさそうな表情を浮かべていた。
「うちの子には、いつも一番おいしいものを食べさせてきました。たまに食べすぎて吐くこともありましたけど、少しでも早く大きくなってほしくて……」
それを聞いた祖父は、母親の肩に優しく手を添えた。
「子を想う気持ちはわかる。あなたは良い母親なのだろう。でも、肥料をやりすぎれば、作物の根や芽を傷めるのと同じで、食べものも与えすぎれば子どもの脾胃を痛めてしまう。何度も風邪をひいたり、汗が止まらなかったりするのも、すべて普段の脾胃の養い方と関係しているんだよ。子どものうちは、親がしっかりと管理してあげないといけないよ」
その言葉が、まるで鐘の音のように母親の胸に響いた。
「子どもの養生には、七分目で満足する“七分飽勝調脾剤(腹七部は脾の調整剤に勝る)”という言葉がある。“小児安からんと欲すれば、三分の飢と寒をもってせよ”という言葉もある。過食は必ず脾胃を損じる。脾胃が弱れば、風邪などの邪気がすぐさま身体に入ってきてしまう。子どものあらゆる病は、まず脾胃を守ることが、最も確かな近道なんだよ」
そう言いながら、祖父はそっと子どもの頭を撫でた。
そして、母親に伝えた。
「玉屏風散は、生姜水で服用しなさい。そして、食事は常に“七分目”を守ること」
一か月後、あの虚胖だった子どもの身体はすっきりと引き締まり、自汗もぴたりと止まっていた。
そればかりか、たびたび風邪をひいていた体質までもが改善され、風邪知らずの元気な子になっていた。
指月は喜びを感じ、ノートにこう書き記した。
玉屏風散は、固表止汗の良方なり。その中に含まれる防風と黄耆は、まるで肌表に“金鐘”のような防護を張る役割を持ち、白朮は脾虚を補って整える。まさに“脾常不足”の小児が、外からの風寒に晒されたときの頼れるお守りとなる。生姜水で服用させるのは、先ず生姜の発散力で寒邪を外へ追いやり、その後、玉屏風散で身体を覆う衛気の壁を修復するため。つまり、先に邪を払い、その後で城壁を築き直すという理法だ。ただし、服薬だけでは不十分。「腹七分目」という食養生を守らねば、どれほど名方を使おうと効果は半減してしまう。これこそが、なぜ同じ玉屏風散を使っても、多くの人が満足な効果を得られないのに、祖父だけが安定した効果を出せる理由である。
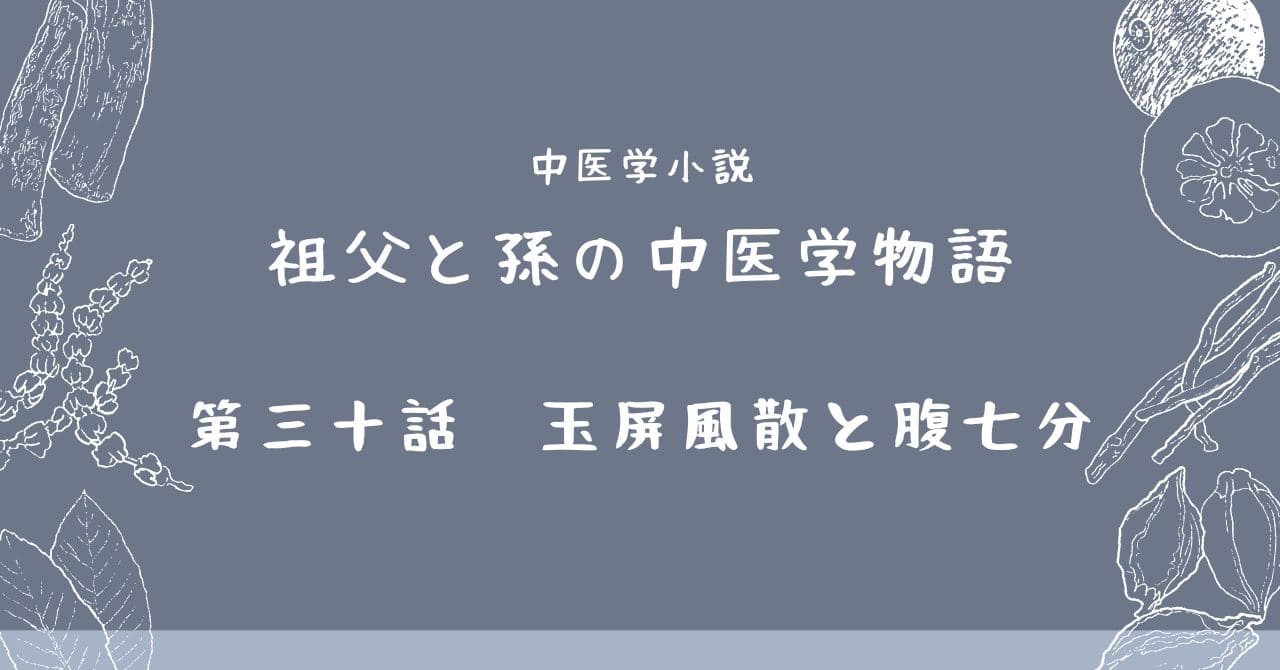


コメント