ある夏のこと。
屈強な身体が自慢なひとりの農夫が、冷たい瓜や果物を好んで食べていた。
暑さも手伝い、毎日のように冷たいものを摂っていたところ、ある日とうとう腹を下し、十数回もトイレに駆け込むことになった。
まさに「どんな豪傑も、三度の下痢には敵わぬ」である。
下痢が止まらず、ついには肛門まで脱垂し、屈強だった姿は見る影もなく、まるで空気の抜けた風船のように床に伏して動けなくなった。
起き上がることすらままならず、まさに「病が来れば、まるで山が崩れるように倒れる」とはこのことだった。
家族はあわてて医者を呼んだ。
家中ではあちこちの医者を呼び、あれこれと手を尽くしていた。
ある医者は「通因通用」と称して、苦寒の薬で下し、またある医者は、下痢を止めようと炭薬で収斂させようとした。
それでも、十日あまり治療してみても、いっこうに回復せず、かえって身体はどんどん衰えていった。
今では、たとえ粥をひと口すすっただけでもすぐに下してしまうほどだった。
さすがにこれはいけないと、ついに茅葺の家まで足を運び、祖父と指月に助けを請うこととなった。
祖父は指月に、まず脈を診るように言った。
指月が脈を取ると、首をかしげた。
「……祖父、この脈が沈んでて、浮かび上がってきません」
祖父はにこりと笑いながら答えた。
「空気が抜けたボールと同じだよ。弾ませようとしても、弾まないだろう?」
その言葉を聞いて、家族は青ざめた。
「先生、この子が倒れれば我が家が崩れてしまう……うちの大事な働き手なんです。どうか……どうか助けてください!」
祖父は静かにうなずいた。
「そうとも。家族のためにも、倒れてはならない。だが彼は、長期にわたり生ものや冷たい果物を好んで食べてきた。その冷えが脾の陽気を傷つけたのだ。脾は湿をつかさどる。脾陽が損なわれれば、清気は昇らず、湿気は下に沈む。こうして湿が下焦に停滞し、腸胃に影響して、止まらぬ下痢を引き起こすんだ。今、必要なのは――陽気を上げて湿を取り除くことだ」
指月はすぐに反応した。
「そうか! 『黄帝内経』には、“清気が下にあると飧泄を生じる。湿が盛んであれば濡泄となる”とあります……つまり、昇るべき清気が下がっているから、上げてあげればいいんですね!」
祖父はにっこり笑って尋ねた。
「では、清気を昇らせ、下陥した脈勢を持ち上げるには、どんな方剤が良いかな?」
指月の顔が輝く。
「中気不足、内臓下垂、清気が昇らぬときは――『補中益気湯』です!」
祖父は満足そうにうなずいた。
「そう、そして――もう一味、“防風”を加えるんだ。そうすれば、清陽が上竅から出て、清濁は交わらず、中気が養われ、泄瀉も止まるよ」
その場ですぐに煎じ、農夫に飲ませると、なんとすぐに下痢が止まり、食欲が湧いてきた。
その後、三服を飲み終えるころには、農夫は再び畑に出られるようになっていた。
家に戻ってから、指月は祖父に尋ねた。
「どうして前に診た医者たちの処方は効かなかったのでしょうか?」
祖父は茶をすする手を止めて答えた。
「病が治らないのは、病が難しいからではない。薬が証に合っていないだけだよ。では、薬が証に合わないのはなぜか? それは、書を読んでいないからだ。“病治せざるは、皆読書の少なきに由る”――とは、偉大な先人の言葉だね。たとえば、吳鞠通は『補中益気湯』に防風を加え、清陽を昇らせて下痢を止めた。孫一奎も『蒼術防風湯』で防風を用いて脾陽を昇らせ、同じく泄瀉を治した。つまり、防風は単なる祛風薬ではなく、脾陽を上げるという重要な力も持っているんだよ」
指月は目を輝かせ、納得の表情を浮かべた。
(やっぱり祖父はすごい。防風を加えるのにも、ちゃんと古籍の裏付けがあったんだ……)
指月は、さっそくノートにこう書き記した。
脈勢が下陥し、泄瀉が止まらないときは、昇陽除湿が最も効果がある。
『補中益気湯』に防風を加えるべし。古書に妙方あり――
“清気を昇じ、濁気を降ろす”こそ、中気を補い、泄を止める鍵である。
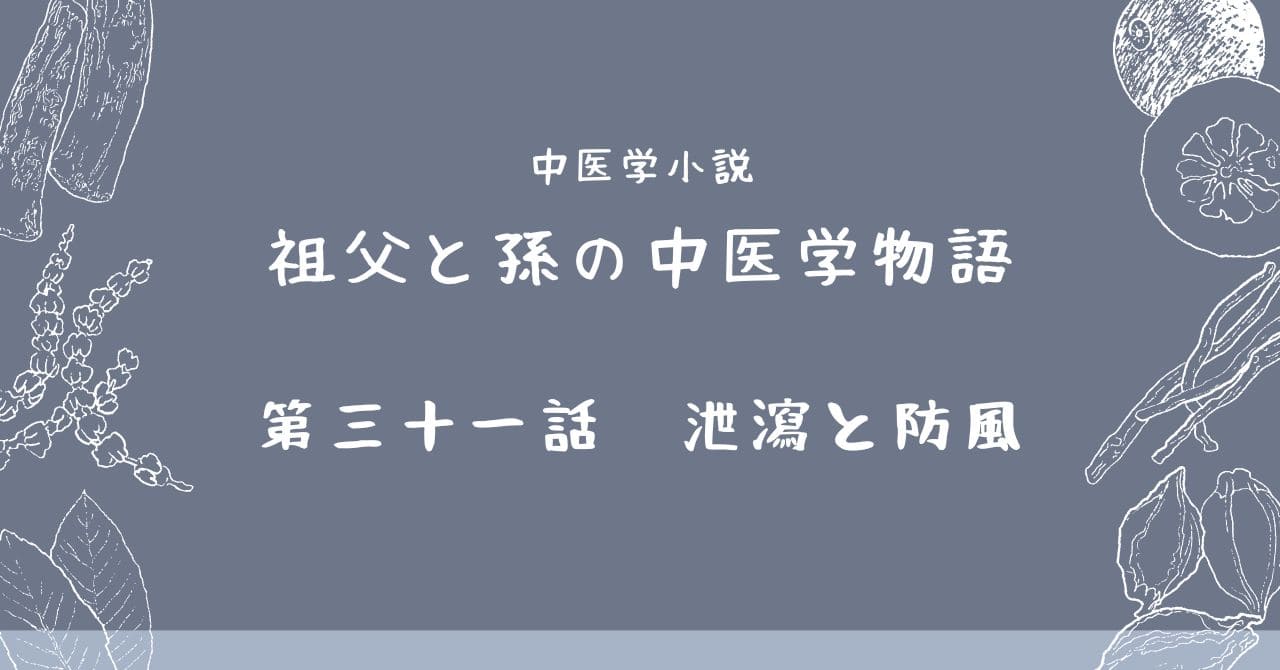


コメント