祖父と指月は、今日も薬籠を背に山へ薬草を採りに出かけていた。
途中、向こうからひとりの農夫が手を振りながら叫んだ。
「先生、どうか足を止めてください!」
二人が立ち止まると、その農夫は汗を拭いながら駆け寄ってきた。
息も絶え絶えで、しばらく肩で息をしていたが、ようやく口を開いた。
「先生、うちの年寄りが半月前に中風で倒れまして、ずっと床に伏せているのです。それからというもの、一度も大便が出ず、食欲もなく……。診てくれた医者たちは口をそろえて“このままでは命に関わる”といいました。潤腸丸を何度も飲ませたのですが、腸がまるで動かないんです。もしかしたら腸まで中風で麻痺してしまったのではないかと……」
そう言って農夫は不安げにうつむいた。
祖父は話を聞くと何も言わず、静かに竹杖を前に突き出して道を示した。
「案内しておくれ、すぐに見に行こう」
そう言うと二人は農夫とともに歩き出した。
薄暗い寝室の中、一枚の薄い布団をかぶった老人が、身動きもできず横たわっていた。
時おり呻き声を漏らしながら、虚ろな目で天井を見つめている。
その部屋には家族が大勢集まっていたが、誰ひとりとして心安らぐ者はなく、ため息ばかりがこぼれ落ちていた。
医者には何人も診せたが、回復の兆しは一向に見えず、「もう覚悟するしかないのでは」と誰もが心の中で思っていた。
指月は、こうした場面に何度も立ち会ってきた。
ふと『大医精誠』にある一節が脳裏に浮かぶ。
――「病人がひとり家の一隅にひっそりと臥し、家中すべてがうつうつとして楽しまずにいる」
たった一人が病に伏すことで、家族全員の笑顔が失われ、食事でも箸が進まなくなる。
病とは、患者ひとりだけのものではない。
家という場すべてが、その痛みに飲み込まれるのだ。
ゆえにこそ、医者が治すべきは“ひとりの病”ではない。
その背後にある“ひとつの家”をも癒やすことにあるのだ――
指月が脈を取り終えると、首をひねりながら呟いた。
「おかしいな……中風を患ったあとなのに、脈にまだ力がある。まるで何かの気が、突き上げようとして止まっているような感じだ」
祖父は、近くにいた家族にたずねた。
「この数日、大小便はどうだった?」
家族の一人が答えた。
「小便は、ほんの少ししか出ていません。なにせ食べ物もあまり口にしておらず……。大便にいたっては、中風以来、まったく出ていないんです」
それを聞いた祖父は、指月に目を向けて言った。
「指月よ、“急則治其標”、いま一番急を要するのは何だ?」
指月はしばし考え込みながら答えた。
「『黄帝内経』に曰く“小大不利は、まさにその標を治すべし”とあります。いま一番急を要するのは、大小便が出ないことです!」
すると家族の一人が訴えるように続けた。
「でも、こんなにたくさんの便通の薬を飲ませたのに、一向に効かないんですよ……」
指月は渡された薬方を見た。
そこには、火麻仁、当帰、白芍、杏仁、郁李仁、松子仁など、いずれも滋陰養血・潤腸通便の薬ばかりが並んでいた。
祖父はしばらく考え、やがてゆっくりとこう言った。
「これは、脈気が詰まって滞っている。気の流れをまず通さねばなるまい。いまは清と濁の区別がつかず、体の中で停滞している。おならひとつ出ず、食べた物すら満足に運べない。こういう状態では、潤す薬では通じない」
そう言うと祖父は、常道をあえて外れた処方を示した。
――防風、枳殻、甘草の三味。
「この三味を粉にして、白湯や米湯で一服につき二銭(約7.5g)を服ませなさい」
その日の午後、家族は言われたとおり薬を用意し、粉にして患者に服用させた。
するとすぐに、腹の中で何かが動き出したように「ぐるぐる」と音を立て始めた。
しばらくして、強烈なおならが一発――。
そして次の瞬間、寝たきりの老人は、言葉を発する間もなく、まるで矢が放たれたかのように、大便を一気に漏らした。
布団も寝間着も、たちまち汚れ、部屋にいた者たちは驚くしかなかった。
だが不思議なことに――
その一便をきっかけに、食欲が戻ってきたのか、夜にはお粥を一碗平らげ、そのままぐっすりと眠りについた。
そして翌朝、目覚めた老人は、これまでの呻き声が嘘のように静かになり、自らの言葉で家族に話しかけたのだった。
意識ははっきりし、顔にも少しばかり血色が戻っていた。
さすがにまだ床を離れることはできなかったが、さらに数日、体を整える薬を服んだあとは、杖を使ってゆっくりと歩けるまでに回復した。
あのとき家族はすでに死を覚悟していたのだ。
だが、まさに黄泉の入り口から引き返してきたこの命は、その後も数年、穏やかに生き永らえることとなった。
その様子を見ていた指月が、ぽつりと疑問を漏らした。
「祖父……どうして下剤も使わず、腸を潤す薬も使わなかったのに、どうしてあんなにスムーズに便が出たのでしょうか?」
祖父はにっこりと笑みを浮かべて答えた。
「病を治すには、まず“気”を整えることだ。その次に、各々の症状に向き合うのが本道だよ。これは《此事難知》にも書かれている大切な教えだ。見た目には中風で便秘しているようでも、真に見るべきは脈の状態。気が詰まって流れず、上下が通じていない。清と濁が混じり、出口も入り口も閉ざされていた。だからこそ、防風で清陽を上げ、枳殻で濁陰を降ろし、そして甘草で全体を調和させる。気が巡れば、すぐに放屁し、大便も下りる。治療とは、そういうものだよ」
その言葉に、指月はただただうなずくばかりだった。
祖父は『簡便単方』という古書を棚から取り出し、指月に手渡した。
指月はそれを一目見るなり、ぱんっと額を叩いて笑った。
「なるほど、病が治らないのは、勉強不足ゆえですね。祖父の治療は、みんな古書に書かれた道理に基づいていたのですね!」
『簡便単方』には、こう書かれていた。
「風を消し、気を巡らす。老人の大腸が詰まる秘結には、防風・枳殻を各一両、炒ってから、甘草半両を加えて粉末とし、白湯にて二銭ずつ服用せよ」
さらに指月は他の古書も引っ張り出して読み漁り、防風と枳実(枳殻)の組み合わせが便通を促す妙薬であることを、いくつも確認した。
防風が清陽を上げ、枳殻が濁陰を下ろす――。
このふたつの薬がまさに「昇清降濁」の絶妙なコンビであることに、深く納得した。
指月はさっそく、ノートにこう書き記した。
『太平聖恵方』の「搜風順気丸」は、防風で脾の清気を上げ、枳殻と大黄を配して腸をひろげ気を巡らせる。中風によって起こる風秘・気秘には、清陽を昇らせ濁陰を降ろすことで、快方へと導く――
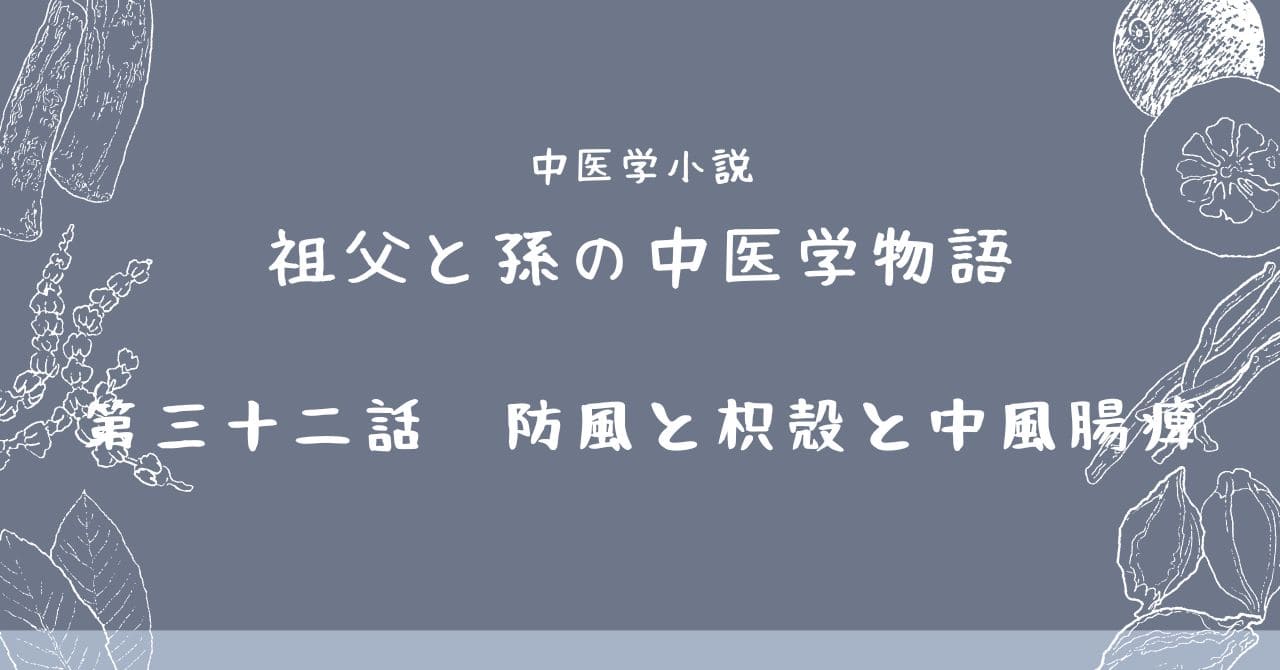


コメント