小児の口内炎には、肚臍への外用療法がよく効く。
なぜなら、小さな子どもは「純陽の体」であり、身体が通透していて、肌表から薬を吸収しやすいからだ。
細辛のような極めて辛い薬は、その性質上、どこにでも届き、すぐに効果が現れる。
では、大人のひどい口内炎にはどうすればよいのだろうか?
ある日、一人の中年男性がやってきた。
口の中はひどくただれ、激しい痛みで口すら開けられず、食事もままならないという。
祖父は、病状にはすぐに触れず、ゆったりとした口調で尋ねた。
「普段、よく食べているものは?」
「酒が好きで、よく油で炒ったピーナッツをつまみに飲みます。毎日、それが楽しみでして」
祖父は指月に脈を診るよう促した。
「脈はどうだい?」
「脈は沈んでいて速いです。鬱熱があるようです」
祖父は男に向かい、尋ねた。
「あなたの臓腑にはかなりの熱がこもっているようだ。便通もよくないだろう?」
男は苦笑いしながらうなずいた。
「ええ、よく2〜3日出ないこともありますし、出てもスッキリしない感じです」
「毎日、酒と揚げ物、油っこいものばかり食べていたら、腸に油がまとわりついて動かなくなるのは当然だ。野菜を摂らないのも原因の一つ。飲酒の習慣がある方は、野菜を避けがちだからね」
男は「なるほど、だから口内炎が治ってもまたすぐにできるのか……」とつぶやいた。
祖父は笑いながら言った。
「そういうことだ。今後はお酒を控えて、食事には野菜を多く取り入れなさい。脂っこいものは減らし、食生活を見直せば、自然と治っていくよ」
男はしきりにうなずいていた。
頭ではわかっていても、習慣を断ち切るのは難しいものだ。
自分の悪癖をわかっていながら、ついつい繰り返してしまうのが人間というもの……。
祖父は指月に問いかけた。
「こういった、寒熱が入り混じった口内炎や歯茎の腫れには、どんな薬を使うべきだろう?」
指月はすぐに答えた。
「寒温を併用すべきです。《本草綱目》にある兼金散――細辛と黄連の組み合わせが良いと思います」
祖父は満足そうにうなずいた。
「その通りだ。細辛は昇散の性質を持ち、行き届かぬ場所はない。風を祛い、痛みを止め、内にこもった火を発散させ、黄連を導き、まっすぐ患部へと届けてくれる。あらゆる痛みや痒み、瘡(ただれ)は、心に属するものだ。黄連は心経の熱火を清め、毒を下へと降ろすことで、炎症を抑えてくれる。この二味の薬だけで、十分だよ」
「用量はどうしますか?」
「基本は等分で粉末にする。ただし、寒痛が強ければ細辛を多めに、熱痛が強ければ黄連を多めに調整すればよい。そうすれば、歯茎の腫れでも、口内炎でも、あらゆる口腔の痛みに応用できる」
その後、男は言われた通りに酒と油ものを控え、処方された兼金散を服用した。
三回ほど飲んだだけで、あれほどの口内炎はみるみる引いていき、さらに二剤飲み終えるころには潰瘍も完全に治ってしまった。
実は、指月は男のために兼金散を二種類用意していた。
ひとつは粉にせず、煎じ薬として内服する分。
もうひとつは、兼金散を細かく粉末にし、蜂蜜で練って患部に直接塗る外用薬として調えたもの。
黄連と細辛――一つは苦寒でありながらまっすぐに炎を折る力を持ち、もう一つは辛温にして、肌の表層からこもった熱を吹き散らす。
寒と熱、内と外。
まさに陰陽相済の理がそこにあった。
内外から同時に効かせることで、鬱熱を解き放ち、熱と痛みを治したのだ。
指月は『本草綱目』を開き、兼金散の項目をノート書き写した。
兼金散:黄連と細辛の配合による妙薬。
専ら口内炎や歯茎の腫れ、疼痛に効く。
李時珍曰く:
「此の二薬、一は冷、一は熱。一は陰、一は陽。寒に熱を以て用い、熱に寒を以て治す。君臣相佐し、陰陽相済す。まさに制方の妙を得たり。故に功ありて偏勝の害なし」
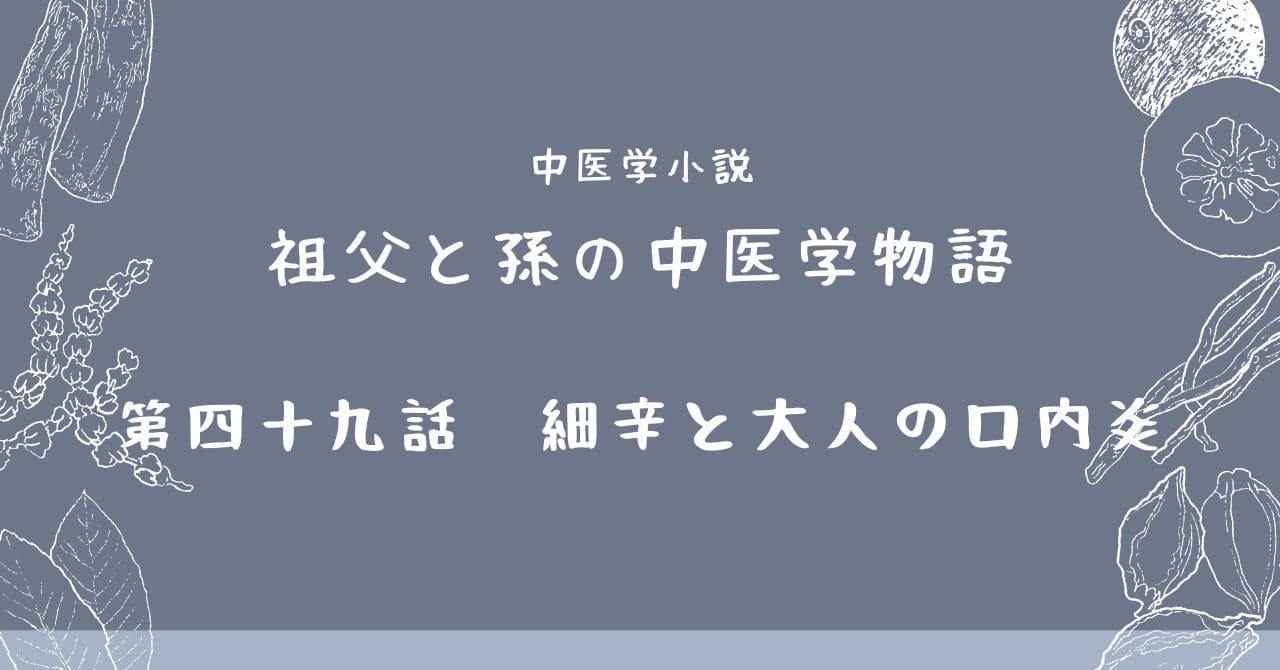


コメント