『攻城を恐れず、書を読むことを恐れず』
これは、祖父が指月に古書を読み聞かせる際に最もよく使う言葉です。
『攻城を恐れず、書を読むことを恐れず(攻城不怕堅,攻書莫畏難)』
中国の諺で、城を攻め落とす際に困難を恐れてはならないのと同様に、知識を学ぶ際にも困難を恐れてはならないという意味です。
指月は読書をしながら、眠気を感じていました。
ウトウトしていると突然、芳しいお茶の香りが漂ってきて、指月は目が覚めました。
「またうたた寝していたのか? 医聖(張仲景)や薬王(孫思邈)に会ったかい?」
祖父は笑いながら、机の上で彼が最も好きな功夫茶を淹れていました。
指月は伸びをして、ぼんやりとした目をこすると、祖父に向かって言いました。
「医聖や薬王には出会えず、目にするのはただの麻黄や杏仁ばかりです」
最近、祖父が麻黄湯を使って風寒頭痛を治し、肺鬱咳嗽を治し、さらには抑うつ症を治していました。
昨日は麻黄湯を使って利尿させ、水腫を治療しましたが、指月はその仕組みがまだ理解できていなかったのです。
「お前はまだあの漁師のことを考えているのか?」
「その通りです!」
その漁師は先日、雨の中で漁をしていました。
なかなか魚が捕れず、その間ずっと雨で濡れ続けました。
やっとの思いで少し捕れたので漁をやめました。
ところが彼は、全身が濡れていているのに服を替えず、そのまま市場に魚を持って行ったのです。
売り終えて家に戻ると体に異変を感じました。
小便が出ず、汗も出ず、全身寒気に襲われたのです。
(風邪か? 今日は早く寝よう。明日には治るだろう……)
漁師は早めに布団に入り眠りにつきました。
次の日、尿意を感じてトイレに行っても小便があまり出ませんでした。
下腹部が張ってきて、その後、徐々に手足が腫れてきました。
漁師は怖くなり、茅葺き屋根の家にやってきたのです。
指月は腫れた漁師の姿を見て、驚きました。
これほど腫れた体を見たことがなかったのです。
手首も腫れていたので正確な脈がとりづらい状態でした。
(この患者を祖父はどうやって治療するのだろう?)
指月は片時も祖父から目を離さないで治療を見続けました。
(漁師が治ったのは良かったけど、どういう理屈だったんだろう……)
指月は漁師の水腫の症例を思い出しながら、急須を持ち上げて、自分の茶碗にお茶を注ごうとしました。
ところが、お茶が一滴も出てきませんでした。
「ぼうっとしながら注ぐのは危ないからやめなさい。それに、それではお茶は出てこないよ」
「え?」
指月は空気穴を押さえていたことに気がついていませんでした。
当然、何度急須を傾けてもお茶は出てきませんでした。
(どうして? お茶を注げないないなんておかしいよ)
指月は、まだ自分は夢の中にいるのではと思いました。
でも、これは明らかに現実でした。
小指月は夢から覚めて、喉が乾いているのにお茶が飲めません。
(せっかく祖父がお茶を淹れてくれたのに、どうしてお茶を注げないんだ?)
指月は漁師のことをすっかり忘れていました。
祖父に「何故?」という表情を向けました。
「急須の中のお茶がなぜ下に流れ出ないと思う?」
指月は戸惑いました。
祖父は笑いながら、急須の空気穴を押さえていた指月の指を掴むと、少しずらして空気穴を開放しました。
すると、急須の注ぎ口からお茶が出てきて、茶碗がお茶で満たされました。
「空気穴を塞いでいたのか……気がつかなかった」
「考え事をしていると、簡単なことでもできなくなることがあるんだよ」
指月は反省すると同時に、疑問を感じました。
(そういえば、どうして空気穴を塞ぐとお茶が出てこなくなるんだろう?)
指月はこれまでこの現象を深く考えたことがありませんでした。
祖父の提壺揭蓋(ていこけいがい)の動作を見て、指月は何かを理解したように感じました。
しかし、完全な理解までは、まだ薄い壁で隔てられているような気がしていました。
提壺揭蓋は、急須を傾けて蓋を外すことを指します。急須の場合、空気穴を開けることと蓋を外すことは同じ意味になります。
指月はこの疑問を問題を解決する必要がありました。
この疑問すら解決できなければ、他の多くの道理が理解できるわけがないと感じたのです。
祖父はいつも指月に「散々考えても解決できない場合は、別の方法を考える必要がある」と言っていました。
問題に行き詰まった時、無理やり解決しようとせず、別の方法を考えることで、一気に解決できることがあります。
日常生活の些細な現象から、重大な疑問が解消されることがあるのです。
「この急須の蓋は人体の肺蓋のようなもだ。肺は五臓の華蓋であり、急須から出るお茶は人の膀胱や尿道からでる尿のようなものだ。もし、急須の空気穴を押さえて閉塞させると、お茶は下に流れない。一方、押さえていた指を少し緩めて開放すると、お茶は次々と流れ出す」
指月は、うんうんと肯きました。
「中医学では、肺は水の上源である。先日の漁師は、長時間に渡って水に浸かり、雨に打たれていた。そうすると、肺が主る皮毛が風寒湿により閉塞される。寒気を感じ、脈が浮いて緊張する。風寒湿が皮毛閉塞させると、その影響は肺に及ぶ。その結果、急須の蓋の空気穴が押さえられるとお茶がでなくなるように、人間では尿が出なくなってしまう。小便が排出されないと、体内の水分が滞り、腫れてしまうのだ」
指月は、急須でお茶を注ぐことと、人間の排尿に共通の機序があることに驚いた。
「麻黄湯を使って肺気を宣通することで、空気穴を開放するんだ。肺を開放し尿が排出されるようにするのだよ。これが古人が言う『提壺揭蓋法』である。これにより利水され、水腫も解消されるのだ」
「分かりました! 分かりました! 祖父が漁師に麻黄湯を一回分だけ処方したのは、こういった理由からだったのですね。専用の利尿薬を使うのではなく、風寒を解表し、尿が出るようにして水腫を解消したのですね」
祖父はその通りと肯いきました。
「私は最初、どうすれば利尿・消腫に効果的な薬を選べるかばかり考えていました。しかし、いくら考えても、『肺は水の上源である』という古典の言葉には思い至りませんでした。実際には、肺気が開くことでこそ、水道が調整され、膀胱へ水を送ることができるのです。つまり、単に利尿作用のある薬を考えるのではなく、まず肺気を通じさせることが重要だったのです」
指月は理屈が理解できて、ようやく気が晴れました。
そして、祖父と一緒に智恵の茶をゆっくりと味わいました。
第五話 提壺揭蓋法 完
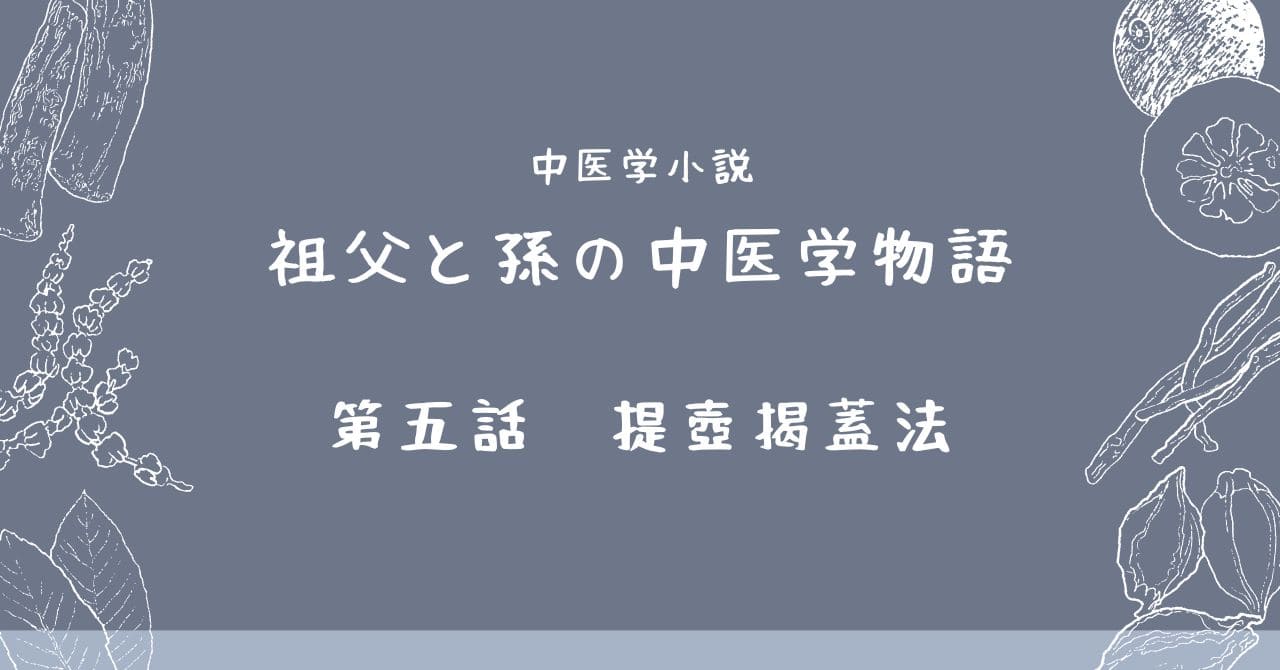
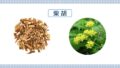

コメント