ある村の医者が、祖父の処方箋を手にして、茅葺の家にやってきた。
「私は病気を診てもらいに来たのではありません。先生に教えを請いに来たのです」
祖父は、「教えなどと恐れ多いこと。遠慮なく話しなさい」と、穏やかに言った。
医者は、指月が書いた処方箋を取り出し、それを見ながら尋ねた。
「以前、子宮筋腫の女性を診察されたと思いますが、覚えていますでしょうか? 私は桂枝茯苓丸を使ったのですが、あまり効果がありませんでした。なのに、なぜ先生が処方した桂枝茯苓丸はよく効いたのでしょうか?」
指月が処方箋を見ると、医者に言った。
「この処方には、桂枝茯苓丸に藁本が加えられています」
医者は驚いて尋ねた。
「藁本に筋腫を治す作用があるのですか? 活血化瘀、つまり血行を促進して腫瘍を消す作用が?」
祖父は首を横に振った。
医者はなおも問い続けた。
「私は三稜や莪朮(がじゅつ)といった瘀血を破る強い薬を使っても効かなかったのに、先生は風薬である藁本を使って効かせました。どうしてですか? 私はてっきり腫瘍には攻めて壊す方法が第一だと思っていたのですが……」
祖父は静かに答えた。
「痛みを止めるのに、必ずしも活血薬が必要なわけではない。腫瘍を消すのにも、必ずしも攻撃的な薬が必要なわけではないんだ」
医者は「瘀血を攻めることが腫瘍治療の基本」と思い込んでいた。
なぜ子宮筋腫に藁本を使うのか、理解できなかった。
その時、指月は『神農本草経』を開いて、藁本の記述を指し示した。
「藁本は“婦人の疝瘕(せんか)・陰中の寒腫と痛み・腹痛・頭風痛を治す”とあります。」
医者は納得しかけたが、なおも問いた。
「頭風痛を治すのは分かります。頭の頂上の痛みには藁本が良いと聞きます。でも、なぜ子宮のような下腹部に効くのですか? 藁本は上へ昇る薬じゃありませんか?」
祖父は医者に問い返した。
「その女性は、スカートをはき、オフィスで足元にエアコンの冷風を受け、冷たい飲み物や果物をよく口にしていたのでは?」
医者はハッっと驚いて、静かにうなずいた。
祖父はさらに問い続けた。
「女性の脈を取った時、やや浮いていて緊張があり、普段から風にあたるのを嫌がり、頭痛を起こしやすい様子はなかったかな?」
田舎医者は、またうなずいた。
祖父は続けた。
「子宮筋腫は、どうしてできると思う?」
指月が『黄帝内経』の一節を引いて、医者の代わりに答えた。
「“積の生ずるところは、寒によって生ず”とあります。」
「寒邪がどの経絡を傷つけると、表から裏へと進んで、腫瘤を生じやすいかな?」
医者は答えた。
「子宮は“胞宮”といい、腎に属します。腎と表裏の関係にあるのは膀胱です。つまり、寒邪が膀胱経に侵入すると、腎の気化作用がうまくいかず、停滞が起こって腫瘤が生じるのだと思います」
祖父はにこりと笑って言った。
「その答えが、まさに真相なのですよ」
けれど、医者はまだ首をかしげたまま釈然としない様子だった。
祖父はゆっくりと話しを続けた。
「藁本という名の通り、この薬草は身体の最も高い“巓頂”にまで達することができる。つまり膀胱経によく入る。足太陽膀胱経は表を主る経脈だ。そして子宮は裏の臓。スカートを穿いた状態で、オフィスで冷房が足元に当たり、腰から下が冷えていく。すると、寒さは下から上へと毛竅を引き締め血脈を収縮させていく。そこへ、冷たい飲み物や果物が加わると、今度は上から下へ寒が降りてくる。下腹部でこれらが合わさると、下腹部に集中した寒邪によって子宮が収縮し、血が滞って瘀血となる。だから、活血化瘀で既にできた腫瘤を治すのは、“病すでに成りしを治す”ことだ。一方で、太陽経の表寒を散じ、生冷を断ち、冷房とスカートをやめるのは、“病いまだ生じざるを治す”ことにあたる。治療とは、すでにできたものを消すのはもちろんだか、これからできるものを防ぐことが要なんだよ」
医者は、話を聞いていて目から鱗が落ちたようだった。
「先生、本当にお見事です。私は、ただ腫瘤を瘀血と見なし、攻めて砕こうとしていましたが、その瘀血の背景にある“寒”の存在をまったく見落としていました。寒が気血を収縮させてどんどん腫瘤を生じさせる以上、いくら攻めても追いつくはずがありませんでした!」
祖父はにこやかにうなずいた。
「それが理解できれば、もう藁本にこだわる必要はないよ。たとえば太陽経の風薬である羌活や独活も効果がある。だから、『神農本草経』には“独活は風寒を撃つを主とし、女子の疝瘕を治す”と書かれている。子宮筋腫や疝瘕が、どうして風寒と関係あるのか? 人は瘤ができれば、そればかりを見てしまう。だが瘤の背後にある真の原因を考える人は少ない。古典には、そうした“風寒”と“疝瘕”の密接な関係が、実に素直に書かれている。だからこそ風薬を使えば、劇的な効果を生むことがある。膀胱経の表面の寒邪が散じれば、子宮に滞った気もすんなりと流れ始めるんだ。あなたは“諸症、まず表を解すべし”という言葉を知っているかな? 『傷寒論』に出てくる多くの名方は、単に外感病だけでなく、あらゆる難治性疾患にも応用できる。今の人が中医をうまく使いこなせない理由は、こうした素朴で根本的な中医の思考から離れてしまったからなんだ」
指月は話を聞きながら、何度もうなずいていた。
(なるほど……だから祖父は、藁本で子宮筋腫や腹中の冷えによる痛みを治すのか)
婦人が常に風にあたって頭痛を訴えていたのは、太陽膀胱経の気化がうまくいっていなかったためだった。その結果、水湿が体内に停滞し、積聚となっていたのだ。
このような病には、病巣そのものにとらわれず、気化機能に着目して治すことが肝要。腫瘤を攻めるのではなく、寒を散らすことで、足の太陽膀胱経を通じて寒邪を外へと散じさせれば、経脈は自然と開いてゆるみ、脈象の「浮緊」もすっと消えていく。そうなれば、瘀血も自然と排出されやすくなり、腹中の痛みもあっという間に消えてしまう。
田舎医者は深くうなずき、こう言った。
「これからはもっと先生に養生の術を学ばなければなりません。養生を知らなければ、病がどこから来るのかもわからず、病の根を断つこともできない。薬の使い方だけにこだわっていたのでは、いつまでたっても“病の去る道”しか見えず、“病の来る道”は見えません。だからこそ、先生が他の医者には治せない病を治せるのは、慧眼と用薬の妙だけでなく、“病の由来”を知っているからなのですね。」
田舎医者は深く頭を下げて拝礼した。
「次にまた疑問が生じたら、必ずもう一度ご教示を仰ぎに参ります。先生、どうかそのときはまたお力をお貸しください」
田舎医者が帰ったあと、すぐに指月はノートに書き留めた。
病を見て源を知ることが大切である。
薬を議する前に、まず病を議する。
病がどうやって生じたのかがわからなければ、根治は難しい。
藁本が腹中の筋腫や腹痛を治すのは、瘤を溶かしたり痛みを止めるのではなく、
膀胱経の気化を高めて寒を散らし、経脈を通じさせることで、痛みを自然に止めるため。
『本草正義』にはこう記されている:
「藁本は、婦人の疝瘕、陰部の冷えによる腫れと痛み、腹中の痛みに用いる。
これらはすべて“清陽不振”“厥陰の気が鬱して昇らない”ことに起因する。
温めて和し、昇らせて持ち上げ、結を解き寒を除くことで、激しい痛みも治まり、疝瘕も除かれる。
だが、陰虚内熱や肝の絡脈に結滞がある疝瘕や痛みに対しては、藁本の適応ではない。」
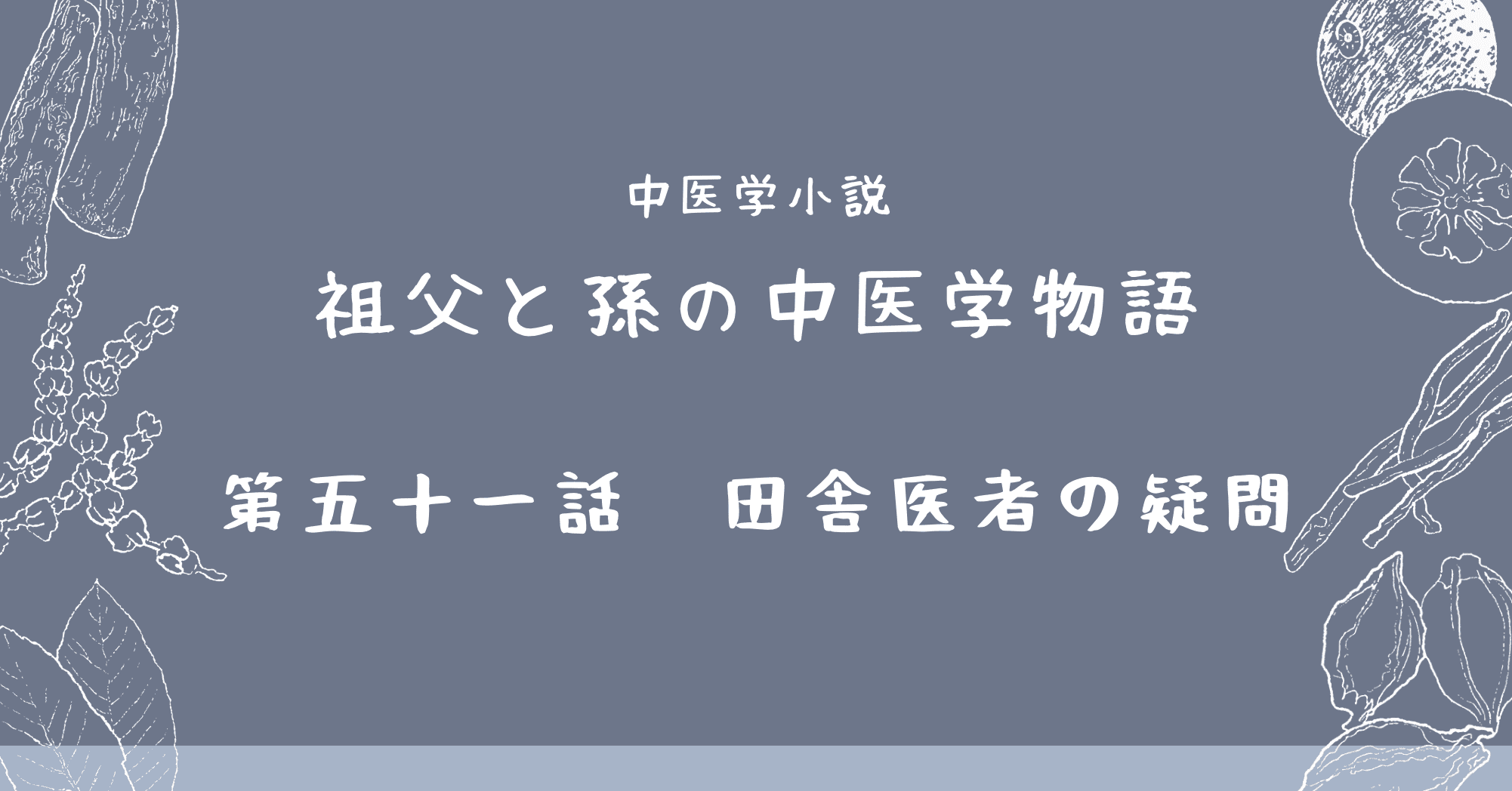
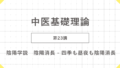

コメント