南方では雨が多いため、雨に濡れたり、風寒に晒されたりして、風寒痺証になる患者が少なくない。
ある老人がいた。
若い頃は雨の中でも平気で働いていた。
周りから「雨を避けた方がいい」と忠告されても、「帰って風呂に入れば大丈夫だ」と取り合わなかった。
そんな生活を長年続けた結果、年を取る頃には、頭痛・鼻づまり・腰背の痛み・膝の痛みが出てきた。
目はかすみ、耳鳴りもするようになった。
ようやく事の重大さに気づいたときには手遅れで、雨の中での作業を避けるようになったものの、既に病は根を下ろしていた。
天気が少し変わるだけで、これらの持病が次々にぶり返す。
老人は悔やんでも悔やみきれなかった。
「老いて病むは、壮年に招いたもの。衰えてから残る害は、盛んな時に作ったもの」
これはよく言われることだ。
だからこそ、元気盛んな若いときほど、慎重に行動すべきなのだ。
勢い任せの無茶は身を滅ぼす。
昔の人はこうも言う。
「老人の言うことを聞かぬと、すぐに痛い目を見るぞ」
歳を重ねた人々は、風霜を耐え、病苦を味わってきたがゆえに、物事の本質を深く、遠くまで見通しているものだ。
汗をたっぷりかいた後に冷水で体を洗ってはいけない。
雨に濡れたらすぐに乾いた服に着替えること。
そんな些細な習慣が、実は健康に大きな影響を与えているのだ。
細かいことに気を配れるかどうかが、健康という人生の成功と失敗を分ける。
そして今、この老人は杖をつきながら、茅葺の家の戸を叩いた。
「最近は、頭も腰も痛むし、手足の関節も思うように動かない。時々足がつってしまうし、鼻は詰まるし、目もかすんで、耳もボワンボワン鳴ってね……」
訴えられるまま、指月は横でせっせと記録を取りながら、治療法を考えていた。
だが、祖父はというと、いつものように煙草をくゆらせながら、まるで聞いていないかのように平然としていた。
老人はこれを見て、「この二人、本当に話を聞いているのか?」と不安になり、同じ話をもう一度、最初から繰り返した。
そのとき、祖父は初めて口を開いた。
「指月、この病をどう治す?」
指月は答えた。
「風寒が表を塞ぎ、気血が不足し、経絡は通じず、さらに肝気も鬱滞しているようです。ですので、風湿を祛い、気血を補い、経絡を疏通し、気機を調えるべきかと思います」
祖父は微笑んで言った。
「彼の左の脈象はどうだった?」
「左の脈は鬱滞していて、上がってくる力がありません。」
「左の寸・関・尺は何を主っている?」
「心、肝、腎です」
「それだけか?」
指月は首を傾げ、思い出せずにいた。
そこで祖父は言った。
「督脈もだ」
――督脈は人体の陽気を総括する大黒柱。五臓六腑の陽気が上昇できないとき、それを支えるのがこの督脈。督脈が通れば、巅頂に至り、毛孔や鼻孔を開き、そして“頭は諸陽の会”と言われる通り、全身の陽気は頭部に集まる。もし督陽が昇らなければ、陽気不足により、頭痛、目のかすみ、耳鳴り、鼻づまり、全身の痺れや痛みとなって現れる。
「この多岐にわたる症状を、一つの薬で解決できるものがある。督脈を通じて諸症を解く薬だ。それが何か思い浮かぶかい?」
指月はしばらく考えたが、答えが出なかった。
これまで督脈に働く薬など、聞いたことがなかったからだ。
祖父は諭すように言った。
「病症は一群の蜂のようなもの。蜂を捕えるには網で一網打尽にするのではない。女王蜂をおさえれば、群れは自然と収まる」
門の外には数箱の養蜂箱があった。指月も女王蜂さえおさえれば、全ての蜂はおのずと従うことを知っていた。
「だから病を治すときも同じ。主証を押さえることが大事だ。核心さえ掴めば、あとの症状は自然と解けていく」
「では、この病の王は何でしょうか?」
祖父は微笑みながら答えた。
「それは“年老いて体が衰え、督陽が昇らず、風寒が体表を閉ざし、清陽が塞がれている”ことに他ならない」
「では、どう治すのでしょう?」
「たった一味――蒼耳子(そうじし)を粥にして食べる」
指月は驚き、『神農本草経』を開いた。そこにはこう書かれていた。
「蒼耳子は頭寒痛、風湿周痺、四肢拘攣痛を主る」
まさにこの老人の悩む、頭から足先までの痺れと痛みに合致していた。
祖父は、この複雑な病態をたった一味の薬で解き明かしたのだった。
老人には、蒼耳子と粳米を一緒に煮て粥にして食べさせるように指示した。もし粥が面倒なら、蒼耳子を粉にして煎じても良いと言い添えた。
老人はこの方法を続けた。
半月ほどで鼻は通り、頭痛は消え、全身の痺れや痛みは大きく軽減した。手足のこわばりも解け、目のかすみや耳鳴りまでもが改善したという。薬粥を食べ終える頃には、頭がすっきりして晴れ渡るようだった。
『本草綱目』には、「蒼耳子は頂門(頭頂)と脳を通じさせる」とある。
このように、お金をかけず、多年にわたる持病を治すことができる簡単で安価な処方――その効果を目の当たりにした老人は、この薬のことを村中に広めた。
農村では風寒湿による痺れ痛みに苦しむ者があまりに多かったからである。
督脈の陽気が昇らず、腰・背・頸・頭・脳・各種感覚器官にまで陽気が届かない。
そんな症状には、蒼耳子こそが最良の一薬だった。
蒼耳子は督脈を通じて陽気を引き上げ、風寒湿を追い出す薬なのだ。
指月は小さなノートに、こう書き記した。
『本草備要』曰く、
「蒼耳子は風湿を発散させ、上は脳頂に通じ、下は足膝に至り、外は皮膚に達す。頭痛・目のかすみ・歯痛・鼻炎を治す」
何廉臣曰く、
「脳風頭痛・閉塞には必ず蒼耳子を用いるべし。蒼耳子は清陽の気を巅頂まで昇らせることができる」
『聖恵方』曰く、
「蒼耳子粥は、目のかすみ・耳鳴りを治す。また散剤として煎じてもよい」
蒼耳子は督脈を通じ、督陽が昇れば、全身の陽気もまた通達し、風寒を追い払うことができる。
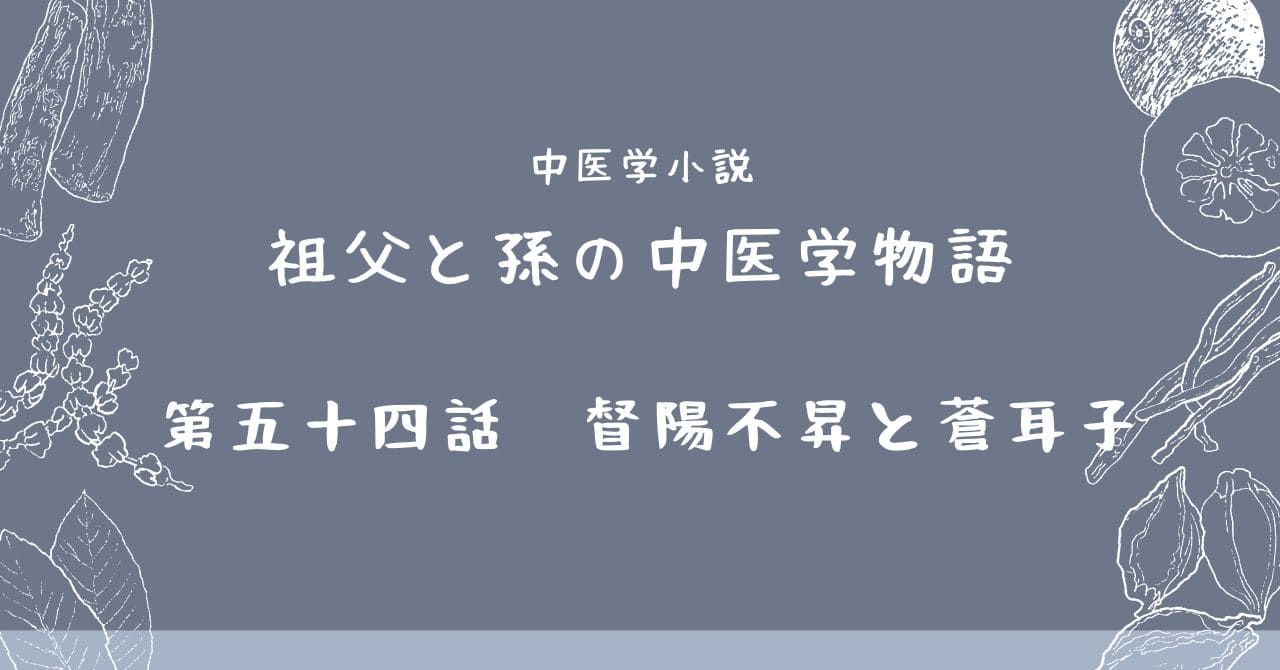


コメント