指月はこれまで多くの典籍を読みあさったが、どこにも「蒼耳子が督脈を通る」などという記述は見つからなかった。
そこで祖父に尋ねた。
「この“蒼耳子が督脈を通る”っていう説はどこから来たの?」
祖父はその言葉を聞いて、しばらく深い回想に沈んだあと、静かに語り始めた。
「それはね……数十年前のある出来事にさかのぼるんだ。この“蒼耳子が督脈を通る”という話は、ある老道医から伝授されたものなんだよ。」
「老道医……? 初めて聞きました」
祖父はうなずきながら語った。
「その老道医は人里離れた深い山林に一人で住んでいた。性格は孤高で、世間とは交わらなかった。人々も、よほど手に負えない難病でなければ、軽々しく彼のもとを訪れることはなかった」
「どうしてですか? 病気を治せる先生なら、みんなから慕われるのでは?」
「それがな……彼はハンセン病(麻風病)の患者たちと共に暮らしていたんだ。彼らの病を癒やし、痛みを和らげることに尽くしていた。人々は彼を“異端”と見なし、恐れて近づこうとしなかったんだ」
「麻風病……それって、顔も崩れて、手足も壊死して、最後はひどい苦しみの中で死んでしまう病ですよね……。」
祖父は目を細め、淡々と話を続けた。
「そうだ。だが、老道医は恐れず、忌まわしがらず、ただただ彼らを救いたい一心で、日々薬を調合していた。そしてその彼が、数多くの難病を、ただ一味の“蒼耳子”を使って治していたんだ」
「ただ一味の……?」指月は目を丸くした。
「そうだ。もちろん、証に応じて薬味を加減はするが、その軸となるのはいつも蒼耳子だった。まるで神仏の加護でもあるかのように、効き目が現れるのだ」
祖父の表情は真剣だった。
「当時、町でも手に負えない数例の難病患者がいた。名のある医者たちも皆お手上げだった。私は彼らを連れて、老道医の住む山中へと向かった」
「老道医はどう対応したのですか?」
「毎日、彼は薬草を煉り、麻風病の研究に集中していた。彼にとって町の人間の難病など、関心外だった。だから最初は、患者たちの懇願にも耳を貸さず、山を降りるよう命じてきた」
「それでも……?」
「それでも、患者たちは山を下りなかった。彼の門前にひれ伏し、雨に打たれながら何日も待ち続けた。その真摯な想いに、ようやく心を動かされた老道医は、重い口を開いたんだ」
「そして……治したんですよね?」
祖父は、静かにうなずいた。
「そう。すべての症状に共通するのは“陽気の閉塞”だった。そして彼は、督脈の不通が諸症の根源であると看破し、蒼耳子で督陽を通じ、清陽を頭頂へと昇らせることで、病の根を一掃した。以来、私はこの薬の妙を身をもって知り、今に至るまで、必要なときには必ず“蒼耳子”を処方するのだよ」
指月は首をかしげて尋ねた。
「全部、蒼耳子で治したって……どんな“難病奇病”だったのでしょうか?」
「最初の症例は“頭風”だ。十年来の慢性頭痛で、何度治療しても効果がなかった。だが老道医は、蒼耳子・天麻・白菊花の三味だけで、一服で効果を現し、三服で完治させたんだ」
指月は思わず手を打ち、声を弾ませた。
「妙技ですね! 蒼耳子は督脈を通じて清陽を頭頂へ引き上げ、風寒湿による痺痛を発汗によって解く。そこに天麻・菊花を加えることで、肝風を鎮め、肝胆の昇り過ぎた陽気を下げる……これはまさに“督脈で陽を昇らせ、任脈で陰を降ろす”、昇降調和の絶妙な方剤ですね!」
祖父はさらに続けた。
「二例目は産後の婦人だった。出産後、全身の皮膚が数年間ずっとかゆくてたまらなかった。特に酒に触れると、かゆみがひどくなる。こんな体質であれば、普通の医者なら“酒を禁じろ”と言うだろうな。さて、指月、お前ならこの症例にどう処方する?」
指月は腕を組んで考え込んだが、答えが出なかった。
「うーん……わかりません……」
祖父はニヤっと笑った。
「正反対のやり方をとったのさ。老道医は“以毒攻毒、以酒引薬”の理を用いた。つまり、酒を禁じるのではなく、“酒を薬引として使う”ことで、長年体内に潜んでいた風邪と湿気を一気に発散させたのだよ。」
「ええっ! 酒を使ったんですか? 一体どうやって?」
「蒼耳子の花、葉、種子を等量で粉末にし、毎回酒で服用させた。数日でかゆみが静まり、数年苦しんだ頑固な風疹も治まった。その後、たまにぶり返しても、同じ方法で服用させるとすぐに治った」
指月は目を輝かせて言った。
「すごい……“禁ずる”のではなく、むしろ利用して“通じさせる”という考え方。身体の反応に目を向けて、症と体質を同時に調えたわけですね」
祖父はうなずいた。
「そうだ。理にかなっていれば、正も邪も無いのが中医の妙味。たとえ毒であっても、用い方しだいで妙薬になる。これが老道医の胆力と見識なんだ」
次第に、指月の中に、薬の味だけでなく医の哲理が、少しずつ沁み込んでいくのだった。
指月は興奮気味に言った。
「それで? まだ他の例もあるのでしょうか?」
祖父は静かに煙草を一服し、ゆっくりと語り出した。
「もう一つある。これが三つ目で、最も頑固で、最も毒の強い“癰(よう)・疔(てい)”だった。十数年にわたって、何度も再発し、どんな薬を使っても効かず、名医たちも手をこまねいていた。その病を……なんと老道医は、蒼耳子一味だけで治したのだ」
「えっ!? 蒼耳子一味だけで、そんな毒疔を!? どうやって?」と、指月は乗り出すように尋ねた。
「蒼耳子を炒って粉末にし、黄酒で服用する。さらに、外用としては鶏卵の白身(蛋清)を患部に塗る。この“内服と外治の合わせ技”で、疔毒が根こそぎ抜けて、再発することもなかったのだ」
指月の目はますます輝いた。
「まだ他にもありますよね?」
祖父は笑いながら言った。
「あるとも。けど、それはまた今度ゆっくり話そう」
指月は名残惜しそうに言った。
「えー、終わりですか? 本当に? もっと知りたいです……」
祖父はポンポンっと指月の頭を叩いた。
「まだ続きがあるさ。あのとき、私は実際に老道医の治療をこの目で見て、その効果に深く感銘を受けた。そしてこう思った。この人こそ、私の師と仰ぐべき人物だ。どうしても教えを受けたい!」
「それで弟子入り志願したんですね?」
「そうだ。山の奥まで追いかけて行って、礼を尽くして頼んだんだよ。ところが老道医は、こう言い放った。
『弟子はとらぬ。おまえも早く山を下りろ』」
「ええっ、それで諦めたのですか?」
「いや、そう簡単には諦めなかった。老道医が最初に病人を拒んだのも、誠意が足りないと見抜いたからだ。なぜなら、病人たちが心から願い続けた結果、最後は診てくれた。“誠意に勝る力なし”ということだ。だから私も、あの小屋の前で何日も待った。一日、二日、三日……老道医はまるで私など見えないかのように無視し続け、ついにはホウキで追い払おうとした」
「それでも……?」
祖父の眼差しは遠くを見つめ、懐かしむような口調で言った。
「そう、それでも私は動かなかった。なぜなら、医を学びたいという思いに、一点の迷いもなかったからだ。四日目も私は山を下りなかった。その日は大雨が降り、全身ずぶ濡れになり、空腹と寒さで心が折れそうになった。『無理なのか……』そう思ったそのときだった。老道医が、ふいに小屋の外に出てきてこう言った」
「小僧、下山したら蒼耳子をよく研究しなさい。なぜそれが督脈を通るのかを考えなさい。どうすれば督脈を調えて諸病を治せるのか、じっくり考えなさい。きっと将来、医道において何かしら成すものがあるだろう」
そう言い残すと、老道医は身を翻して去っていった。
「……ああ、これで師弟の縁も終わったのかもしれない」
そう思いながら、私は寂しく山を下りていった。
ーーー
指月は目を輝かせながら言った。
「なるほど! 蒼耳子が督脈を通るっていうのは、老道医の言葉だったのですね。祖父が難病を治すとき、督脈から論じていくやり方も、そこから学んだものなんですね!」
祖父は静かにうなずき、微笑んだ。
「そうだよ。人の脳頂に清らかな陽気が満ち、三花(神・精・気)が頂に集まれば、たとえ病を得ても、重くはならない。その後私は『道蔵』や多くの道家医学の書を読んだ。すると気づいたことがある。真の道医たちは、みな“三花聚頂、五気朝元”を根本としていた。この理念が、あの老道医が蒼耳子を督脈に通すという処方を行い、酒で陽気を引き上げた理由なんだよ。お前も将来、臨床でじっくり試してみなさい。そして自分の身体で“内証”してみることだ。きっと道医の宝が、まだまだ掘り出せるはずだよ」
「三花聚頂、五気朝元」は道教内丹学における高次の修練境地を表す術語で、精・気・神を一体化させて頭頂に集め(形神合一)、「五臓の気」を調和させて先天の本源へと還すことで、心身と天地が通じる無碍の循環状態を実現することを指す。
祖父は少し間を置き、しみじみと続けた。
「本当はこういう話は、お前がもっと成長してから教えるつもりだった。けど、今日はお前が自ら問いを発してくれた。それだけで十分だ。中国の伝統医学が、漢唐以降で次第に衰えていったのは、民間の偏方(即効薬)ばかりに注目し、医理の探究を疎かにし、何より“医道の体得”を忘れてしまったからだ。本当の医道とは、口先だけで学べるものではない。身体で行じ、証してこそ初めて会得できるものなんだ」
指月は、祖父の話を胸に刻んだ。
「医とは、理を学び、道を修めること。薬とは、術の一端にすぎぬ」
そういう教えが、静かに彼の心に根を下ろしたのであった。
巅峰の道医たち——たとえば孫思邈、陶弘景、華佗、葛洪——彼らに共通するのは、いずれも「医と道をともに修め、事理に通じ、知行を一体とした人物」であったということだ。
彼らは自己の内なる修養を重視する一方で、外的な薬物の運用にも精通していた。
どちらか一方を軽んじることはなかった。
そのような姿勢こそが、医学を一歩一歩と高みへと導いたのである。
だからこそ、もし伝統的な中医学の道を進みたいのならば、道徳と技術をひとつにし、ともに修めていく以外に道はないのだ。
ゆえに曰く、「道なくして術は行われず、術なくして道は遠い」と。
祖父は続けてこう言った。
「指月よ、お前はこれから医書や古典ばかりに埋もれるのではなく、もっと人間の道徳というものを味わいなさい。世の中の仕組みに明るくなれば、それもまた医理となるし、人情に通じれば、それもまた薬物となるのだよ」
指月は、すべてを理解できたわけではなかったが、こくりとうなずき、ノートにこう書き記した——
医の道は、最終的には医術を借りて「道と徳」を修めることである。
道医とは、道徳をもって医を行い、術を用い、そして医学を自らの身体で体得する者である。
《本草匯言》にはこうある:
「諸風の眩暈、または頭脳の激しい痛みに対しては、蒼耳子三両、天麻・白菊花をそれぞれ三銭用いる」
《聖恵方》にはこうある:
「婦人の風による瘙痒性のじんましんで、全身のかゆみが止まらないときは、蒼耳の花・葉・種子を等量取り、細かく粉末にして、酒と共に服用する」
《経験広集》にはこうある:
「悪性の腫瘍(疔瘡)を治すには、蒼耳子五銭を軽く炒って末にし、黄酒で服用し、さらに卵白を患部に塗れば、腫瘍の根が抜けて再発しない」
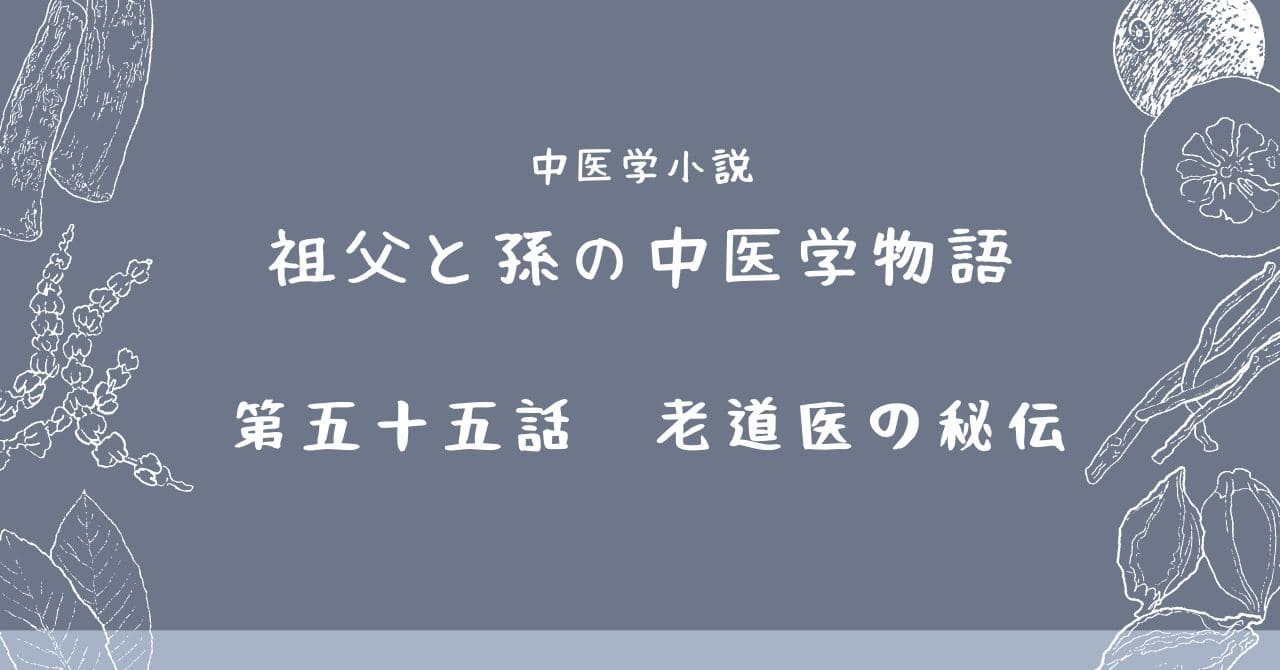


コメント