三分治、七分養
俗に「三分治、七分養」と言われるように、多くの場合、慢性疾患や難治性の病気は、医師がすべてを治療することはできません。
薬の効果はせいぜい三割に過ぎず、残りの七割は、養生によるものです。
もし適切な養生を怠れば、たとえ肩や腕の小さな痛みであっても、名医を困らせることになるでしょう。
村に一人の壮漢(強く勇ましい男)がいました。
体格は立派で元気なのが自慢でしたが、五、六年前から肩周りの痺れと痛みに悩まされるようになりました。
最初の頃は、薬を飲めば二〜三ヶ月は痛みが治っていました。
しかし、次第に効果は薄れ、一ヶ月しか効かなくなり、さらに一週間しか効かなくなり、ついには薬を飲んでも全く効かなくなってしまいました。
彼は医者を求めて、村や県内の医者をくまなく探し回りました。
名医がいると聞けばすぐに駆けつけました。
ただの肩と腕の痛みにもかかわらず、名の知れた何十人もの医者に診てもらった結果、全員に顔を覚えられてしまいました。
医者たちは、治らない上に、男がしつこく何度も訪れてくるため、気まずくなり、もはや男に処方を出すことを拒むようになりました。
そんなある日、男はついに痛みで仕事ができなくなってしまいました。
肩から肘にかけての痛みがひどく、まったく動かすことができません。
かつてはその強靭な体で、水の入った大きな桶を二つ持ち上げることができたのに、今では自分の腕すら持ち上げることができなくなったのです。
彼は両腕をだらりと垂らしたまま、茅葺き屋根の家にやってきました。
もはや手を使って戸を叩くことができず、代わりに頭を戸に打ち付けました。
「ゴン! ゴン!」
指月は、あまりにも大きなノック音に驚きました。
(これは病状が深刻なせいなのか、それともただの乱暴者の仕業なのか?)
戸を開けると、そこには大きな体をした壮漢が立っていました。
指月は少し腹を立てながら言いました。
「ノックするにも礼儀があるでしょう? そんな乱暴に叩いたら、この竹の戸が壊れてしまいます!」
壮漢は申し訳なさそうに、顔を赤らめ恥ずかしそうに言いました。
「すみません……。でも、本当にどうしようもなくて……。両腕がまるで凍りついたみたいに、まったく動かせないんです。だから仕方なく、頭でノックしました……」
指月はハッとしました。
(まさか、これがあの噂に聞く『氷凍肩(凍結肩)』。最も重い肩関節周囲炎では!?)
「それなら仕方がありませんね」
そう言うと、彼を診察机へと案内しました。
祖父は相変わらず古書を読んでいて、先ほどの大きなノック音が聞こえていなかったかのようでした。
指月が「祖父」と呼ぶと、祖父はようやく本を置きました。
祖父は振り返り、その壮漢を見つめました。
「脈を診るので、手を机の上に乗せて」
彼は手を机に置くのも苦労していました。
歯を食いしばって痛みに耐え、ようやく手を置くことができました。
祖父は尋ねました。
「風にあたるのが嫌か?」
「はい」
「汗をかくか?」
「はい」
祖父は指月に向かって言いました。
「お前も脈を診なさい。脈はどうだ?」
指月は脈を診てしばらく考え、「脈は浮緩で、少し遅いです。舌苔は薄白です」と答えました。
「それではどうすればいいのだ?」
「桂枝加葛根湯を使います!」
指月は自信を持って答えました。
祖父は微笑みながら肯いて、「それなら早く処方を書きなさい」と言いました。
指月はすぐに筆を取り、一枚の微かに黄ばんだ宣紙を広げました。
その処方の字は、とても子供が書いたとは思えないほど堂々としており、少なくとも20年は修練を積んだ者の筆跡のように見えました。
指月がわずか数年で書き上げた字は、普通の人が何十年もかけて練習する量をはるかに超えていたのです。
最初の頃、彼はまだ紙すら使わず、木の葉に水をつけて字を書く練習をしていました。
今の指月は、まさに「筆を揮えば大沢に龍蛇が舞い、深山に柿の葉を採りて空に書す」といった境地に達していたのです。
その壮漢は、宣紙に書かれた処方を見て驚きました。
「えっ、たったこれだけですか?」
彼が知る医者たちは、一度の処方に十数種類もの薬を用いるのが普通でした。
しかし、今回の処方はほんの数種類しか記されていません。
「私の病気はこんなに重いのに、こんな少しの薬で本当に治るのでしょうか?」
彼は疑わしそうに言いました。
祖父は微笑み、ゆっくりと語りました。
「尿の泡は大きいが、何の重さもない。だが、秤の錘(おもり)は小さくとも、千斤(500kg)をも押さえることができる(秤砣虽小压千斤:見かけは小さくても侮れないということのたとえ)。薬が証に合えば、一碗の湯薬で治るが、証に合わなければ、船いっぱいの湯薬を飲んでも無駄なのだよ」
壮漢は「なるほど」と肯きましたが、それでも不安は消えませんでした。
「先生、私はこの病気をもう五、六年も治療しています。でも、治るどころか、どんどん悪化しているんです。たくさんの医者に診てもらって薬を処方してもらいましたが、薬を飲んでいる間は少し良くなっても、やめるとすぐに悪化します。今ではもう仕事すらできません。こんな状態で、これからどうやって生活していけばいいのか不安なんです……」
彼は懸命に訴え続けました。
「だから、私は先生の評判を聞いて、はるばるここまで来たんです。本当にこの薬で私の腕は治るんでしょうか?」
祖父は首を横に振りながら言いました。
「この薬では、あなたの病気は治らないよ」
この言葉に、壮漢は大きく落胆しました。
指月も驚きました。
祖父はこれまで「薬で治らない」と一度も言ったことはなかったのです。
それに、祖父は指月に『黄帝内経』を読ませ、こう教えていました。
「病とは人体に本来備わっているものではない。ゆえに、得ることができるならば、取り除くこともできる。治せないと言うのは、まだその術を得ていないだけである」
(なぜ祖父は「治せない」と言いながら、処方をしたのだろう?)
祖父はようやくゆっくりと口を開きました。
「薬は病の三分しか治せない。あとの七分は、あなた自身の養生次第だ。あなたは自分で病を治せるのに、なぜ医者を探し回るのだ?」
壮漢は唖然としました。
「自分で病を治せるなら、こんな苦労して医者を探したりしませんよ! 自分で治せる病なら、とっくに治しています! 私は薬を煎じることすらできないんですよ。何をするにも人に頼まなきゃならないし、手が痛くて戸を叩くことさえできない。それなのに、自分でどうやって治せるというんですか?」
祖父は、「ふぅ」と息を吐くと、核心を語り始めました。
「薬は病の出口を示すことはできても、病の入口を閉ざすことはできない。あなたは考えたことがあるか? そもそも、腕の痛みはどうやって始まったのか? この病を得る前、あなたは何をしていた?」
壮漢は眉をひそめ、記憶をたどりました。
そして、しばらく考えてから答えました。
「あれは六年前の夏のことでした。妻と夫婦の営みを終えた後、胸のあたりが火照って仕方なくなったので、涼もうと思って窓をすべて開けて寝たのです」
「それで?」
「それで、腕を窓枠の上に置いて、風に当てながら眠りました。翌朝起きたら、腕が少しこわばっていましたが、あまり気にしませんでした。時々痛むようになりましたが、気にせず放っておいたのです」
「それで?」
「でも、時間が経つにつれて痛みがどんどん悪化し、ついにはこうして医者を探し回るようになってしまったのです……」
「今も寝るときに窓を開けているのかな?」
「さすがに全部は開けていません」
祖父はさらに尋ねました。
「今、寝るときに腕を布団の中に入れているか? それとも布団の外に出しているのか?」
壮漢は考えることもなく即答しました。
「私は寝るときに、手を布団の中に入れたことがありません」
指月は笑顔を浮かべて言いました。
「祖父、分かりました」
「何が分かったんだ?」
指月はある出来事を思い出したのです。
「先日、私が首を寝違えたことを覚えていますか? 寝るときに布団をかけず、涼しさを求めて窓を開けていたため、風寒の邪気が体を傷つけてしまったのが原因でした。これからはそんなことは絶対にしません。寝るときにはきちんと布団に入り、腕を布団の外に出すような真似はしません。だって、風に当たって冷えるのが怖いのですから」
壮漢は驚いたように、指月の言葉をじっと聞いていました。
そして、ようやく自分の病気の、本当の原因に気づいたのです。
「ははっ、この大きな体を持っていても、目に見えない冷えが原因で、こうも仕事ができなくなるとは。どうしてこれまでの医者は、私にこのことを教えてくれなかったのでしょうか?」
祖父は静かに言いました。
「養生には『座るときも寝るときも、風に当たらないようにし、眠るときは手を布団の中に入れるべきだ』という言葉がある。少しでも養生の心得がある者なら、あなたの肩や背中の痛みが治らなかった理由が分かったはずだ。医者たちは、病は診ていたが原因を診ていなかったのだろう」
祖父は指月に命じ、処方の最後に次の一行を書かせました。
「房事の後、精気が外に漏れ、気血が虚となる。その状態で養生を怠り、ただ涼しさを求め、窓を開け腕を露出したため、風邪が虚に乗じて侵入し、肩部の経脈を痺阻させた。桂枝加葛根湯を用いて、解肌発表し、営衛を調和させ、経脈を疏通せよ」
それから一ヶ月後――
壮漢が再び茅葺き屋根の家にやって来ました。
しかし、今回は自分の病を診てもらうためではありませんでした。
彼は笑顔で言いました。
「先生、ありがたいお言葉をいただき、本当に感謝しています! 先生の言葉は、お金や、どんな薬よりも価値がありました。処方された薬を飲み、寝るときに手を布団の外に出さないようにしたのです。すると、すぐに肩や腕の痛みがなくなりました! 先生が言っていた『自分で病を治せる』という意味がやっとわかりました! 結局、私は自分で病気を作っていたんですね。無知のせいで、自分で自分の体を傷つけていたんですね」
彼の言葉には、深い気づきと感謝の念が込められていました。
指月は患者の病気が治ったことは嬉しかったのですが、気持ちがモヤモヤしていました。
『なぜ桂枝湯が経脈を疏通させ、痺痛を軽減できるのか?』
指月の中で、この問題が解決していなかったからです。
指月はすでに、「頸や肩の痺痛が、風寒による外からの束縛が原因で生じているのであれば、桂枝加葛根湯を使う」ということを知っていました。
しかし、なぜこの処方なのか?
なぜ他の薬ではなく、桂枝加葛根湯なのか?
指月は、薬の使い方の裏にある「道理」を追求するタイプでした。
納得できる答えが得られるまで、絶対に諦めませんでした。
そこで、彼は数日間にわたり祖父の周りを付きまとい、何度も何度も質問しました。
「梨の味を知りたければ、自分で食べてみることだ」
しかし、指月はそんな言葉には納得しません。
「祖父! ちゃんと説明してください!」
彼のしつこさに根負けした祖父は、ある「実験」を思いつきました。
「今夜は冷えるな。よし、指月よ。井戸へ行って、桶に水を汲んできなさい」
指月は祖父の考えを測りかねながらも、言われた通りにしました。
「この水を外に置いておきなさい」
小指月はますます混乱しました。
(祖父は一体何を考えているんだ? 何の実験なんだ?)
祖父の計略はいつも不思議で、簡単には理解できません。
指月は考えても仕方がないと思い、言われた通りにしました。
翌朝、外は冷たい風が吹きつけ、吐く息は白く染まっていました。
祖父は、外に置いておいた桶の水にそっと手を触れました。
水は氷のように冷たく、祖父はすぐに手を引っ込めました。
「指月、早くこっちへ来なさい!」
指月は「待ってました」といわんばかりに、すぐに駆けつけてきました。
「指月よ。お前は桂枝がどうやって経脈を疏通して痺痛を止めるのか知りたいと言っていたね? 今日は特別に教えよう。よく見て、しっかり聞きなさい。 今日のことは、一生忘れられない体験になるだろう」
指月は興奮しました。
(何日考えてもわからなかったこの謎の答えを、ついに教えてくれるのか! でも、祖父って本当にじらすのが上手いよなぁ。こんなに引っ張らないで、早く教えてくれればよかったのに……。この数日間、私がどれだけ悩んだと思ってるんだ!」
小指月は文句を浮かべつつも、それ以上にワクワクしていました。
祖父は真剣な表情で言いました。
「指月、今から言うことをよく聞くんだよ」
指月は神妙な顔つきで、こくりと肯きました。
「手をこの水の中に入れなさい。しかも、腕全体をしっかりと浸すんだ。さあ、やってみなさい」
小指月は驚きました。
(えっ? こんな寒い日に、水の中に手を入れるの? しかも腕を全部!?)
指月は祖父の意図を測りかねながらも、言われたとおりに手を水の中へ入れようとしました。
指先が水に触れた瞬間、全身に衝撃が走りました。
「冷たっ!」
指月は、手を離そうと思いましたが、「ついに答えがわかるんだ!」と思い、「えい!」と勢いよく両手を水の中に突っ込みました。
しかし、すぐに後悔しました。
目を大きく見開き、苦悶の表情を浮かべました。
(な、なんだこれは!? こんなにも冷たいのか!? まるで氷の洞窟に手を突っ込んだみたいだ……)
彼はすぐに手を引き抜きたくなりましたが、祖父に約束した以上、最後までやり遂げなければなりません。
指月は「途中で投げ出す人間」が何よりも嫌いでした。
だから、自分自身は絶対に途中で投げ出さないと決めていました。
「約束を破るなんてありえない!」
そう思いながら、歯を食いしばって耐えました。
一方、祖父はというと……指月が頑張っているのを見もせずに、悠々と煙草をふかしていました。
指月を一瞥することもなく、ただ静かに煙を吐き出し、その煙が朝の澄んだ空気の中でゆらゆらと舞っていました。
このキリッと冷え込んだ朝を楽しむかのように、石の上に座り、足を組み、遠くの景色を眺めていました。
一方は、冷たさに歯を食いしばり、手を震わせながら必死に耐える少年。
もう一方は、温かな煙をくゆらせながら、何も気にしない風情の老人。
氷と炎のように、まったく対照的な二人の姿がそこにはありました。
指月にとって、一秒一秒が拷問のように長く感じられました。
何度も祖父を呼ぼうとしましたが、我慢しました。
しかし、ついに限界が訪れました。
「祖父!!!」
指月は叫びました。
祖父は、ゆっくりと振り向くと、何も知らないふりをして言いました。
「ん?どうした、指月? まだ時間は来ていないぞ」
指月は訴えました。
「手が凍りついて、もう動かせなくなくなってきました!」
祖父はただ微笑みながら言いました。
「答えを知りたくないのか? もし知りたくないなら、もうやめてもいいよ」
何日も考えてもわからなかった「答え」。
ここ諦めてしまえば、せっかくの機会を無駄にしてしまう。
指月は、再び歯を食いしばり耐え続けました。
やがて、祖父はゆっくりと立ち上がりました。
「よしよし、もういい。良く頑張った。さあ、家に入って話そう」
指月は、凍りついた両手をようやく水から引き抜きました。
しかし、手は震え、腕全体がこわばり、まるで氷の塊になったかのように動きません。
(くそぉ、何もかもがカチカチに凍ってる……)
指月は今すぐにでも火に当たり、温かいものを飲みたいと願いました。
なんと――
驚いたことに、祖父はすでに準備をしていたのです。
家に入ると、そこには暖かく燃え上がる火鉢が置かれていました。
「最初から用意してくれていたのですね!?」
指月は、祖父の深謀遠慮さに驚きました。
指月は、先日、頭で戸を叩いていた壮漢と同じように、両腕がだらりと垂れ、まったく上げることができませんでした。
急いで火鉢の前に駆け寄り、両手をかざして温めました。
「あぁ~、温かい! なんて気持ちがいいんだ!」
温かさを感じながらも、まだ指は思うように動きませんでした。
さらに、冷水に長く浸していたせいで、筋や血脈が凍りついたような感覚が残っていました。
ジンジンとした痺れと痛みは、いくら火で温めても、完全には回復しませんでした。
その時、祖父が湯気がたった熱々のスープを一杯、そっと差し出してきました。
指月は、何も考えずにすぐに飲み始めました。
「うわっ、甘くて辛い! でも、めちゃくちゃ美味しいです!」
スープを飲み終えて、わずか十五分後、指月の額にじんわりと汗が滲み出し、凍りついたようだった手が苦もなく動かせるようになりました。
手の痺れや痛みが、すっかり消えていたのです。
指月は、その味に覚えがありました。
「祖父、これは桂枝湯ですね?」
祖父は、「そうだ」と肯きました。
「温めて経脈を疏通し、風寒による痺痛を止める第一方剤、それが桂枝湯だ。甘味は直接気血を補い、辛味は寒冷で凍った血脈や関節を通し、寒気を追い出す。これが、桂枝湯が痺痛を治す仕組みだよ」
すべてがつながりました。
指月は目を輝かせながら自分の頭をパチンと叩きました。
「わかりました! 祖父。もう言わなくて構いません! 答えがわかりました! はははっ!」
祖父は満足そうでした。
祖父は、指月が「自分自身で」医の道を悟ることを何よりも大切にしていました。
決して知識を一方的に詰め込んだり、決まりきった理論を押し付けたりはしませんでした。
祖父のすべての教えは、「指月が独立して考え、自ら体得し、実感をもって医の理を理解する」ためのものだったのです。
「師の言葉をなぞるだけの医者」ではなく、「自らの体験を通じて医道を理解し、応用できる医者」になるために――。
このとき、指月は『黄帝内経』の言葉を思い出していました。
「寒則渋而不行,溫則消而去之」(寒すれば渋滞して行かず、温めれば消えて去る)
「血気遇寒則凝,得温則行」(血気は寒に遇えば凝結し、温を得れば流れる)
「寒主收引,不通則痛……」(寒は収引を主とし、通じなければ痛む……)
つまり、寒さが血脈を収縮させ、気血を滞らせることで痺痛が生じるということ。
そして、それを温めて経脈を疏通させれば、血脈が再び流れ出し、痺痛は解消されるということ。
この病理の流れと、桂枝湯の作用機序を、指月は今朝の実験を通してすべて体感したのでした。
(あぁ、これこそが本当に学ぶということなんだ!)
どれだけ書物を読んでも、どれだけ患者を診ても、どれだけ祖父の話を聞いても、今日のような体験には及ばない。
自分の体で感じ、理解し、納得したからこそ、医道は「生きたもの」になる。
祖父は私に伝えたかったのだ。
医道を心で理解できなければ、どうやって桂枝湯を自在に使い、寒性の痺痛を治せるというのか?
指月は、心の奥底から湧き上がる興奮と感動を抑えきれませんでした。
指月は今、真に「医の道」へ足を踏み入れたのだと確信したのでした。
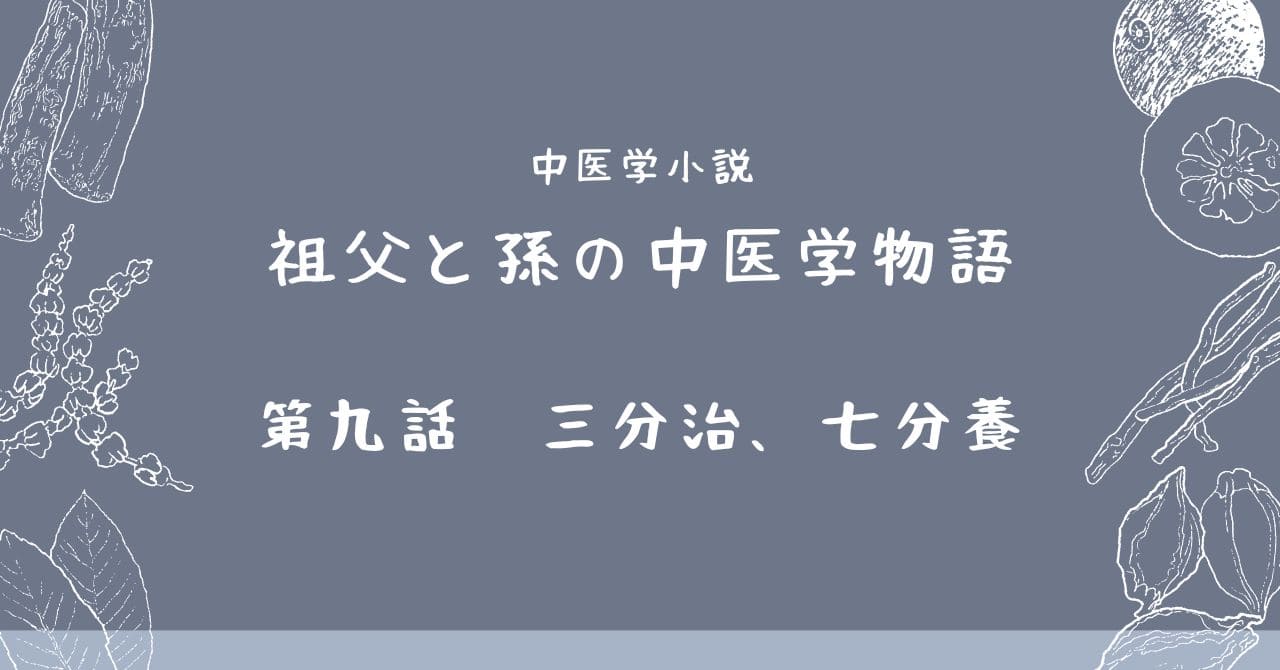


コメント