むかしむかし、清の乾隆帝は、三たび江南を訪れ、身分を隠してひそかに民間視察を行いました。
その目的のひとつは、海寧に住む実の両親に会うことであったとも言われています。
行く先々では、多くの護衛が昼夜を問わず密かに警護し、旅は決して楽なものではありませんでした。
ある日、乾隆帝一行は鎮江に到着し、ある宿に滞在しました。
ところがその晩、乾隆帝の体中に不思議なかゆみが広がり、どうしても眠ることができません。
夜更け、乾隆帝は着替えを済ませてそっと宿を出ると、町の薬店を訪れました。扉を叩くと、中年の店主が戸を開けました。
「夜分遅くに失礼します。草薬を少し分けていただけませんか?」
礼儀正しく整った言葉遣いと、若々しく品のある佇まいに、店主はすぐに彼がただ者でないことを感じとりました。
「どうぞお入りください」
店主は乾隆帝を奥へと招き、茶を淹れてもてなしました。
乾隆帝は灯りを借りると、店主が古い薬書を丁寧に筆写していることに気づき、その勤勉さに心を打たれました。
やがて、乾隆帝はかゆみをこらえながら自らの症状を静かに説明しました。
店主は脈を取り、体を観察しながら、こう診断しました。
「これは疥癬(かいせん)ですね。民間では疥癩瘡とも呼ばれる皮膚病の一種です。治療は可能です。ただし、この薬を使用した後は絶対に掻かないように。もしどうしても掻いてしまったら、その手を口に運んではなりません。この薬草には、強い毒性があるのです」
乾隆帝は興味深く尋ねました。
「その薬草の名は何と申しますか?」
店主は静かに答えました。
「“断腸草”と申します。伝説では、神農が百草を味わった際、この蔓性植物の若葉を噛み、飲み込んだところ、たちまち激しい毒にあたり、腸が断ち切られるような苦しみで命を落としたと言われています。神農が命を落としたこの草は、それ以来、人々から“断腸草”と呼ばれるようになりました」
乾隆帝はその話に深く感銘を受けました。
薬を受け取り、宿へ戻って服用すると、翌朝にはかゆみがすっかり治まっていました。
乾隆帝は再び薬店を訪れ、店主に多額の褒美を贈りました。
そして、店の額に「神農百草堂」という自筆の大きな書を掲げました。
この出来事の後、その薬店の名は大江南北に轟き渡り、人々の信頼を集める名店となったといいます。
おしまい


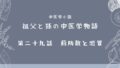
コメント