祖父と指月が薬草採取から戻ってきた頃には、太陽はすっかり昇り、大地はぽかぽかと温かく、山の霧やもやも晴れていました。
指月はいつものように手際よく火鉢を整え、お湯を沸かし始めました。
というのも、祖父には一日のうちに一〜二杯だけ熱いお茶を飲むという習慣があるからです。
ただし、決して飲みすぎることはありませんでした。
「お茶は少量なら胃を健やかにし、食欲を促してくれるが、飲みすぎればかえって脾胃を傷めてしまう。どんなによいものでも、取りすぎては毒になる。ほどほどを知ること。それが本当の満足につながるのだ。足るを知ってこそ、心はいつも穏やかでいられる」
そう語りながら、祖父は湯呑みから一口ずつお茶を味わいました。
そしてふと一首の詩を口ずさみはじめました。
それは《不知足》という詩だった。
一日中奔走するのは、ひとえに空腹を満たすため。
ようやく腹が膨れれば、次は着る物が気になる。
衣食が満たされれば、今度は美しい妻が欲しくなる。
美しい妻を迎え子をもうければ、土地がないのが悩みとなる。
田畑を買い広い地を得れば、今度は馬も船もないと嘆く。
馬やラバを飼えば、今度は官職がないと人に侮られる。
県の役人の地位を得てもまだ満たされず、今度は朝廷で高い地位が欲しくなる。
人の欲が尽きることはない――
もし世の中の人々が真に満ち足りることがあるとすれば、
それは南柯の夢、すなわち幻の中でだけのことだろう。
祖父が詩を歌うその声に、指月は耳を傾けながら、その詩の意味を考えていました。
そのとき、ふと手元が狂って、手に持っていた小さな湯壺を倒してしまいました。
沸き立つ熱湯が彼の小指にかかり、一瞬で真っ赤に腫れ上がりました。
「あぁ! 熱いっ!」
思わず跳ね回りながら、反射的に手に息を吹きかけました。
祖父は振り返り、その様子を見てすぐに察しました。
「やれやれ、またやったな。水火のやけどには、どうすればいいか、覚えているか?」
跳ねながらも指月は叫んだ。
「生姜です。生姜が効くんです!」
「なら、何をもたもたしているんだ?」
祖父のひと言で、小指月はすぐに厨房へ駆け込み、大きな生姜をひとかけ取り出すと、石臼に放り込みました。
そして、火傷していないほうの手で素早くすり潰し、ペースト状にしました。
それを熱で赤く腫れ上がった指に塗りつけました。
すると、あれほど痛かったのが、嘘のように和らいでいきました。
「はぁ〜、ちょっと楽になった。生姜があってよかった……」
翌日には、すでに痛みはまったくなくなり、数日後には跡も残らず完治しました。
この小さな知恵は、体験と共に指月の心に深く刻み込まれました。
その夜、指月は自分のノートにこう書き記しました。
「水火の火傷には、生姜を使うこと」
祖父が常々言っていることがありました。
「医者というのは、病の苦しみを知らなければ、真に病を癒すことはできない。
実際に痛みを味わってこそ、薬の大切さを理解できる。その痛みがあるからこそ、人は心から医術を磨き、苦しむ人々を救おうと決意するんだ。だからこそ、経験は一つたりとも無駄にせず、必ず記録しておきなさい」古来の聖人や賢人たちは、皆そのようにして志を立てた。彼らは自分のためではなく、良き薬と知恵が後の世に伝わり、人々を病苦から救うことを願っていたのだ」
そう言って祖父は、人差し指と中指を立てて指月に向けました。
「医を志す者が医術を高めてゆくには、二つの道がある。ひとつは、古の書物をよく読み、日々必ず新たな学びを得るという心構えを持つこと。もうひとつは、自らの体験を通して薬効を確かめ、その臨床の証を積み重ねていくこと。そしてそれらの経験を、丁寧に記録に残してゆくことこそが、未来の命を救う種となるんだよ」
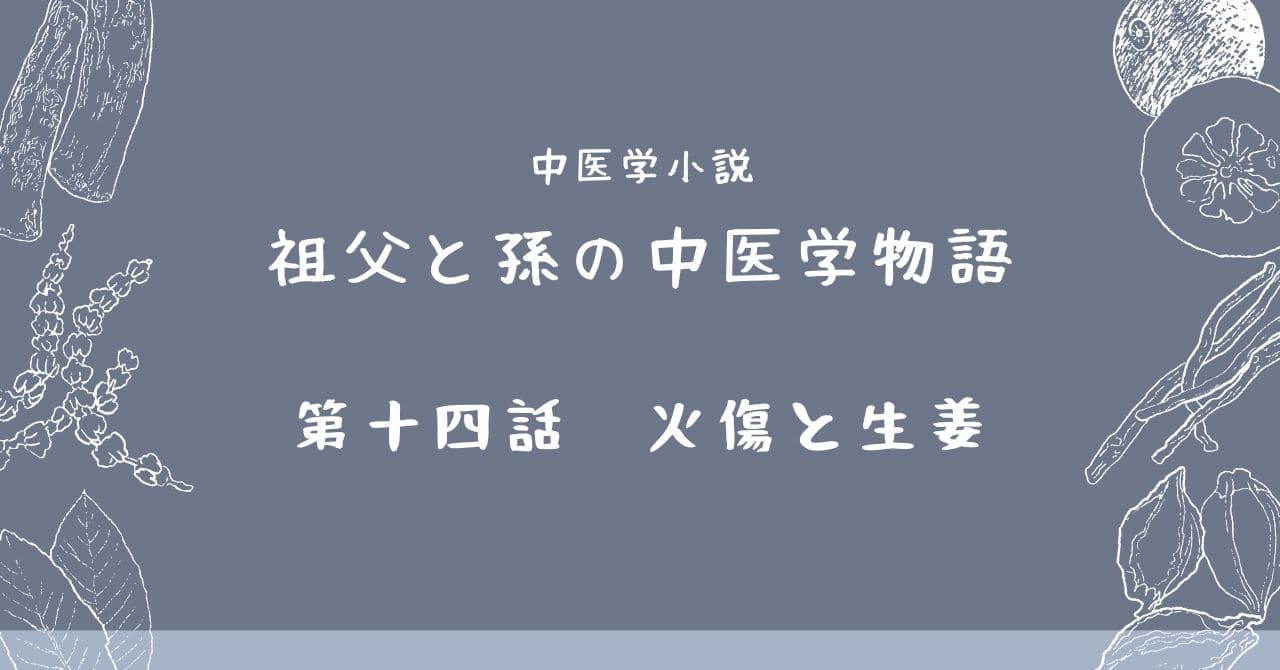


コメント